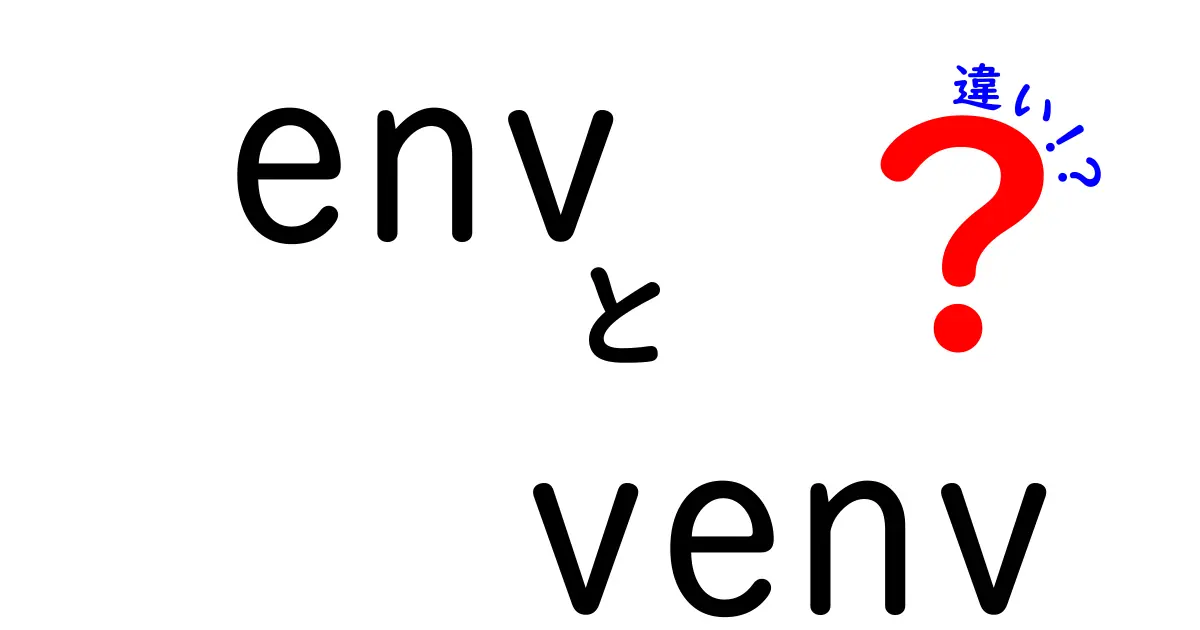

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
envとvenvの違いを理解するための基礎講座
プログラミングを始めたばかりの人が混乱しがちな用語のひとつが「env」と「venv」です。envは環境変数を扱う仕組み、venvはPythonの仮想環境を作る仕組み、この二つは名前が似ていますが役割がまったく異なります。環境変数はプログラムがどう動くかを決める設定値の集まりで、たとえば PATH、PYTHONPATH、DEBUG などが挙げられます。これらはシェルのセッションごとに変えることができ、プログラムの挙動や接続先を動的に切り替えるのに使われます。
一方でvenvは“Pythonの依存関係”をプロジェクトごとに分けて管理する箱のような存在です。仮想環境を作ることで、同じマシンの別のプロジェクトが互いに影響を受けず、特定のライブラリのバージョンを安定させることができます。venvはその箱の中にPythonの実行ファイルとサイトパッケージをまとめて置き、他のプロジェクトと混ざらないようにします。
ここで覚えておきたいのは「envとvenvは別の目的を持つ機能である」ということです。envは環境設定の変更、venvは依存関係の分離を担います。よくある混乱はこの境界線を見失うことです。
またOSごとの違いにも注意が必要です。WindowsとUnix系では、コマンドの呼び出し方やactivateスクリプトの場所が異なる場合があります。基本ルールとしては「環境設定はenv、Pythonの依存関係はvenv」という捉え方を持つと、初学者でも混乱が少なくなります。
実務での使い分けと注意点
日常の開発現場では、まず新しいプロジェクトを始めるときにvenvを作るところから始めます。Pythonの公式推奨である venv を使えば、グローバルな Python 環境を汚さずに済みます。手順は「python -m venv .venv」→「.venv/Scripts/activate(Windows)」または「source .venv/bin/activate(macOS/Linux)」と進みます。 activation すると、PATHが変わり、pythonやpipがvenvの中のものを指すようになります。デフォルトのままでは依存関係は世界共通ですが、venvを使うとプロジェクトごとに違うライブラリの組み合わせを安全に管理できます。
一方でenvは環境変数を調整して外部のツールやデータベースと連携する場合に便利です。実務では、サーバー上で動かすアプリの設定を環境変数で分離するケースが多く、Dockerやクラウド環境での設定と組み合わせるときに活躍します。
重要なポイントは「venvはPythonの依存関係を、envは実行時の設定値を隔離する」という基本方針を崩さないことです。 誤解のある落とし穴として、venvを作ってもOSのライブラリやデータベースそのものは隔離されず、あくまで Pythonの世界だけが分離される点を理解しておく必要があります。環境変数の扱い方が複雑になると、開発マシンと本番環境での挙動差が生まれやすくなるため、設定ファイルと同様に documented な手順を書くことが大切です。
実務のコツとしては、プロジェクトごとにリポジトリ内に README やスクリプトを用意し、venv作成と活性化のコマンドを共通化すること、また .gitignore に venv ディレクトリを入れて、依存関係を requirements.txt に固定する習慣をつけることです。テスト環境やデモ環境にも同様のルールを適用すれば、連携時の混乱を防げます。
友達と話していると、venvってただの技術用語以上のものに見えてきます。私は初めてvenvを使ったとき、まるで同じPCの中に小さな研究室を作るみたいだと感じました。プロジェクトAには requests の新しいバージョン、プロジェクトBには古い依存を使う必要があって、どちらも同じグローバル環境では干渉します。venvを作り activate すると、そのプロジェクト用のPythonとライブラリだけを取り出して別の空間に置くことができるのです。最初はコマンドの順番やパスが分からず戸惑うこともありますが、慣れてくると「このプロジェクトにはこの箱」を用意しておくのが自然になります。要するにvenvはPython開発のための“独立した小さな部屋”を作る道具であり、OSの設定とは別に、依存関係の安定を保つための現代的な常識と言えるでしょう。





















