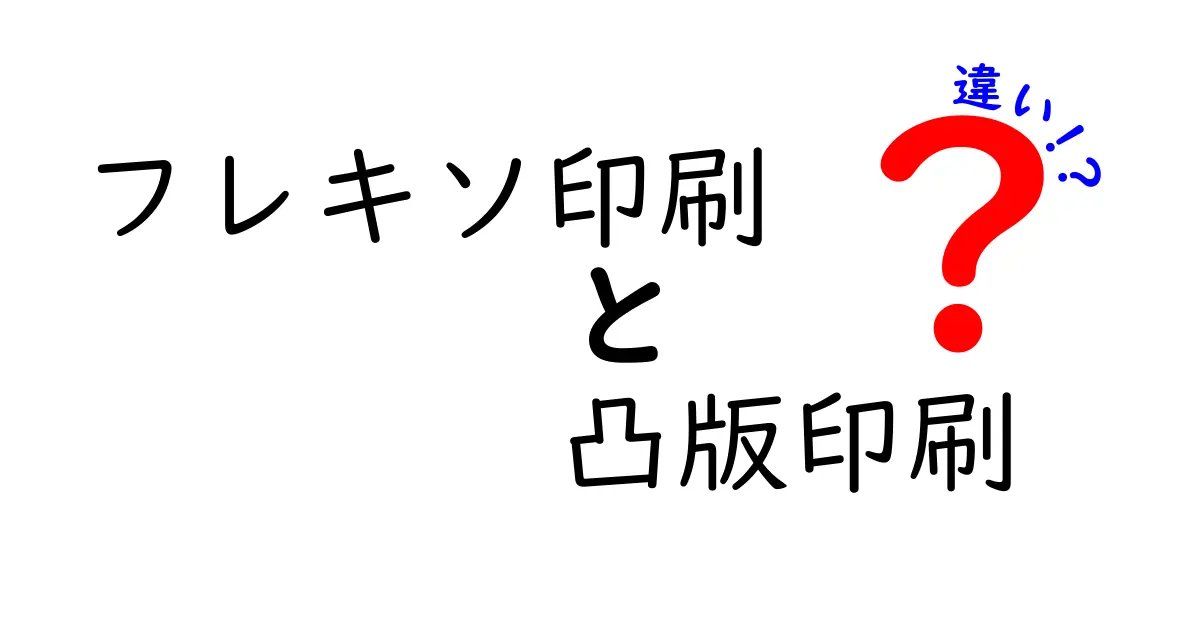

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:フレキソ印刷と凸版印刷の違いをつかむ
印刷の世界にはいくつもの方法がありますが、フレキソ印刷と凸版印刷は特に身近で、日常の包装や紙もののデザインに直結しています。フレキソ印刷は柔らかいゴム版を使い、版の凸部にインクを乗せて紙に転写します。凸版印刷は硬い版を使い、紙に直接「浮き出た形」を押し付けるイメージです。これらの違いを知ると、なぜ同じ「印刷」なのに表現やコストが違うのかが理解できます。
普段の買い物のパッケージを観察して、印刷の境界線を思い浮かべると、学びが深まります。
この解説では、まず仕組みをざっくりと押さえ、次に用途と向き不向きを見ていきます。学校の教材や身の回りのパッケージで見る印刷は、どちらの技術が使われているかを観察するとよいです。結論としては、フレキソ印刷は大量生産と包装向け、凸版印刷は高級感と細部の表現に向く点が大枠です。ただし「全てこれ一択」ではなく、デザインとコストのバランスで選ぶのが現場の鉄則です。
フレキソ印刷の仕組みと特徴
フレキソ印刷は、柔らかいゴム版・樹脂版を使い、版の凸部にインクをのせて紙へ転写します。版はローラーのように回転することが多く、包装材やラベル、袋物などの広い面にもきれいに印刷できます。インクのタイプとして水性・溶剤性・UV硬化などがあり、環境への配慮が進む現代では水性インキの採用が増えています。
特徴としては、曲面や凹凸のある形状にも印刷しやすいことと、印刷スピードが速い点が挙げられます。ラベルやパッケージ印刷に強く、コスト面も総じて安定しています。ただし、細部の再現性や微細なラインは凸版ほど正確には出ない場合があるため、デザインの段階で解像度の許容範囲を決めておくと失敗が減ります。
さらに、フレキソは印刷速度が速いことが多く、ロットが大きくなるほど単価が下がる「大ロット向き」の特性があります。紙質の選択にも柔軟で、結合材の強いコーティング紙やコート紙など、様々な紙に対応できます。製品の耐久性や表面の質感を検討する際には、インキの乾燥方式(乾燥温度・UVなど)も重要です。
総じて、柔軟性とスピード、コストのバランスが魅力であり、現代のパッケージ産業を支える大黒柱と言えるでしょう。
凸版印刷の仕組みと特徴
凸版印刷は、硬い版の凸部にインクを乗せ、紙へ押し付ける方法です。版は金属や硬質樹脂で作られ、文字や絵柄が盛り上がっています。印刷時には、紙と版が強く接触するため、深い版押しと独特の立体感(エンボスに近い質感)を生み出します。これにより、活字のようなシャープなラインや濃淡の再現が得意になります。これらは、印刷の質感を左右する大事な性質です。
一方で、版の作成には専門的な技術と時間が必要で、初期コストが高くなることがあります。少量のときは割高になる場合が多いため、用途を選ぶ印刷方法と言えるでしょう。
凸版印刷は、紙の手触りや厚み、表面のテクスチャを活かした高級感のある印刷に適しています。名刺や招待状、アート作品の印刷などで使われることが多く、紙の風合いを活かしたデザインが映えます。インクの密着力を高めるため、版の微調整やインクの粘度管理が重要です。最終的な仕上がりは、紙の選定と表現技法の組み合わせしだいで大きく変わります。
実務での使い分けと表の比較
日常の製品設計では、どの印刷方法を選ぶべきか迷うことが多いです。以下の表は、フレキソ印刷と凸版印刷の主な違いをまとめたものです。選択の際のポイントを整理しておくと、企画段階での意思決定が速くなります。
上の表を見れば一目で違いがわかります。現場では、企画の目的に合わせて使い分けるのが基本です。例えば、同じ包装でも大量に印刷するならフレキソ、紙の手触りと高級感を重視する場合は凸版を選ぶのがよいでしょう。
また、最近は両方の技術を組み合わせたハイブリッド印刷も増え、表現の幅が広がっています。デザインと材料の選択肢が増えるほど、消費者に伝わる印象も変わります。
友だちと印刷所の見学をしていたときのこと。職人さんが「フレキソ印刷は曲面にも強いんだ」と教えてくれた。ゴム版が紙の上を転がるように触れて、ラベルの角まできれいに色が乗るのを見て、僕は思った。凹凸感のある凸版に比べて、フレキソは速さと柔軟性が魅力。だが細部の再現には向かない場面もある。だからデザイナーは、紙の性質・仕上がりの風合い・コストを総合して選ぶのだと知った。
前の記事: « ダイヤルとプッシュの違いを徹底解説|使い分けのコツと身近な例





















