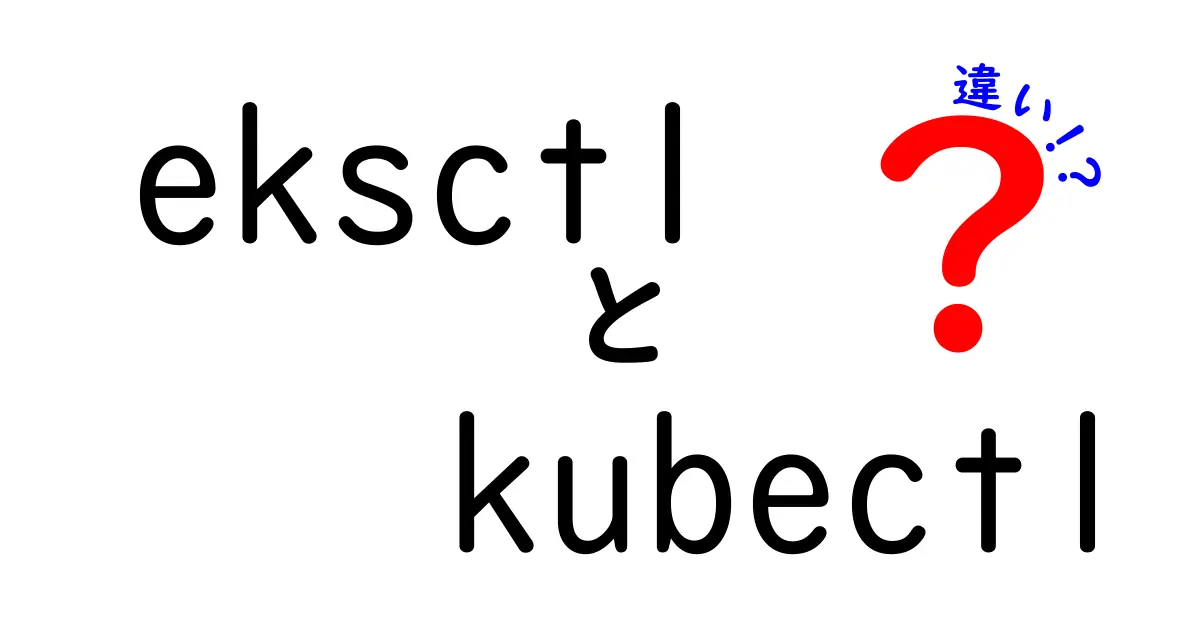

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
eksctlとkubectlの違いを徹底解説
ここでは eksctl と kubectl の違いを、初心者にも分かりやすい言葉で丁寧に解説します。Kubernetes を使い始めるときには、この2つのツールがそれぞれ別の役割を持っていることを理解することが第一歩です。
まずは全体像をつかみましょう。
この2つは同じ世界を扱っていますが、できることや使い方が違います。
本記事ではそれぞれの基本、実務での使い分け、そして具体的な違いを、事例を交えて紹介します。
最初におさえるべきポイントは、eksctlがクラスタの“土台”を作る道具、kubectlがクラスタ内部の“操作盤”になるという役割分担です。これを理解すると、最初の学習の順序が決まり、どの段階で何をすべきかが見えやすくなります。さらに現場では、この2つを組み合わせて使うのが普通で、ステップごとに役割を分けて作業を進めるとミスを減らせます。
本記事の後半では具体例と短い手順、そして比較のポイントを整理します。特に、クラスタ新規作成のときにeksctlを使うべき理由、リソースのデプロイや監視をkubectlで行う理由を、誰でも想像できる場面で説明します。最後には、覚えておくべき最も重要なキーポイントを短くまとめています。
eksctlの特徴と主な用途
eksctlは AWS の EKS クラスターを作成して管理するための専用 CLI です。クラスタの作成、ノードグループの追加、バージョンの更新、設定の適用といった“クラスタ自体の構築と運用の土台作り”を簡素なコマンドで実現します。
実務では、初期構成を手早く再現したい場面が多く、YAML ファイルを使って宣言的に定義する方法が重宝されます。
この機能の背後には、AWS アカウントと EKS のリソースを適切に紐づけ、セキュリティ設定を自動で適用する仕組みがあります。
eksctlのもう一つの強みは、スクリプト化と再現性です。
開発チームは同じコマンドのセットを使い続けられるため、環境間の差を小さく保てます。
ただし、eksctl単体ではクラスタ内部のリソースの細かな挙動を直接操作することはできません。つまり、クラスタの外部側の設定をまとめる役割に特化している点を覚えておくと良いです。
学習の初期段階では、eksctlを使ってクラスタを作ってから、kubectlで内部リソースを触るという基本の流れを身につけるのが自然です。
実務の例としては、VPC設定、ノードの種類選択、IAM ロール付与、クラスタバージョンの一括更新などを eksctl で行い、更新後の安定性を確認するのが一般的です。さらに、エラーハンドリングやロールバックの戦略を前もって決めておくと、運用がスムーズになります。
kubectlの特徴と主な用途
kubectlは Kubernetes のリソースを作成・表示・変更・削除するための標準的な CLI です。Pods や Deployments、Services、ConfigMaps などの Kubernetes オブジェクトを日常的に操作する役割を持ちます。
kubectl は「現在のクラスタ内の状態を操作する」道具であり、クラスタを構築する機能は持っていません。
そのため、実際の開発では、eksctl でクラスタを作り、そのクラスタの中で kubectl を使ってアプリのデプロイや設定変更を行います。
kubectl の強みは、クラスタ内のリソースとその状態を細かくコントロールできる点です。
リソースのスケールアウト、ロールアウトの進行状況の監視、イベントの確認、設定の適用など、運用の核となる操作を行います。
また、リソースの定義ファイルを用意して適用する「宣言型の運用」を実現するにも kubectl は必須のツールです。
つまり、「クラスタ内部の作業を日常的に回す道具」という理解がぴったりです。
kubectl の実務的な活用例としては、アプリのデプロイ、コンテナのスケーリング、ローリングアップデートの監視、ログの取得、イベントの追跡、設定ファイルの適用などがあります。これらの操作は頻度が高く、kubectl による正確さと迅速さが運用の安定性を大きく左右します。
kubectl はまた、宣言的な運用を実現する中心的なツールとしての地位を確立しており、DevOps や継続的デリバリーの現場で欠かせません。
現場での使い分けと具体例
実務では eksctl と kubectl を同時に使う場面が多く、役割を分けて使えば混乱を避けられます。
例として、まず新しい EKS クラスターを作るときには eksctl で「土台」を整えます。
ノードの追加やバージョンアップ、ネットワーク構成などは eksctl の方が効率的です。
その後、クラスタが動き始めたら kubectl にバトンタッチして、アプリのデプロイや設定変更、監視設定、リソースのスケーリングなどを行います。
もし誤ってリソースの定義を変更してしまっても、kubectl での確認作業と適用の操作で元に戻すことができます。
この組み合わせこそが実務の王道であり、学習段階の人にも、現場の人にも、理解を深めやすい方法です。
具体的には、最初に eksctl でクラスタを作成し、その後 kubectl で Deployment や Service をデプロイします。リソースのステータスを監視する際には kubectl の logs や describe コマンドを使って原因を特定します。スケーリングやロールアウトの管理、証明書の更新などの運用は、kubectl を中心に進めつつ、必要に応じて eksctl で設定を整えると効率的です。現場のチームはこの流れを覚えることで、トラブル時の対応速度を大幅に上げることができます。
まとめと使い分けのコツ
ここまでの内容を要約すると、eksctl はクラスタの構築と運用の土台づくりを担当し、kubectl はクラスタ内のリソース操作と日常的な運用を担当することが基本的な役割分担です。
それぞれの用途を分けて覚えると、学習の順番も自然で、実務でも混乱を減らせます。
使い分けのコツとしては、クラスタの新規作成時にはまず eksctl、日常のリソース操作やトラブル対応には kubectl を使い分けることです。
さらに、同じ結果を再現できるようにスクリプト化を心がけ、YAML ファイルを中心に環境を管理する習慣を持つと良いでしょう。
最後に重要なのは、2つのツールを別個の「役割」として認識し、互いを補完しながら使いこなすことです。これが Kubernetes 運用を安定させ、学習を進める最短ルートです。
- 主な役割 eksctl はクラスタの作成と管理の土台作り、kubectl はクラスタ内リソースの操作と日常的な運用
- 対象作業 eksctl はクラスタ構成の定義・ノード追加・設定適用、kubectl はリソースの作成・変更・監視に使用
- 操作対象 eksctl は EKS クラスター自体、kubectl は Kubernetes のリソース
- 難易度感 eksctl は初期設定・設計寄り、kubectl は日常操作・運用寄り
- 使い分けの要点 クラスタの土台を作る時は eksctl、リソースの操作は kubectl
友だちと話していたとき kubectl と eksctl の違いの話題になって、 kubectl は手元の Kubernetes リソースを操作する道具、 eksctl は AWS の EKS クラスターを作ったり設定したりする道具だと整理しました。 kubectl が日常の操作命令を受け取る司令塔なら eksctl は初期構築や大規模運用の土台を整える設計者のような役割。実際の作業は併用する場面が多く、それぞれの役割を理解して使い分けることが成功の秘訣だね。





















