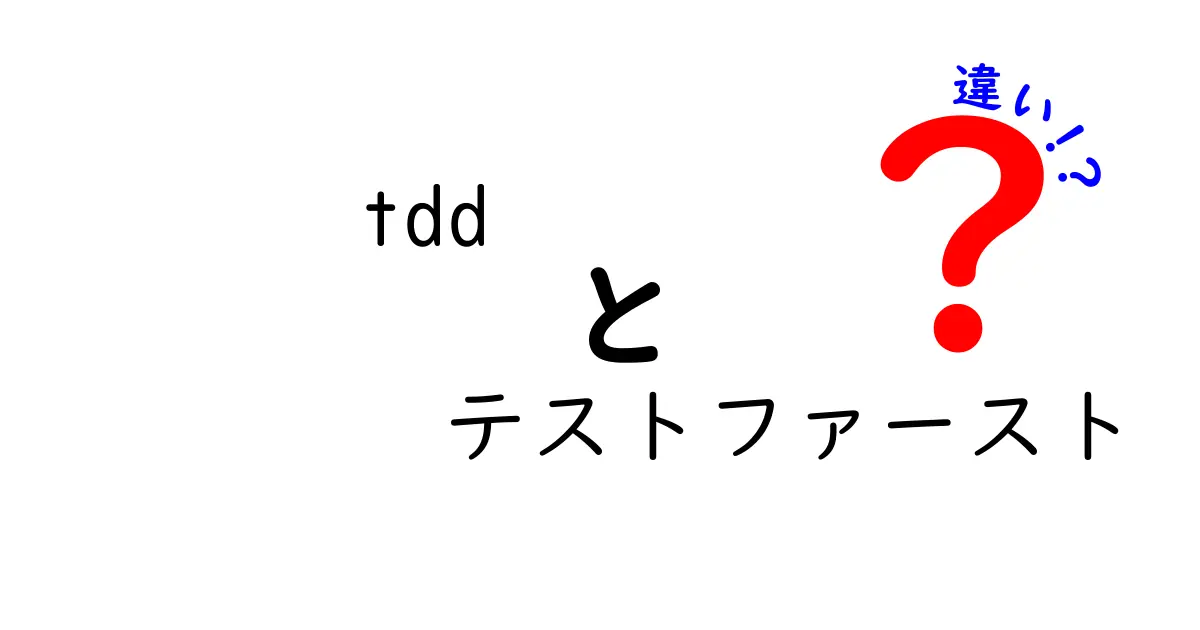

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:TDDとテストファーストの違いを知ると仕事が楽になる理由が見えてくる。ここでは用語の基礎と全体像を、初心者にも伝わる丁寧な言い回しで解説します。ソフトウェア開発において「テストを書く順番」と「テストを軸に設計を進める考え方」は似て非なるものです。これを正しく理解することで、機能の信頼性を高め、バグを早く見つけ、変更に強いコードベースを作るための第一歩を踏み出せます。実務の現場で混乱を招く表現の違いにも触れ、どの場面でTDDを選択すべきかの判断材料を整理します。テストファーストとTDDの関係性を、イメージ図と小さな例を交えながら、難しく感じさせない語り口で説明します。
ここからは、TDDとテストファーストの「違い」が現場でどう現れるのかを、具体的な場面を想定して説明します。まずTDDの本質は「まずテストを考え、それを元に実装を進める」という思考にあります。これにより、何を作るべきかが明確になり、後で仕様が変わっても対応しやすい設計になることが多いです。対してテストファーストは、実装前にテストの順序を決め、その順序に従って少しずつコードを追加していく実践のパターンを指すことが多く、思想全体を含むわけではない場合もあります。
この違いを理解する最大のメリットは、変更に強いコードベースを作るための道筋を自分で作れる点です。もちろん現場ではTDDだけを走り続けるケースもあれば、短期のタスクでテストファーストを採用する場合もあります。いずれにしても、テストを先に書くという「癖」が身につくと、要件が曖昧な時点での対策が早く取れるようになります。
ここからは実務での使い分けを、次の表と例を通して具体的に見ていきます。
この表を見れば、TDDは設計思想を含む広い枠組みで、テストファーストはその中の実践的な要素の一つと見ると理解しやすくなります。実務での適用はプロジェクトの性質や納期、チームの経験値によって変わるため、最初は小さな成功体験から始めるのがコツです。
いずれにしても、テストを書いてからコードを書く習慣は、ソフトウェアが壊れにくく、変更の影響範囲を把握しやすくする最短ルートの一つです。
友達と放課後に雑談していたとき、テストファーストの話題になって、私は最初それを『最初にテストを描く練習』くらいにしか思ってなかった。でも深掘りすると、それが単なる手順以上の意味を持つことに気づく。テストを最初に書くと、何を作るべきか、誰が使うのか、どう使われるべきかがはっきり見えてくる。さらに、テストが失敗する理由を早期に見つけられるので、後からの修正が楽になる。実際のコードでは、 UIの振る舞いを決めるテストを先に作ることで、UIとバックエンドの結合点を慎重に設計できる。だから私は、テストファーストを“設計の友人”と呼ぶことにしている。





















