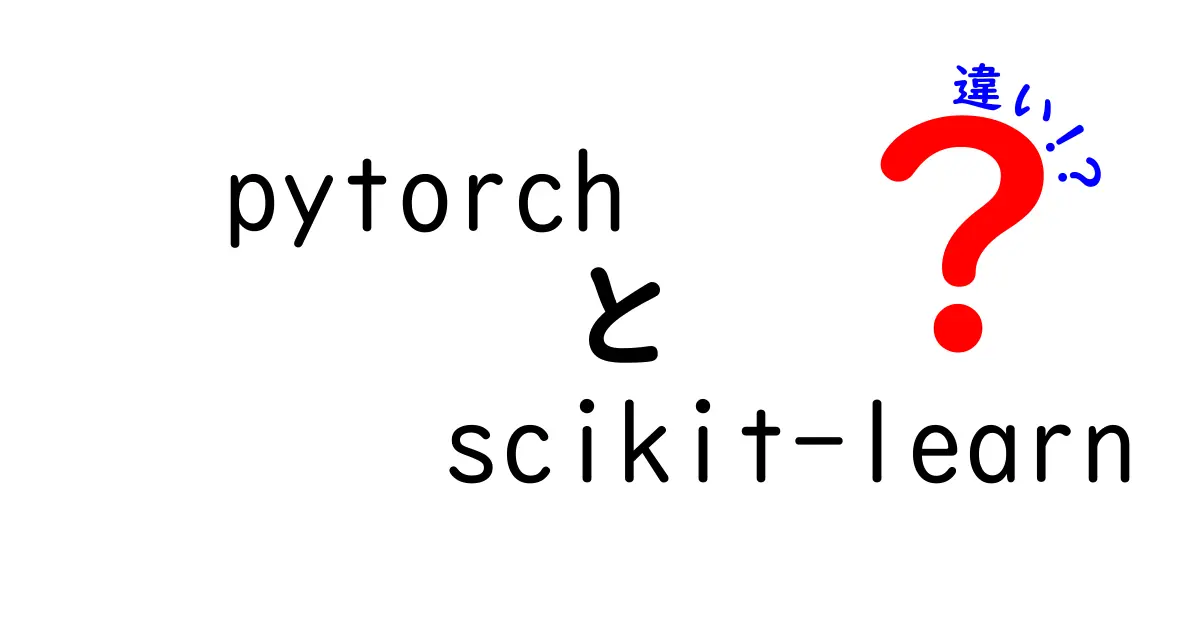

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
pytorchとscikit-learnの違いを徹底解説!初心者でも分かる使い分けと選び方
目的が違うことを最初に押さえよう
機械学習を学ぶとき、まず大事なのは目的と道具の違いを正しく知ることです。PyTorchは深層学習、つまりニューラルネットワークを作るための強力なツールです。動的計算グラフといわれる仕組みを使って、コードを書きながらモデルの挙動を直感的に確認できます。
一方、scikit-learnは伝統的な機械学習アルゴリズムをまとめたライブラリで、回帰・分類・クラスタリング・前処理などが揃っています。特徴量の前処理、モデルの選択・比較、クロスバリデーションといった作業が、初心者にも分かりやすく整理されています。
この二つは同じ“機械学習ツール”ですが、得意分野が異なるので、使い分けが大切です。初心者は最初はscikit-learnから学び始め、徐々にニューラルネットに踏み込むときにPyTorchの力を借りるのがよい流れです。
使い分けのコツと学習の流れ
現場での使い分けのコツは、データと目的を最初に見極めることです。小さなデータセットや伝統的なアルゴリズムを試すなら scikit-learn が便利です。学習の流れは、データの分割(train/test)、前処理、モデルの選択、学習、評価、改善の順です。
反対に、データ量が多く、画像・音声・テキストのような複雑なデータを扱い、最終的に精度の高いモデルを作る場合は PyTorch の活躍の場になります。
PyTorch は GPUの活用や動的計算グラフで、柔軟にモデルを組み立てられます。これらを踏まえ、最初は scikit-learn で基本を固め、次に PyTorch で深層学習の領域へ段階的に挑戦しましょう。
放課後の雑談で出た PyTorch の話題。僕は深層学習の世界に入りたい友だちに、PyTorch は動的計算グラフで開発が楽になると伝えました。彼は最初に scikit-learn の良さを思い出し、データの前処理や伝統的なアルゴリズムの理解を優先していたことを話してくれました。結局、道具は使い方次第だね、と二人で笑いました。





















