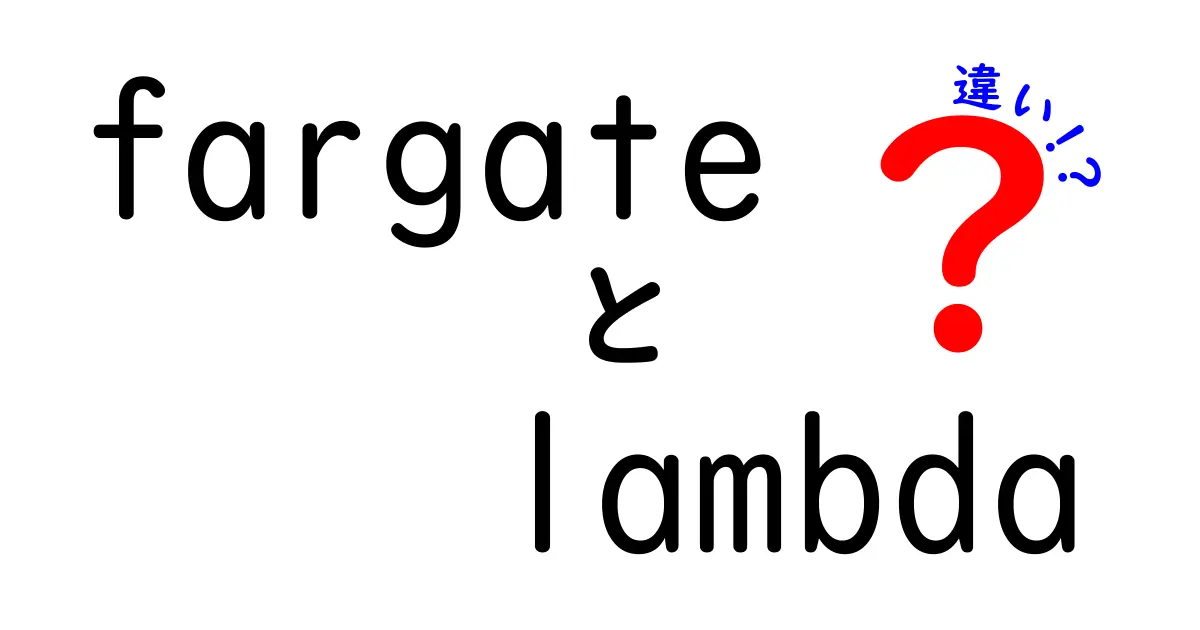

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:Fargateと Lambdaの基本的な違いを一言で理解する
この項目では、Fargateと Lambdaの違いを初心者にも分かる言葉で整理します。Fargateはコンテナを動かす仕組みの一つで、ECSまたはEKSと連携して、アプリを構成するパーツを「コンテナ」として実行します。ユーザーはDockerイメージを用意して、タスク定義・サービス設定を行い、クラスタ内のリソースを動的に割り当てます。対して Lambdaはイベント駆動のサーバーレス機能で、コードを関数としてアップロードすると、APIゲートウェイ・ストレージイベント・メッセージキューなどのイベントに応じて自動的に実行されます。Fargateは「起動してから動かす」という長めの実行時間を前提とし、Lambdaは「イベントが来たら実行する」という短時間・高頻度の実行を前提とします。これらの違いはコストの見積もり、運用の負荷、開発の設計方針に大きく影響します。
この先を読めば、あなたのアプリがどちらの選択肢で最適化されるか、"寄せるべき"方向性が見えてくるはずです。
ポイントは3つです。1) 起動時間の違い、2) コストの課金モデル、3) 運用の手間とスケーリングの仕組みです。
技術的な違いを分解して比較
このセクションでは、技術的な違いを要素別に分解して比較します。まずアーキテクチャの違い。Fargateはコンテナ実行基盤、Lambdaは関数実行基盤で、それぞれの設計思想が異なります。起動時間の特性、スケーリングの粒度、状態管理の方針、イベントソースとの結びつき、セキュリティと権限管理、監視・デバッグの観点など、比較軸を整理すると理解が深まります。FargateはDockerイメージの更新を素早く反映でき、長時間のタスクにも適しています。一方 Lambdaはイベントごとにインスタンスを自動起動・停止し、短時間の処理を大量に回すのに向いています。加えてコストモデルの差は大きく、Lambdaは実行時間とリクエスト数に課金され、Fargateは実行時間と割り当てたCPU/メモリに課金される点が特徴です。
この違いを理解することで、要件に応じた最適な設計が見えてきます。
実際の運用での使い分け例
実務の現場では、システム全体の性質を見て使い分けることが多いです。例えば高速な応答が求められるAPIや、頻繁に発生するイベント処理にはLambdaを選ぶとコストと運用の負荷を抑えやすいです。逆に、動画のエンコード、機械学習の推論パイプライン、長時間走るバックグラウンド処理などはFargateの方が適しています。もちろん両方を組み合わせるハイブリッド戦略も現実的です。ただし注意点として、Lambdaの寒いスタート問題や、Fargateのリソース過剰割り当てによるコスト増、デバッグの難易度差などを見落とさないことが重要です。
設計初期には、要件を「イベント駆動型か」「継続的な処理か」で分解して、データの流れとボトルネックを描くと良いでしょう。ブレない基準を作ることで、変更にも強いアーキテクチャになります。
結論と要点
結論として、Fargateと Lambdaは「使いどころが異なるツール」です。同じアプリでも構成要素によって適切な選択肢が変わることを理解することが大切です。新しい機能を追加する際には、イベント駆動の処理はLambda、長時間・状態を伴う処理はFargateという軸で分けるのが有効です。最終的な決定には、予算、運用チームのスキルセット、監視・セキュリティ要件、スケールの期待値などを総合的に考える必要があります。
この記事の要点を簡単に振り返れば、起動時間・課金モデル・運用負荷の三つの観点を押さえ、要件に最も適したサービスを選ぶことが最も効率的なアーキテクチャ設計につながります。ここまでの理解が深まれば、次の一歩として実際のリソース選定表や試作を行う準備が整います。
ねえ、起動時間の話、ちょっと雑談しよう。Fargateはコンテナを常に“起動済み”の状態で動かせることが多いから、急に来る処理にも強いんだけど、その分待機コストが生まれやすい。一方 Lambdaはイベントが来るたびに起動して実行して終わるスタイルだから、待機コストがかからない。ただし寒いスタートの影響で最初の数百ミリ秒が遅く感じることもある。だから、イベントの性質をみて、"すぐに終わる処理"はLambdaへ、処理時間が長く安定したリソースが必要な場合はFargateへ、という割振りを考えると良いんだ。





















