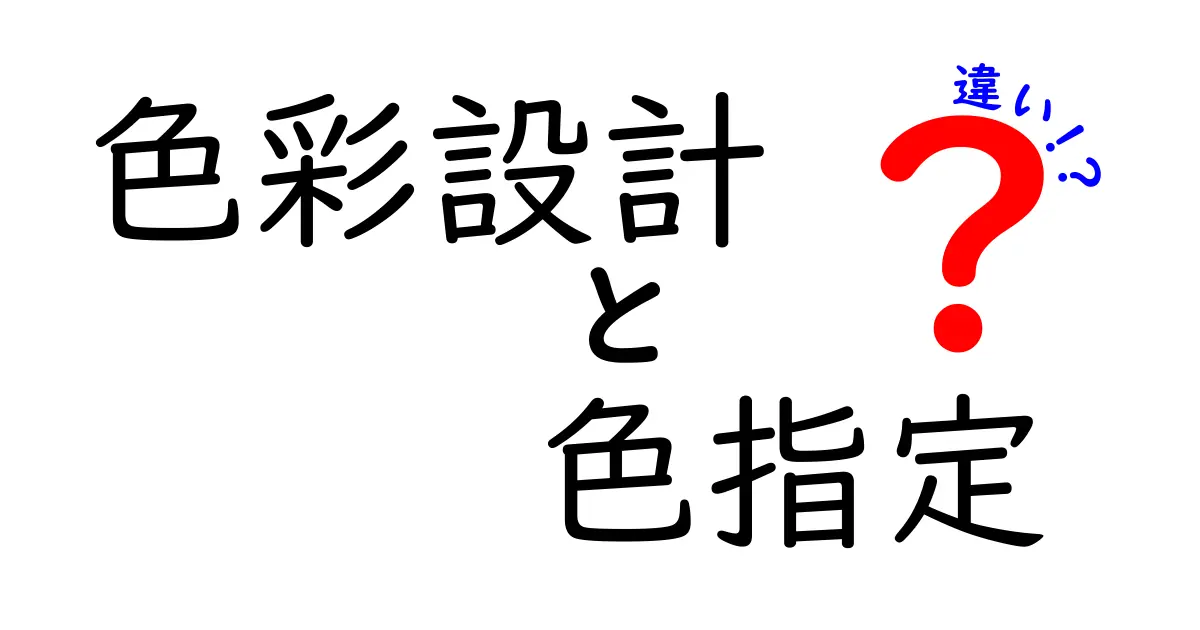

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
色彩設計と色指定の基本的な違いを知ろう
みなさんは「色彩設計」と「色指定」という言葉を聞いたことがありますか?どちらも色に関わる言葉ですが、実は意味や使い方が全く違います。
色彩設計は、全体的にどんな色を使うか、どう組み合わせるかを考えることです。たとえば、建物の内装や商品のパッケージ、ウェブサイトのデザインなどで、色の調和や印象を決める作業を指します。
一方で色指定は、決まった色を正確に伝えるための方法です。例えば、印刷物を作るときに「この色をこの色番号で使ってください」という具体的な指示を出すことです。
このように、色彩設計は「全体の色の計画」、色指定は「具体的な色の指示」と覚えておくとわかりやすいです。
色彩設計の役割と重要性
色彩設計は、見た人にどんな印象を与えたいかを考えながら色の組み合わせを決める仕事です。
例えば、飲料のパッケージを考えるときには、その飲み物が持つイメージやターゲットとなるお客さんの好みを考慮して色を選びます。
青色は冷たさや爽やかさを感じさせるため、スポーツドリンクのパッケージに使われることが多いですし、赤色はエネルギーや情熱のイメージがあるので、元気を出させたい商品に選ばれます。
つまり、色彩設計とは単に色を選ぶだけでなく、色を通して伝えたいメッセージや感情を形にする作業なのです。
また、色の組み合わせやバランスを考えることで、見た目が美しく、使いやすいデザインに仕上げることができます。これにより、商品の魅力が高まったり、ブランドのイメージアップにつながったりするのです。
色指定の具体的な方法と注意点
色指定は、色彩設計で決まった色を正確に再現するための指示をすることです。
色の世界にはさまざまな色の表現方法があり、代表的なものに「RGB」「CMYK」「Pantone(パントン)」などがあります。
例えば、印刷物ではCMYKというシアン・マゼンタ・イエロー・黒の4色を混ぜて色を作ります。一方、画面の色はRGBの赤・緑・青の光の組み合わせで作られます。
色指定をする際には、目的に合った色のコードや番号を使い、誰が見ても同じ色だとわかるように細かく決めます。
色指定があいまいだと、仕上がりの色がバラバラになってしまい、品質やイメージに悪影響を与えることがあるため注意が必要です。
色彩設計と色指定の違いをまとめた表
まとめ:色彩設計と色指定を理解するとデザインが楽しくなる!
「色彩設計」と「色指定」は、色に関わる大切な作業ですが、役割や目的は違います。
色彩設計は、全体の色の計画を立てて見た目や印象を考える仕事です。
色指定は、その計画で決めた色を正しく伝えるために具体的な数値や色番号を使って示します。
正しい色彩設計と色指定があって初めて、美しく魅力的な商品やデザインが完成するのです。
デザインや制作の仕事に関わる人は、ぜひこの違いを理解して活用してくださいね!
色指定は単に色番号を伝えるだけの作業に見えがちですが、実はすごく繊細な部分があります。例えば、同じ赤でも画面の色と印刷の色はまったく違いますし、光の具合や紙の質によっても見え方が変わります。だから、経験豊富なデザイナーや印刷会社のスタッフは「色校正(いろこうせい)」といって何度も色を確認しながら仕上げていくんですよ。こうした細かい調整が、最終的に美しい色を作る秘密なんですね!
次の記事: 色弱と色覚の違いとは?わかりやすく解説!見え方の秘密を知ろう »





















