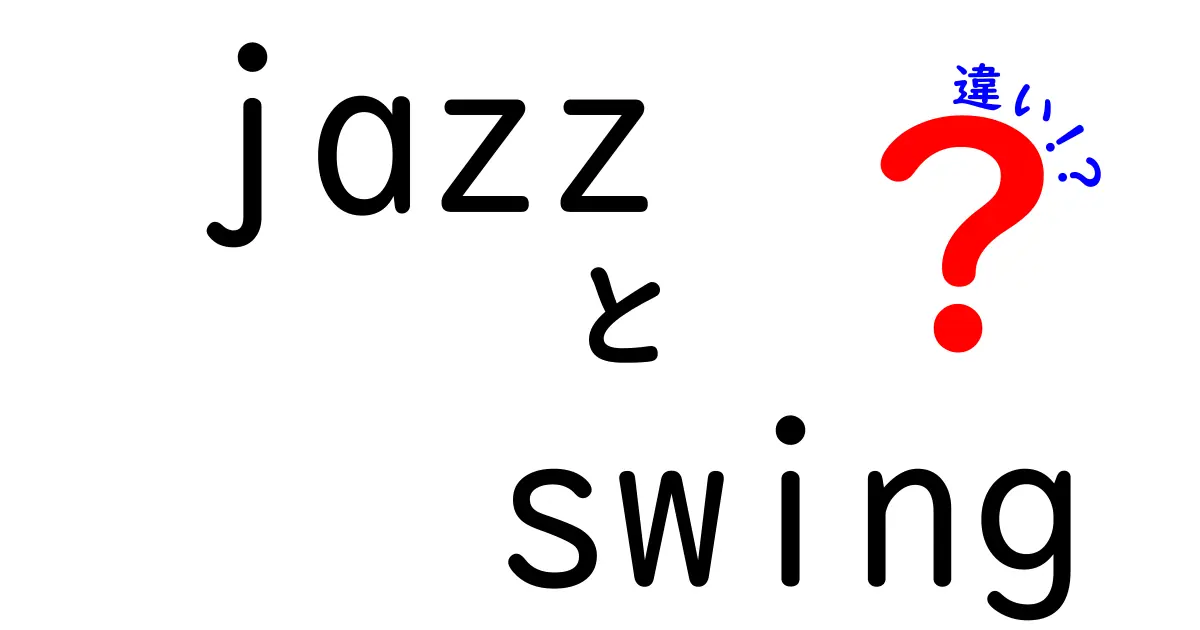

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
jazzとswingの違いを理解するための基本
jazzとswingは似ている言葉ですが、音楽の世界では役割が違います。ジャズは幅広い音楽の総称であり、さまざまなスタイルや時代ごとの変化を含みます。演奏者の創造性や即興性が強く、コード進行が複雑になることも多いです。一方、スウィングはそのジャズの演奏のなかで生まれる特定の「リズムの感じ方」や「音楽の雰囲気」のことを指すことが多いです。スウィングの要素を持つ演奏は、体が自然と揺れるような歩くようなリズム感を生み出します。ここでは初心者にも分かるように、リズム、和音、演奏の場面、聴き方のコツを順番に解説します。
まず大切なのは、ジャズが広い枠組みだと認識することです。ジャズの中にはソロの即興や複雑なコード進行を楽しむスタイル、ビッグバンドのアレンジ、ブルースの影響を強く感じる演奏など、多様な表現があります。これに対してスウィングは、特定のリズムのフィールとダンスの場面で特に強く意識される要素です。つまり、ジャズは「何を演るか」の世界、スウィングは「どう聴く・どう感じるか」の世界と捉えると分かりやすくなります。
1. リズムの違いを聴くコツ
リズムの違いを聴き分ける第一のヒントは8分音符の感じ方とスウィングの長短感を意識することです。ジャズの演奏では8分音符が均等に並んでいるように聴こえることが多いですが、スウィングになると同じ8分音符が2つを1拍に感じる長短のリズムに変わります。これを聴くには、最初は同じテンポで演奏される2つのリズムを聴き比べる練習が有効です。例えば、同じ楽曲のセクションを別のプレイヤーが演るとき、強拍の感じ方が変わるのを聴き分けましょう。
次に、ダンスのリズムと結びつけて想像すると理解が進みます。スウィングは歩くような「ドゥーン・ドゥーン」という跳ねるリズム感を生み出しやすいです。これを意識して聴くと、ソロのフレーズの中にも間や呼吸のような間合いが生まれてくるのが分かります。最後に、実際の聴取を行う際にはテンポを落として聴くことが有効です。ゆっくり聴くと、リズムの揺れやアクセントの置き方が見えやすくなり、スウィングとジャズの違いを自分の耳で確認しやすくなります。
2. 和音とアレンジの違いを感じる
リズムだけでなく、音の雰囲気も大きな違いのひとつです。ジャズは複雑なコード進行やフレーズの展開を楽しむスタイルが多く、セブンスコードやテンションノートが日常的に登場します。これにより楽曲全体の響きが豊かになり、演奏者は即興の場で新しいアイデアを形にすることが求められます。一方スウィングは、和音の使い方が比較的「安定寄り」で、8分音符のリズムと調和したダンス向けのアレンジが中心になることが多いです。つまりジャズが創造性と変化の追求を重視する一方で、スウィングは聴衆の体感と踊りやすさを重視する場面が多いのです。
3. 歴史的背景とダンスとの関係
ジャズの起源は20世紀初頭のニューオーリンズ付近にさかのぼります。黒人音楽の民謡やブルース、ラグタイムが混ざり合い、即興性と個性の表現が広まりました。スウィングは1930年代から40年代にかけてのジャズの拍子感を指すことが多く、ビッグバンドの大規模編成とともに大衆文化として急速に広がりました。ダンスホールでの演奏が盛んになり、ダンスと音楽が互いに影響を与え合う時代背景が生まれました。現在でもクラブやライブでスウィングの雰囲気を持つ曲が人気です。歴史を知ると、なぜこのリズムが多くの人に愛されるのか理解が深まります。
4. 聴く練習の実践と演奏例
実際に聴く練習としては、まず好みの曲を選んで聴き比べることから始めましょう。ジャズの名盤とスウィング寄りの演奏を並べて聴くと、リズムの感じ方やアレンジの差がくっきりと浮かびます。次に楽器ごとの音色にも注目します。ピアノのコードの動き、ギターの伴奏パターン、トランペットのソロの切り出し方など、各楽器がどう役割を果たしているかを理解すると、全体像がつかみやすくなります。実演動画を活用するのもおすすめです。動画ではミスなく演奏している部分だけでなく、練習中のミスや微妙なリズムの揺れも観察できます。ここで重要なのは「自分の耳で聴く力を育てる」ことです。
最後に、実際の場面での学びとして、学校の音楽室や地域の音楽イベントでジャズとスウィングを混ぜたセッションに触れる機会を作ってみてください。生の演奏は教科書にはない発見を与えてくれます。音楽を楽しみながら、耳を鍛え、体を動かすことで、違いを自然と理解できるようになります。
会話の雰囲気を大切にした小ネタです。リズム感という言葉を友達と話している場面を想像してみてください。リズム感は生まれつきの素質より、練習で育つ力です。私は高校の吹奏楽部で最初はリズムが取れず苦労しましたが、拍の切れ目を指揮者の足元と手の動きで追う練習を続けた結果、徐々に体が自然と揺れるようになりました。だからみんなも焦らず、耳を鍛える小さな習慣を積み重ねてください。例えば好きな曲の中から4小節だけ取り出し、拍の位置を数えながらマネして吹く練習をすると、リズム感の基盤がしっかり育ちます。





















