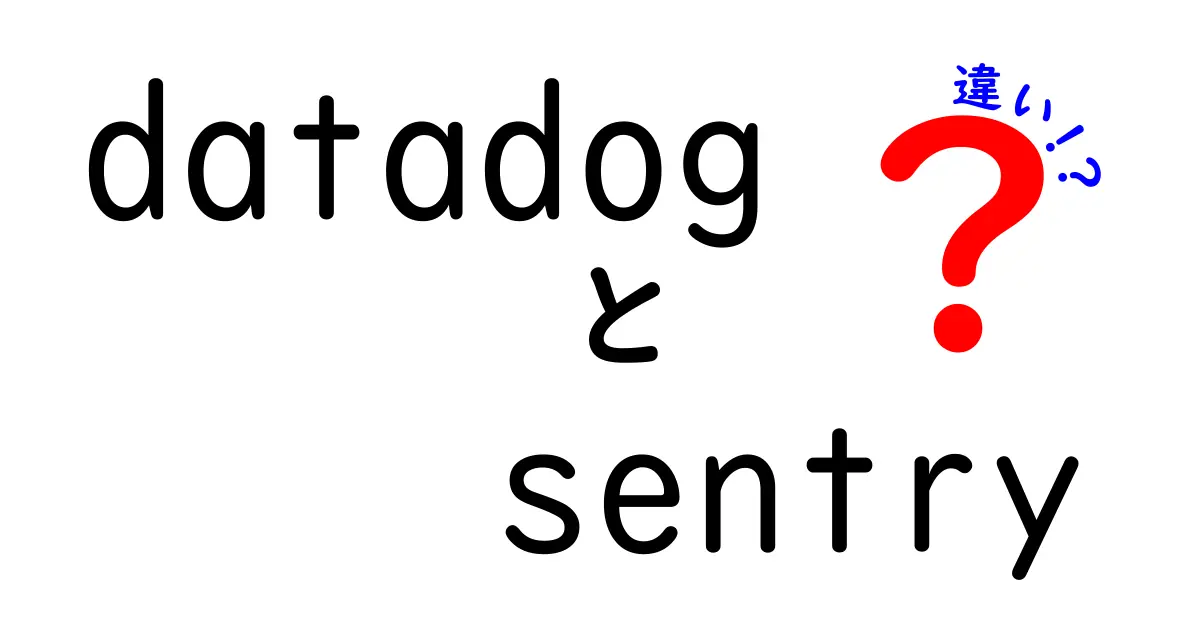

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
DatadogとSentryの違いを理解するための基礎知識
Datadogは総合的な監視ツールで、サーバー・ネットワーク・アプリ・クラウドの指標を一つの画面に集めます。CPU使用率やメモリ、ディスクI/O、アプリの遅延、ユーザー体験データなどをリアルタイムで表示します。これに対してSentryは主にアプリのエラーを追跡するためのツールです。コードで発生した例外、エラー頻度、影響範囲、再現性などを丁寧に記録・分析します。
この2つの違いは大きく分けて「対象範囲」「データの性質」「使い方の流れ」です。
Datadogは「インフラ+アプリ+クラウド環境の全体像」を見せるのに強く、Sentryは「エラーがいつ、どのように発生したのか」を詳しく知るのに強いです。
つまり、Datadogは「今の状態を把握する地図」、Sentryは「どこで問題が起きたのかを特定する地図」と言えるでしょう。
- 対象範囲: Datadogはサーバー・アプリ・ネットワーク・クラウド全体を横断して監視します。
- データの性質: メトリクス、ログ、トレースなどを横断して集め、時系列で表示します。
- 使い方の流れ: アラートの設定→原因探索→対策の繰り返しが基本です。
この違いを理解しておくと、何を監視したいのか、何を解決したいのかがはっきりします。次に「どう使い分けると効率的か」を具体的な場面で解説します。
DatadogとSentryの使い分けの実践ガイド
実務では、DatadogとSentryを「組み合わせて使う」ケースが多いです。以下のポイントを押さえると、現場での混乱を減らせます。
- 全体の状態を把握するためにDatadogのダッシュボードを用意する。CPUやメモリ、アプリのレイテンシ、ネットワークの遅延を一目で確認できるようにします。
- アプリのエラーや例外を見つけるためにSentryを使う。どのコード行でエラーが発生したのか、どのリリースで起きたのかを特定します。
- アラートの役割分担を決める。システム全体の健全性はDatadogでアラート、コードの問題はSentryで通知、という使い分けが分かりやすいです。
- デプロイの前後で連携する。新しいリリースを出す際にはSentryのリリース機能とDatadogのパラメータを紐づけて、問題が起きていないかを同時に監視します。
表で見ると分かりやすいので、以下の図を参考にしてください。
表は実務での選択肢を整理するのに役立ちます。
最後に、具体的な使い分けのケースをいくつか紹介します。
| 状況 | おすすめツール | 理由 |
|---|---|---|
| サーバーの状態とアプリのパフォーマンスを同時に知りたい | Datadog | 横断的な監視が得意だから |
| アプリのエラーを速く修正したい | Sentry | エラー箇所の特定と再現が楽 |
| デプロイ後の影響を追いたい | Datadog + Sentry | 両方を連携させて全体像と原因を同時に見える化 |
使い分けのコツは「見たいものを先に決める」ことです。監視自体を目的にするのではなく、実際に問題を見つけて解決するための手段として捉えましょう。
ある日の放課後、友だちとデータ監視の話をしていて、Datadogは全体像を把握する地図、Sentryはエラーを追跡する探偵のようだね、という話になりました。Sentryのエラーはコードのどの場所で発生したのか、どのリリースで影響を受けたのかを教えてくれて、開発者はその情報をもとに修正を行います。一方Datadogはサーバーの稼働状況、ログ、ネットワークも含めた「今の状態」を示す地図として役立ちます。現場ではこの二つを組み合わせて使うのが最も効率的です。私たちは今日、デバッグとパフォーマンス改善の両方を想定して、ツールの役割を分けて使う練習をしました。Datadogはダッシュボードの設計次第で監視の効率が大きく変わるので、どんな指標を並べるかを友だちと話し合う時間が楽しかったです。Sentryはエラーの原因追求に集中できるので、コードの品質向上にもつながります。結論として、ITの現場ではDatadogとSentryを「役割分担で使い分ける」ことが最も現実的な選択だと感じました。今後は、デプロイ後の挙動を両方でリンクさせる運用を試してみたいと思います。





















