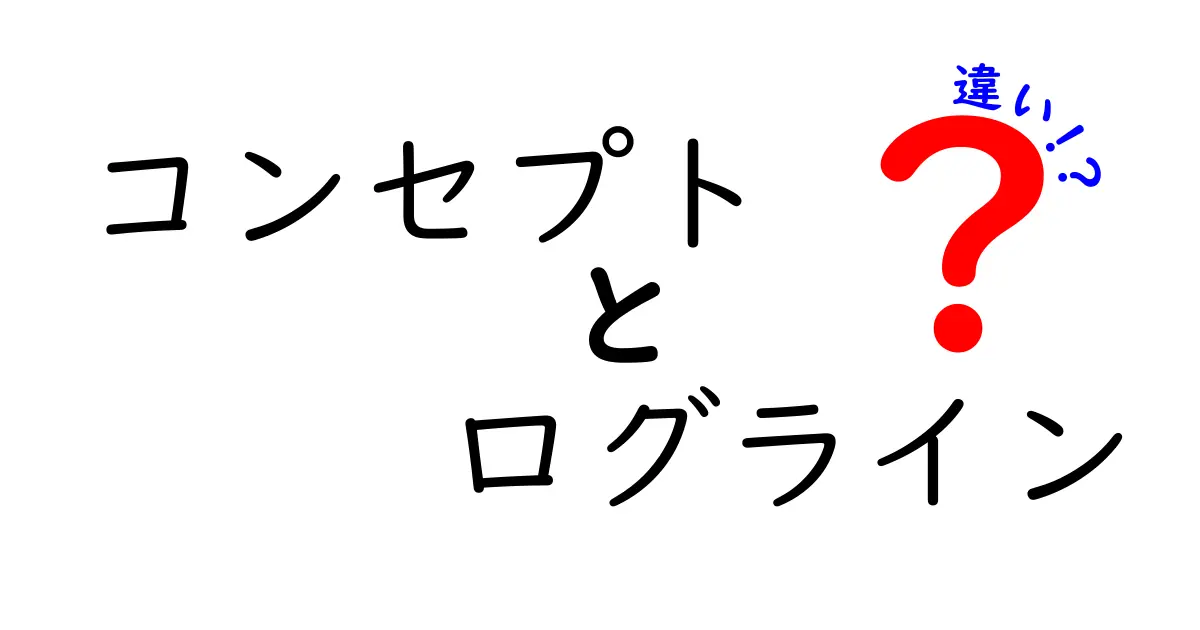

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
コンセプトとログラインの違いを理解するための徹底ガイド
この文章では「コンセプト」と「ログライン」という二つの言葉が、物語づくりの中でどのような役割を持つのかを、やさしい言葉で説明します。まずは「コンセプト」が何を指すのかを理解し、その後に「ログライン」がどういう機能を果たすのかを確認します。これらは別のもののようでありながら、互いに支え合う関係にあります。
心に留めておきたいのは、どちらも物語の核を扱う道具だという点です。たとえば学校の演劇部でも、まずは物語の大筋の「考え方」や「伝えたいテーマ」を決め、それを短く端的に伝える「一文」を作る練習をします。この取り組みは、作品の方向性を迷わず決める手助けになります。
次の文章では、珍しい言い回しは使わず、日常的な言葉で順を追って説明します。コンセプトは広い意味を持つ「大きな考え方」、ログラインはその大きな考え方を一文にぎゅっとまとめたもの、と覚えておくと混乱が減ります。
つまり、コンセプトは「何を伝えたいのか」という根っこの問いに近く、ログラインは「誰に伝えるのか」「何を魅力に感じてもらうのか」という観点を加えた短い説明になります。
この章のあと半ばには、実際の例を用いて違いを実感できるようにします。たとえば「世界を救う勇気ある少年の成長」というコンセプトがあれば、それを一言で表すログラインとして「世界を救うため、若き勇者が自分の弱さと向き合う物語」というような短い文に落とせます。こうすることで、物語づくりの出発点がはっきりと見えてくるのです。
以下の章では、もっと具体的な説明と実践のコツを紹介します。
コンセプトとは何か
ここでは「コンセプト」の基本をじっくり解説します。まず大切なのは「何を伝えたいのか」という質問に対する答えを、できるだけ簡潔かつ力強く作ることです。
概念の核を一語二語で表現できると、その後の企画書や企画段階での指針になります。たとえば「成長と友だちの絆を通じて、勇気とは自分の弱さを認めることだ」というテーマがあれば、これをそのまま説明するのではなく、周辺の要素(障害、仲間、成長のきっかけ)をどう並べるかを考えます。
なお、コンセプトは長く説明するよりも、複数のシーンにまたがる一貫したメッセージを作ることが重要です。
この節の実践ポイントは3つです。第一に大枠のテーマを決める。第二に登場人物と世界観を結ぶ軸を探す。第三に伝えたい感情の方向性を決める。これらを満たすと、企画書を読んだ人に「この作品は何を伝えたいのか」が明確に伝わります。具体例を挙げると「学校の部活動での挑戦を通じた成長」や「異なる文化を持つ仲間たちの協力」など、テーマと物語の土台が結びつく形になります。
実務ではこのコンセプトの作成が企画の第一歩です。チームで案を出すときも、まずこの核となる考え方を共有します。核が揺らぐと、以降のシーン設定やキャラクターの動機づけがブレてしまいます。したがって、全員が同じ色を見ているかを確認する作業が欠かせません。続く段落ではログラインの説明に移ります。
ログラインとは何か
ここでは「ログライン」の基本を詳しく説明します。ログラインは作品の核となる要素を、ひとつの短い文で伝える技術です。長い説明文の代わりに一文で「誰が」「何を」「なぜそれが重要なのか」を示します。
この一文があると、プロデューサーや編集者、読者にも作品の魅力がすぐ伝わります。ログラインの長さの目安はだいたい20語前後、日本語で言えば約20〜30文字程度を目安にします。
ポイントは具体性と魅力のバランスです。現実味を保ちながらも、読んだ人が続きを読みたくなるような要素を盛り込みます。
次に、コンセプトとログラインの関係を理解するための例を使います。先ほどの成長と絆のテーマを考えると、ログラインは「成長をめざす少年が、仲間の協力と自分の弱さを乗り越える」みたいな短い文になります。ここで重要なのはログラインが「起承転結の筋を一文で伝える」こと、そして「物語の最も強いドラマを一文で示す」ことです。
このように、ログラインは企画書の最初の扉として働き、読者にこの作品を見たいと思わせる力を持ちます。
さらに、ログラインを作る際のコツをいくつか紹介します。第一に登場人物の強い動機を含めること、第二に物語の「起点」と「対立」を一文の中で示すこと、第三に現実味のある具体性を入れることです。たとえば学園ものなら学校生活の場面、冒険ものなら未知の世界とリスク、など具体的要素を少しだけ盛り込むと伝わりやすくなります。
両者の違いと使い分け
ここではコンセプトとログラインの違いを整理し、実際の制作現場でどう使い分けるかを説明します。
まず基本の違いは「対象の広さ」と「目的」です。コンセプトは作品の方向性を決める広い視点で、ログラインは作品を伝えるための狭く具体的な一文です。
次に使い分けのコツですが、企画の初期段階ではコンセプトを磨くことに時間をかけ、次のステップとしてそれを短く魅力的なログラインへと落とし込む練習を繰り返します。
実務の場面では、企画書の最初の一文をログラインとして使い、プロジェクトの売りを端的に説明できるように準備します。
この二つを組み合わせると、企画の全体像が揺らぎにくくなります。まず大枠のテーマを決め、それを表現するログラインを作成します。次にそのログラインをベースに、作品の展開を想像していくと、物語の流れが自然に設計できます。最後に、チーム内でログラインを共有し、全員が同じ“引きつけるポイント”を意識できる状態を作り上げることが重要です。
この表を使えば、制作チームで意見がぶつかっても、どちらの要素を強化すべきかを判断しやすくなります。さらに、実際の現場ではこの二つを連携させることが大切です。まずコンセプトを土台に据え、それを短く魅力的なログラインへと落とし込む練習を繰り返すと、企画書の整合性が高まり、プレゼンがスムーズになります。最後に、読者が物語に共感できるよう、日常の身近な言葉で伝えることを心掛けてください。
ねえ、今日はコンセプトとログラインの違いについて雑談風に話してみるね。僕らのチームではまず“テーマは何か”を決めることから始める。たとえば『成長と友情』というコンセプトがあれば、それを一文に凝縮するのがログライン。で、ログラインは読み手が“続きが読みたい”と思う力を持つ必要がある。つまり、コンセプトは大きな地図のようなもの、ログラインはその地図を見せる一言の看板みたいな感じ。
次の記事: AVCとVP9の違いを徹底解説!動画圧縮の選択はどっちが正解? »





















