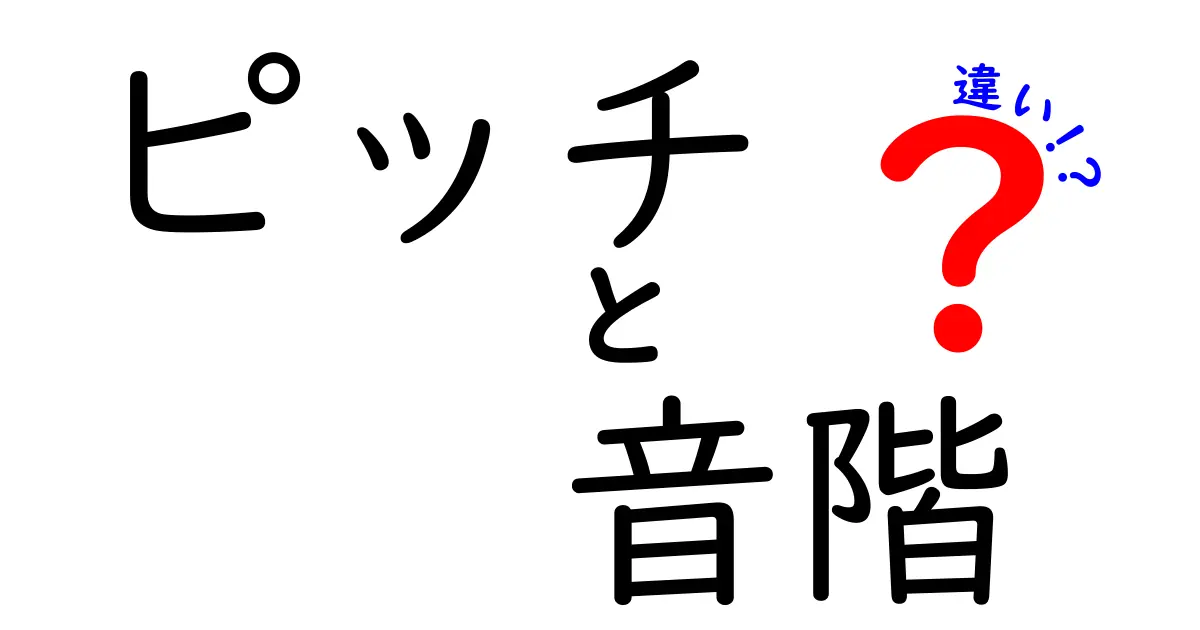

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ピッチと音階の基本をおさえる
ピッチとは音の高さそのものを指す言葉です。高い音は"高いピッチ"、低い音は"低いピッチ"と呼ばれます。理科的には音の波の周波数が関係します。音が高くなると周波数が大きく、低くなると周波数が小さくなる仕組みです。
この情報は耳で感じる情報なので、数字だけを覚えるのではなく“聞こえ方”としてとらえると理解が進みます。音階は音が並ぶ順番や規則を指します。例えば長調の音階は"ドレミファソラシ"のように、一定の規則に従って音を並べます。音階には長音階・短音階・和声的な並びなど、いろいろな種類があります。音階を知ると、曲がどうして“明るい感じ”や“しっとりした感じ”になるのかがわかりやすくなります。
では、ピッチと音階の違いは何なのでしょうか。端的に言えば、ピッチは音そのものの高さ、音階は音の並び方・規則の集合です。音楽を聴くとき、ピッチの高さを感じ取りつつ、どの音がどの順番で来ているのかを音階として認識することで、曲の作られた仕組みを掴むことができます。これを意識して聴く練習をすると、歌や楽器の演奏で「正しい高さ」を再現しやすくなります。
以下の表は、両者の特徴を簡単に整理したものです。用語 意味 日常的な例 ピッチ 音の高さそのものを指す情報。周波数で決まる。 家族の声が高くなるとピッチが上がる、楽器で同じ音を2つの鍵盤で鳴らすと音色は同じでもピッチは同じ高さになる 音階 音を並べる規則や順番のまとまり。曲の骨格になる。 Cメジャーの音階はC-D-E-F-G-A-B-Cの順に並ぶ、和音を作るときの基礎となる 絶対ピッチ vs 相対ピッチ 絶対ピッチは固定された高さ、相対ピッチは基準からの高さの差を測る考え方。 絶対ピッチの例はA=440Hzのような基準、相対ピッチは“ここから数えて何度上か”を言うときに使う
ピッチと音階の理解を深めるコツは、耳で聞く「高さ」と「並び方」を別々に意識することです。最初は難しく感じるかもしれませんが、歌や楽器の練習を通じて、自然と区別できるようになります。例えば、メジャー音階とマイナー音階を聴き比べたり、同じ音を異なる音階で歌ってみたりすると、違いが頭の中ではっきり分かるようになります。
この理解は、作曲・編曲・演奏の現場でも非常に役立ちます。別の楽器で同じ音を鳴らすとき、ピッチの高さが揃わないと音はぼやけてしまいますが、音階の規則を知っていれば正しい位置に音を置くことができます。
ピッチと音階の違いを整理する練習
まずは身近な音源で聴き比べをするのがおすすめです。
1) ピアノやギターで同じ音を鳴らして、音の高さを比べます。
2) その音を中心に、上昇・下降する音階を弾いてみて、何度上がって何度下がるのかを数えます。
3) 唱歌やボーカル練習では、歌唱中の「高さの変化」と「音階の進行」を別々に感じる訓練をします。
これらの練習を繰り返すことで、音楽を聴くときの“芯”がしっかりしてきます。
日常の中で音楽を聴くときも、ピッチの高さと音階の並びを同時に意識するだけで、曲の意味や感情の変化をつかみやすくなります。
この章の要点をもう一度まとめます。
ピッチは音の高さそのもの、音階は音の並び方の規則、そして両者は別の情報を表すということです。音楽を深く理解するには、この2つの違いを頭の中で区別しておくと、演奏や聴覚トレーニングがとても楽になります。
今後の練習でこの理解を活かせるよう、日々の聴取と実践を重ねていきましょう。
追加ポイントとして、絶対ピッチを持つ人と相対ピッチを鍛える人の違いにも触れておくと理解が深まります。絶対ピッチを持つ人は、基準となる高さを常に聴き分ける能力があります。一方、相対ピッチを鍛える人は、基準音から他の音への移動距離を感じる力を強くします。どちらの能力も練習次第で伸ばせるため、焦らずコツコツ取り組むことが大切です。
友達とのカラオケで、“ピッチ”と“音階”の話題が出たとき、私はこう答えました。
「ピッチは音そのものの高さ、音階は音の並び方の規則なんだ。つまり、ピッチは頭の中の音の高さを測る定規、音階は音楽の設計図みたいなものだよ。」すると友達は、同じ曲を歌っているのに歌詞のニュアンスが変わる理由を、音階の違いと音の高さの組み合わせだと理解して納得してくれました。
その後、私たちは一緒にメジャーとマイナーの音階を聴き比べ、同じメロディーでも雰囲気がどう違うかを実感。
この体験から、音楽をもっと深く感じられるようになった気がします。ピッチと音階は、ただ知識として覚えるだけでなく、実際に耳で聴き、歌い、演奏することで“生きた情報”になります。
次の記事: ピッコロとフルートの違いを徹底解説!初心者にも分かる決定版ガイド »





















