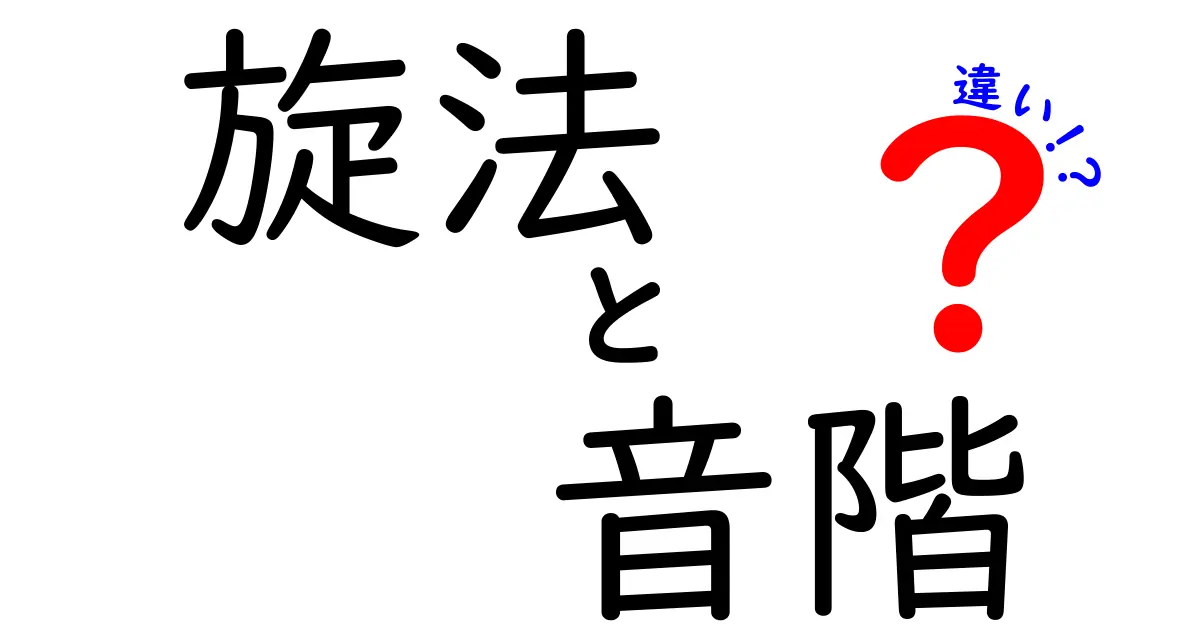

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:旋法と音階の違いを正しく理解するための基礎
音楽を学ぶときには「音階」と「旋法」という言葉が登場します。音階は音の並び方の順序を指し、上がるときの音の高さの並びを表します。たとえば、C長調の音階は「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」という7音の連なりです。一方で旋法は同じ7音の集まりを、どの音を出発点として使うかで聴こえ方が変わる考え方です。つまり、同じ音のグループを使っていても、始点を変えるとメロディーの雰囲気が大きく変わります。旋法は歴史的には教会音楽や民謡、ジャズの即興などで発展してきました。
この理解のコツは、音の“並び方”よりも“始点と結びつく印象”に着目することです。たとえば、Cメジャーの音列をそのまま使い、始点をDやEに置くと、音の並びの流れが変わり、明るさが少し変化します。実際の曲では、旋法を使って場面ごとに雰囲気を作る工夫が多く見られます。中学生のみなさんがつまずきがちな点は、音階と旋法の境界線をはっきりさせることです。音階は“並び方の型”、旋法は“始点を変える発想”だと捉えると整理しやすいです。
この章の目的は、音楽の表現を広げる第一歩としての感覚をつかむことです。音やリズムとともに、旋法の感触を体で覚えると、作曲や演奏の幅がぐんと広がります。さらに、日常の音楽づくりにも応用できる考え方を身につけることで、友達と一緒に演奏する時にも新しい発想が生まれやすくなります。
次のセクションでは、具体的な旋法の名前と特徴を見ながら、音の聞こえ方の違いを体感する練習に進みます。
具体例:イオニアンとその他の旋法で感じを比べてみる
ここでは代表的な旋法をいくつか取り上げ、音の並びと感じの違いを見ていきます。まず7つの旋法には、イオニアン(長調に対応)、ドリアン、フリジアン、リディアン、ミクソリディアン、エオリアン(自然短調)、ロクリアンがあります。
同じ音列を使いながら始点を変えると、音の結びつきが変化します。例えば、Cイオニアンは明るく安定した響きですが、Cドリアンは第6音が下がることによって切なくも聞こえます。Cフリジアンは降調感が強く、Cリディアンは第4音が上がることで幻想的な印象に。Cミクソリディアンは開放感があり、Cエオリアンは暗めの雰囲気、Cロクリアンは緊張感が高い響きです。
このように、同じ7音のグループを使っていても、旋法の違いにより曲のムードが大きく変わります。実際には、同じ7音の組み合わせを使いながらも、曲の開始音を変え、歌詞のメロディーと組み合わせていくと、曲全体の雰囲気がガラリと変わります。練習としては、まずピアノでC系の音列を使い、各旋法の始点を変えて同じメロディーを奏でてみると良いでしょう。こうすることで、旋法の感覚が体感として身についていきます。
実際には、同じ7音のグループを使いながら、曲の開始音を変え、歌詞のメロディーと組み合わせていくと、曲全体の雰囲気が大きく変わります。ここでの表は、主要な旋法とその特徴を目で確認する手助けになります。表を見ながら、学校の音楽の課題や自分の好きな曲にどの旋法が近いかを考えてみると、理解が深まります。さらに、実践としては、ピアノやギターで一つの主旋律を、7つの旋法で同時に演奏してみる練習をおすすめします。こうした練習を重ねると、旋法の「感じ方」が体で覚えられ、即興のときにも自然と活かせるようになります。
今日は友だちと音楽室で旋法の話をしていたとき、私はふと気づいた。旋法は難しい用語ではなく、日常の音楽体験を少し変える“視点”だった。たとえば、同じC音列を使っても、始点をDに置くと耳に届く響きが少し違う。これが旋法の面白さで、映画の場面転換のように気分を切り替える道具になる。私は実際の作曲や即興で、始点を意識的に変える練習を始めた。すると、同じコード進行でも新鮮さが生まれ、歌詞の伝え方まで変わってくると感じた。大切なのは、旋法を“使い方のヒント”として捉えること。
前の記事: « 合唱と歌唱の違いを中学生にもわかるやさしい解説!





















