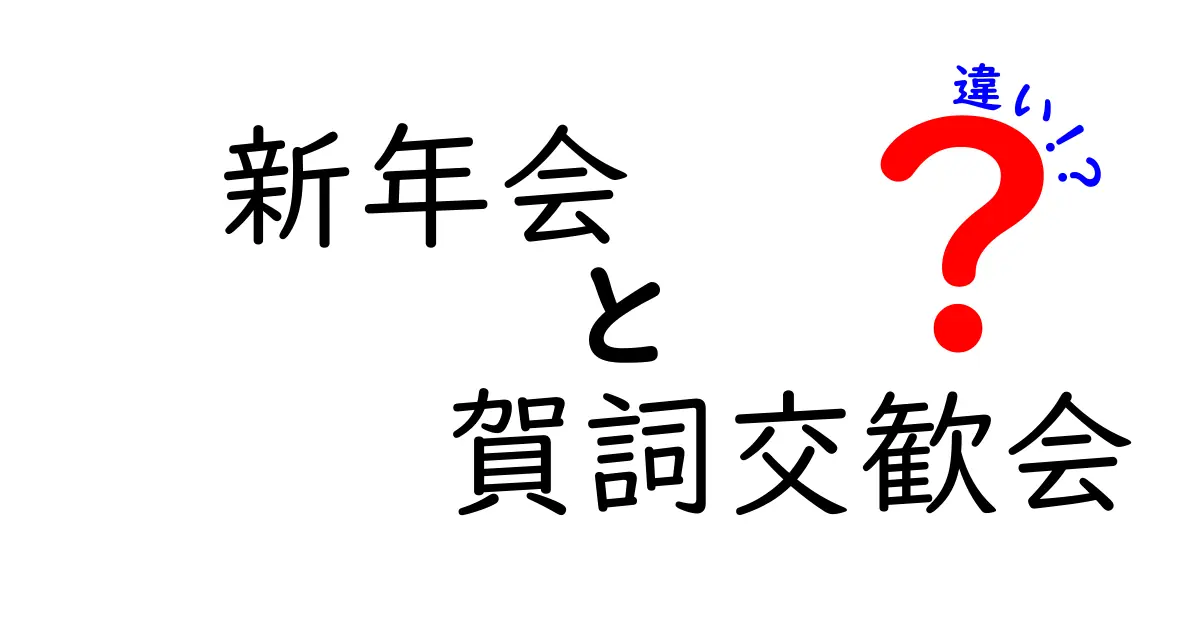

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
新年会と賀詞交歓会の違いを詳しく解説!意味・目的・使い分け・マナーまで完全ガイド
定義と対象
新年会とは、職場の仲間や部署などが集まり、新年を祝って親睦を深める目的で開かれる会のことです。基本的にはカジュアル寄りの場であり、飲食を楽しみながら日頃の業務の緊張をほどく役割もあります。
参加者は主に社内の同僚・部下・上司といったメンバーで構成され、社内の連帯感を高めるための非公式寄りのイベントとして位置づけられることが多いです。
一方、賀詞交歓会とは企業・団体が新年の挨拶回りを兼ねて、社外の取引先・顧客・メディア・協力企業などを招待する公式寄りの行事です。会場はホテルや宴会場など格式の高い場所になることが多く、ビジネスマナーを意識した進行と挨拶の順序が厳格になることがあります。
この二つは同じ「新年の行事」という枠組みで語られることが多いですが、目的・対象・雰囲気が根本的に異なる点が大きな見分け所です。新年会は内部の仲間づくり、賀詞交歓会は外部との信頼関係づくりを主眼とします。具体的な場面を思い浮かべると、社内のミーティング後の一杯と、取引先を招く正式な晩餐会の違いだと整理すると理解しやすいでしょう。
この区別を正しく理解しておくと、招待状の文面・会場選び・進行の計画がスムーズになります。誤解を生まないためには、イベント名だけでなく本来の目的を確認することが大切です。
目的と場の雰囲
雰囲3>新年会は、社員同士のコミュニケーションを深め、日頃の仕事の緊張を解きほぐす場としての目的が強いです。宴席の構成も柔らかく、ゲームや余興が入ることが多く、笑いと和やかさを生む工夫が盛り込まれます。場所は社内の会場や居酒屋・レストランなど参加しやすい場所が選ばれ、自由度の高い進行になることが多いです。
賀詞交歓会は、社外の関係者との信頼関係を構築することを重視します。挨拶の順序、乾杯のタイミング、名刺交換の作法、スピーチの長さなど、ビジネスマナーの順守が重視されます。会場もホテルの宴会場など格式の高い場所を選ぶ傾向があり、参加者は事前に準備した挨拶文を用意するのが普通です。
このように、目的の違いは会の設計に直接反映します。新年会では相互理解と親密さ、賀詞交歓会では信頼とビジネス関係の拡張を目指すため、会の運営方法も異なるのです。最終的には、出席者が快適に過ごせるよう、場の空気感と礼節のバランスをとることが大切になります。
目的と場の雰囲気
新年会は、社員同士のコミュニケーションを深め、日頃の仕事の緊張を解きほぐす場としての目的が強いです。宴席の構成も柔らかく、ゲームや余興が入ることが多く、笑いと和やかさを生む工夫が盛り込まれます。場所は社内の会場や居酒屋・レストランなど参加しやすい場所が選ばれ、自由度の高い進行になることが多いです。
賀詞交歓会は、社外の関係者との信頼関係を構築することを重視します。挨拶の順序、乾杯のタイミング、名刺交換の作法、スピーチの長さなど、ビジネスマナーの順守が重視されます。会場もホテルの宴会場など格式の高い場所を選ぶ傾向があり、参加者は事前に準備した挨拶文を用意するのが普通です。
このように、目的の違いは会の設計に直接反映します。新年会では相互理解と親密さ、賀詞交歓会では信頼とビジネス関係の拡張を目指すため、会の運営方法も異なるのです。最終的には、出席者が快適に過ごせるよう、場の空気感と礼節のバランスをとることが大切になります。
参加者とマナー
新年会の参加者は基本的に社内の同僚・上司・部下で構成され、横のつながりや世代間の交流を深めることが最優先されます。会場の設定もカジュアル寄りで、服装は通常のビジネスカジュアル〜ライトスーツ程度が多いです。名刺交換をする機会はありますが、社外の取引先と比べて形式張らないケースが多いのが特徴です。
賀詞交歓会の参加者は社外の関係者が中心です。取引先の担当者、クライアント、業界の記者など、普段は距離のある相手と正式に名刺を交換します。服装はスーツが基本で、挨拶の順序、話す時間、話題の選定など、事前準備とマナーの徹底が求められます。待機中の姿勢、乾杯の挨拶、名刺の受け取り方まで注意を払う必要があります。
両方のイベントで共通するポイントは、遅刻を避ける、乾杯の前に一斉の挨拶を行う、会話の際には相手の話をよく聞く、席次のマナーを守る、という基本です。いずれの場も相手を尊重する姿勢が最も大切だという点を忘れないでください。
使い分けの実例と準備
実務での使い分けの実例を挙げると、年始の社内行事としての「新年会」を企画し、取引先へ招待状を送る場合は「賀詞交歓会」として位置づけます。準備の段階では、進行表・挨拶文・名刺交換台帳・写真撮影の順序などを事前に決め、当日の流れを関係者に共有します。新年会では余興の企画やゲーム、鏡割りなどの演出を取り入れる一方、賀詞交歓会では開会挨拶と代表者のスピーチ、乾杯の挨拶、名刺交換の時間配分などを重視します。
イベントの終わり方も異なります。新年会は「また来年もよろしくお願いします」という雰囲気で閉じることが多く、賀詞交歓会は「本年もよろしくお願いいたします」という形式的なコメントとともに、名刺リストの整理・フォローアップの計画を立てます。ここで重要なのは、事後のフォローアップをどう行うかです。メールや手紙、来年度の商談につなげる連絡の取り方を決めておくと良いでしょう。
実務表での違いを整理する
以下の表は、両者の特徴を一目で比較できるように作成したものです。実務上の判断材料として、会の計画段階で役立ちます。
去年、部活の同級生と新年会の話で盛り上がったことがあります。私たちは学校の仲間としての親睦を目的に、カジュアルな雰囲気で飲み会を開きました。一方、別の年には親戚や地域の企業の賀詞交歓会に参加する機会があり、名刺を交換する場面に緊張感を覚えました。そんな経験から、同じ“新年の集まり”でも、内部の親密さを重視する新年会と、外部の信頼構築を狙う賀詞交歓会では準備すべきポイントがまるで違うと実感しました。名刺の扱い、挨拶の言葉選び、場の空気づくり、そして何より相手を尊重する姿勢が、どちらでも大切だという結論に至りました。
次の記事: 懇親会と新年会の違いを徹底解説!場面別に使い分けるコツと実例 »





















