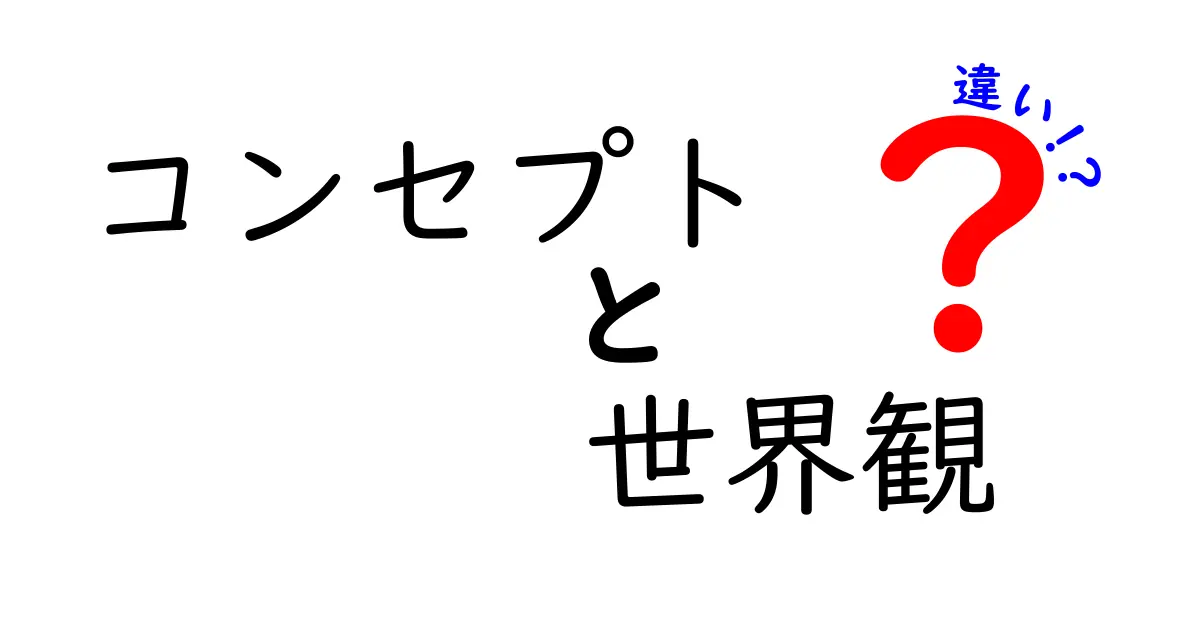

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
コンセプトと世界観の基本を整理する
この二つの言葉は、似ているようで別の役割を持っています。コンセプトは何を作るのか、なぜそれが必要なのかという目的地を決める羅針盤です。実務では「この商品は何を解決するのか」「誰に向けて作るのか」を一文で表現することが求められます。これが企画の核となり、プロジェクトの方向性をまっすぐ示します。対して、世界観はその作品やブランドが存在する“場の雰囲気”を作る要素であり、色味、言い回し、登場人物の性格、描かれる風景など、体験の空気を決めます。世界観がしっかりしていれば、伝えたい感情が伝わりやすく、長く関わってくれる人を生み出します。例えばゲームの企画段階では、コンセプトが「仲間と協力して難局を乗り越える体験」という核心を決め、世界観は中世風の町並み、現代風の銃声、ロボットが街灯の下で走る景色といった具体性でその体験の“匂い”を作ります。
この組み合わせがうまく機能すると、デザイナーは色を選び、ライターは語調を決め、エンジニアは機能を設計する際の判断材料として同じ目標を見失うことが少なくなります。
大切なのは、コンセプトが短く強い言葉として切り出せる一方、世界観は長く続くストーリーや背景を支える土台になる、という点です。
この考え方を日常の企画作業にも取り入れると、情報の伝え方が統一され、関係者との認識齟齬が減ります。ちなみに、コンセプトと世界観は使い分けるだけでなく、相互に補完し合う関係だと覚えておくとよいでしょう。
違いを実務に活かす具体例と使い分け方
このセクションでは、教育現場、商品開発、物語づくりなどの現場で、どうやってコンセプトと世界観を使い分けるかを具体的な例で説明します。入口となるコンセプトは短く覚えやすい一文が有効です。例として「誰でも自分の力で成長できる学習体験」という表現を使い、これを教材の副題やキャッチコピーにします。これに対し世界観は「学習場所の雰囲気」「登場人物の名前と性格」「挿絵の色味」など、体験の場面を具体的に作る要素をそろえます。こうして二つを分けて考えると、企画段階で迷いが減り、関係者との会話もスムーズになります。例えば教材のアプリを出すとき、コンセプトは「楽しく学べることを最優先にする」という一文に集約し、世界観は画面の色、フォント、アイコンの形、キャラクターの性格づけといった要素で統一します。色使いを絞り、語調を同じリズムに整えると、初回利用時の印象が一貫し、学習の進捗を感じやすくなります。
また、世界観を強めたい場面は、ストーリーボードや動画のトーン、案内文の書き方まで影響します。教材の導入部を短い問いかけで始め、次の演習へと緩やかに誘導することで、世界観が自然と堅牢になります。最後に覚えておくべき点として、コンセプトは変わらない目的地、世界観は旅の風景であると理解すると、制作の過程で「何を優先するべきか」が迷いにくくなります。
世界観という言葉を友だちと雑談しているときのように、あれこれ語り合うのが楽しいね。世界観は作品の空気を決める“力”で、登場人物の喋り方や街の匂い、色味まで連動してくる。例えば新作アニメの話題なら、世界観を固めると設定の矛盾が減って、視聴者が世界に入り込みやすくなる。結局、世界観は“その世界がどう感じられるか”を長く支える基盤なんだ。短い説明だけでは伝えきれない深さを、実際の表現の中でどう統一するかを、かつての作品づくりの経験とともに思い出すといいよ。





















