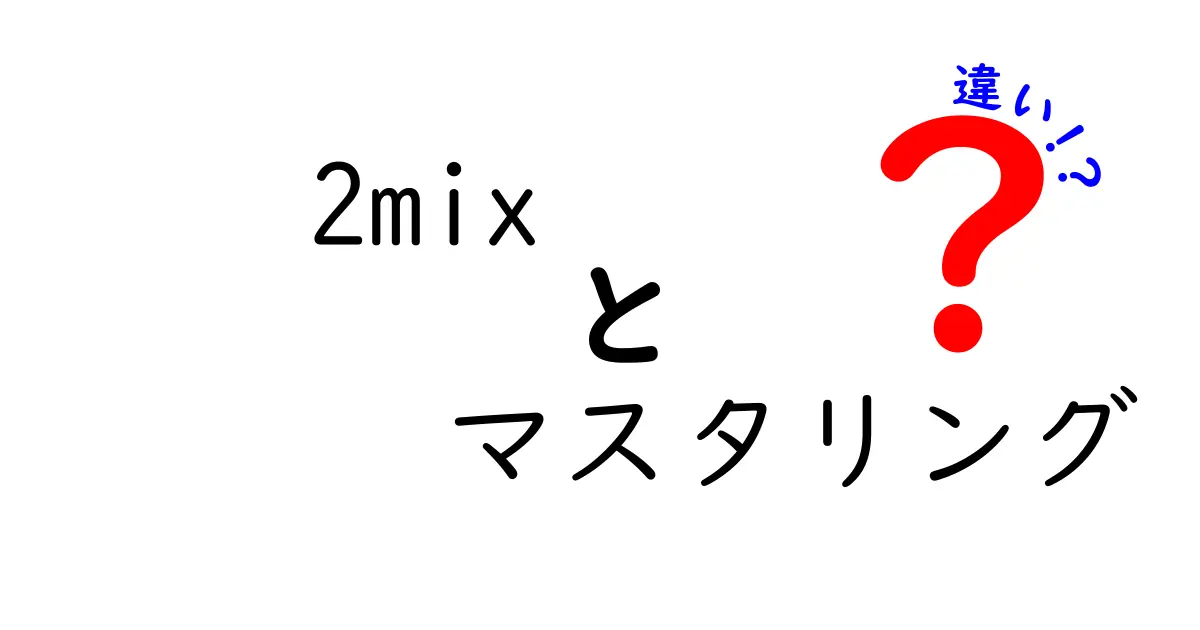

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
2mixとマスタリングの違いを理解するための基礎
音楽制作の現場では2mixとマスタリングという言葉をよく耳にします。2mixは多くの楽器や声を一つのステレオトラックに混ぜ合わせる作業のことです。つまり、曲全体の音量バランスや音色の決定権を握る“混ぜる段階の最終形”を作る工程です。ここで決まる点は、楽器の大きさ関係や位置感、どの音が前に出るかといった聴感の印象です。これらの判断はジャンルやリスナーの環境に大きく左右されます。
マスタリングは完成したミックスをさらに磨く段階です。ここでは、音圧を整えつつ、低音から高音までの帯域バランスを微調整し、再生機器の違いで聴こえ方が変わるのを抑えます。マスタリングは曲全体の適合性と聴感の一貫性を高める最終工程であり、リスナーがどこで聴いても違和感が小さくなるように設計します。
この二つの作業は目的と対象が異なるため、混同されがちですが、実務では「まずミックスを整え、次にマスタリングで仕上げる」という順序が基本です。2mixでの良いバランスがあればあるほど、マスタリングの効果は際立ちます。音楽ジャンルごとに、聴く環境ごとに良い音の基準は変わるため、学習者はこの違いをしっかり認識しておくことが大切です。
本題:2mixとマスタリングの実務的な違いを整理する
ここからは具体的な作業内容の違いを、初心者にも伝わるようにやさしく分解します。2mixの主な目的は「曲全体のバランスを作ること」、つまりどの楽器を前に出すか、どの帯域をどの程度持たせるかを決める作業です。ここではキックドラムのパンニング、ボーカルのEQ、ギターのリバーブ感など、細かな調整を通じて曲の“顔”を決めます。
一方のマスタリングは「曲を世界中の再生機器で聴けるように最適化すること」が目的です。音量レベルの最大化だけでなく、コントラストの調整、位相の微修正、ラウドネスの管理、データのフォーマット適合など、幅広い工程が必要となります。
最終的には、リスナーにとって聴き心地の良さと曲の伝えたい感情が両立するように微調整します。
音の厚みと抜けを両立させる感覚は、実際に触ってみるとすぐに分かるようになります。
2mixは曲の内部の世界を作る作業、マスタリングは外部へ届ける世界を整える作業という理解で覚えておくと、混乱せずに学習を進められます。
結論として、2mixが“曲の現場の完成度を作る工程”で、マスタリングが“リスナーに届ける最終仕上げ”です。この二つの作業を正しく分けて理解することが、失敗しない音作りの第一歩となります。
今日は2mixとマスタリングの話題を雑談風に深掘りします。例えば、音のエネルギーを保ちながら大きく聴かせるには、どの段階でどんな判断が必要かを、学校の友だちとおしゃべりする感覚で解説します。結論はシンプルで、聴く人の耳の成長と共鳴する音作りを心がけよう、ということです。音の世界には規則とセンスの両方が大切で、2mixとマスタリングの違いを知れば、音はもっと自由に操れるようになります。
前の記事: « ボレロと旋律の違いを徹底解説:似ているようで分かる音楽のポイント
次の記事: 楽器と音階の違いを徹底解説:音階が楽器ごとにどう響くのか »





















