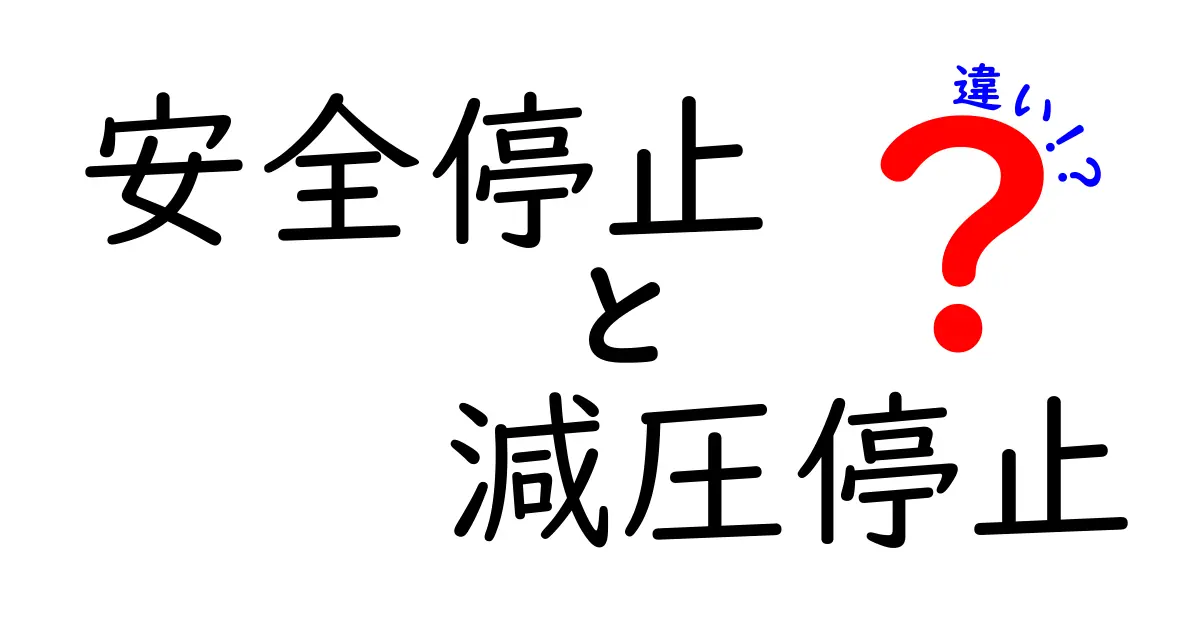

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
安全停止と減圧停止の基本を理解する
このセクションでは安全停止と減圧停止という言葉の意味と、どう違うのかを大局的に説明します。ダイビングでは水面へ上がるときに体内の窒素が急激に減らないようにする工夫がいくつかあり、その中でも「安全停止」と「減圧停止」は特に重要です。安全停止は“安全のための停止”と呼ばれ、深度約5メートル付近で数分間体を安定させて体内の窒素をゆっくり放出させる仕組みです。一方、減圧停止はより長く・深い潜水の後に、規定された深さで複数回停止を行い窒素の排出スケジュールを守る、いわば専門的な停止です。
この両者は「停止」という共通点をもちますが、目的・強さ・必要性が大きく異なります。
分かりやすく言えば、安全停止は“最低限の安全を確保するための止まり方”で、減圧停止は“計画的に窒素を排出するための段階的な止まり方”です。
初心者の方には、最初は安全停止の意味と実施の仕方を覚えることから始め、より深い潜水を目指すときに減圧停止の考え方を身につけると良いでしょう。
安全停止とは何か
安全停止とは、基本的には水深5メートル前後で数分間体を安定させて窒素の排出を助ける処置です。
目的は「急な浮力変化を抑え、窒素が体内に過剰に滞在するのを防ぐ」ことにあります。
多くのダイビング規範では、リクリエーショナルダイビングでは安全停止を推奨または義務付けているケースが多く、上昇中に無理に速く浮かないように注意することが大切です。
実際には、潜水終了時の先に待つ水面へ向けて、5メートル付近で3分から5分程度の時間を確保します。
この間、呼吸を落ち着いて行い、浮力を安定させることがポイントです。
安定した浮力を保つことで、体内の窒素がゆっくりと減圧され、後の減圧停止を待つ時間が短くなる場合もあります。
なお、水温や水流、体調、ダイブの深さなどの条件によっては安全停止の時間が微妙に変わることがあります。このような条件を理解して計画を立てることが、安全停止を正しく活用する第一歩です。
減圧停止とは何か
減圧停止は、安全停止よりも深い場所や長い時間の潜水で必要になる停止です。
潜水後、体内の窒素が急速に排出されると体の組織に小さな気泡ができ、これが上昇に伴って拡大すると“減圧病”と呼ばれる危険な状態につながります。
このリスクを抑えるためには、規定された深さで複数回停止を行い、窒素の排出を段階的に進めることが必要です。
この計画は、ダイブコンピューターやダイブテーブルがこの“減圧停止の段階”を計算して表示します。
停止の回数や時間は、潜水の深さ・水温・体重・浮力の安定具合・個人差などによって変わります。
もしこの計算を守らず急いで浮かぶと、気泡が体内で成長してしまい、痛みや重篤な症状を伴う可能性があります。
従って、減圧停止は“計画的な停止”が必要な場面です。
減圧停止が必要になるかどうかは、潜水のプロファイル(深さと時間の組み合わせ)と機器の情報に左右される点を理解しておくことが大切です。
実務での違いと使い分け
現場での使い分けは、潜水の深さと時間の長さ、計画の段階によって決まります。
基本的には、ほとんどのレクリエーションダイビングでは安全停止を取り入れることが推奨され、減圧停止が必要になるのは深場(一般的には深さの閾値を超える潜水や複数日の潜水)や長時間の潜水、連続するダイブなどの場面です。
ダイブ計画を立てるときは、ダイブテーブルやダイブコンピューターの指示を必ず確認します。
安全停止は「最低限の安全を確保するための停止」であり、減圧停止は「窒素排出を計画的に進めるための停止」です。
これらの違いを理解することで、ダイビング中の無理な行動を避け、健康と安全を守ることができます。
また、現場では水温や水流、混在する他の生物、器材の状態といった周辺条件にも注意が必要です。
最適な安全停止と減圧停止の使い分けには、経験値と適切な指示を受ける指導者の存在が大きな役割を果たします。
安全停止の具体的な手順と避けるべき誤解
安全停止を行う際の基本的な手順は次のとおりです。
1. 水深5メートル付近を維持できるように浮力を安定させる。
2. 重さの調整をして、移動を最小限にとどめる。
3. 呼吸を落ち着かせ、気泡の発生を抑える。
4. 3分から5分程度、浮力を保ちながら窒素の排出を待つ。
5. 指示があれば、それに従ってゆっくりと水深を変えていく。
よくある誤解として「安全停止は必ず3分で終わらせればいい」という考えがありますが、個人差と条件によって適切な時間は異なります。
大切なのは「自分のダイブプランに合った時間を確保すること」と浮力を安定して保つことです。
現場では、周囲のダイバーの動きにも配慮して、衝突を避けるように立ち振る舞いましょう。
減圧停止が必要になる場面と計算の基本
減圧停止が必要になる場面は、安全停止だけではなく、深さが深い場合や長時間の潜水、連続するダイブなど、窒素が体内に蓄積される可能性が高いときです。
この計画は、ダイブコンピューターが自動で計算したり、ダイブテーブルに基づいて手作業で算出することができます。
計算の基本は、「現在の深さと潜水時間」「前のダイブの情報(残留窒素)」を組み合わせて、必要な停止の深さと時間を決めることです。
実際の現場では、指示に従って各停止を順に行い、途中で浮力を崩さないように注意する必要があります。
減圧停止を遵守することは、体にとって過度な窒素を蓄積させず、後の安全な水面移行を確保するための基本です。
もし、体調が悪い、疲れている、水分補給が不十分などの要因がある場合は、ダイビングを中止する判断も重要です。
この表は、安全停止と減圧停止の基本的な違いを一目で確認できるようにしたものです。
ダイビングの計画を立てるときは、表に示した点を頭に入れて、各停止を安全に完了させることが大切です。
止まる時間が長くなればなるほど、体が窒素を排出する機会が増え、上がるときの安全性が高まります。
ただし、過度な待機は浮力の乱れや体力の消耗につながることもあるので、状況を見ながら適切に調整しましょう。
このような判断は、訓練を受けたダイバーや指導者のアドバイスを参考にして、個々のダイブプランに沿って行うことが重要です。
今日は友人とダイビングの話をしながら、安全停止と減圧停止の違いを深掘りしました。安全停止は水深5m前後で3~5分ほど体を安定させ窒素の排出を穏やかに進める“準備運動”的な停止。減圧停止は深場・長時間・連続ダイブの後に必要となる段階的な停止で、窒素を計画的に排出して潜水後の体調を守る仕組みです。実際には機器と計画が大きな役割を果たします。私が感じたのは、ダイブプランを作るときはまず安全停止を心に置き、次に減圧停止の可能性を考えると、迷いが減って上がるときも落ち着いて対応できるということです。ダイビングは体と心のバランスが大事。焦らず、機器の指示に素直に従うことで、安全に楽しく海と付き合えると思います。





















