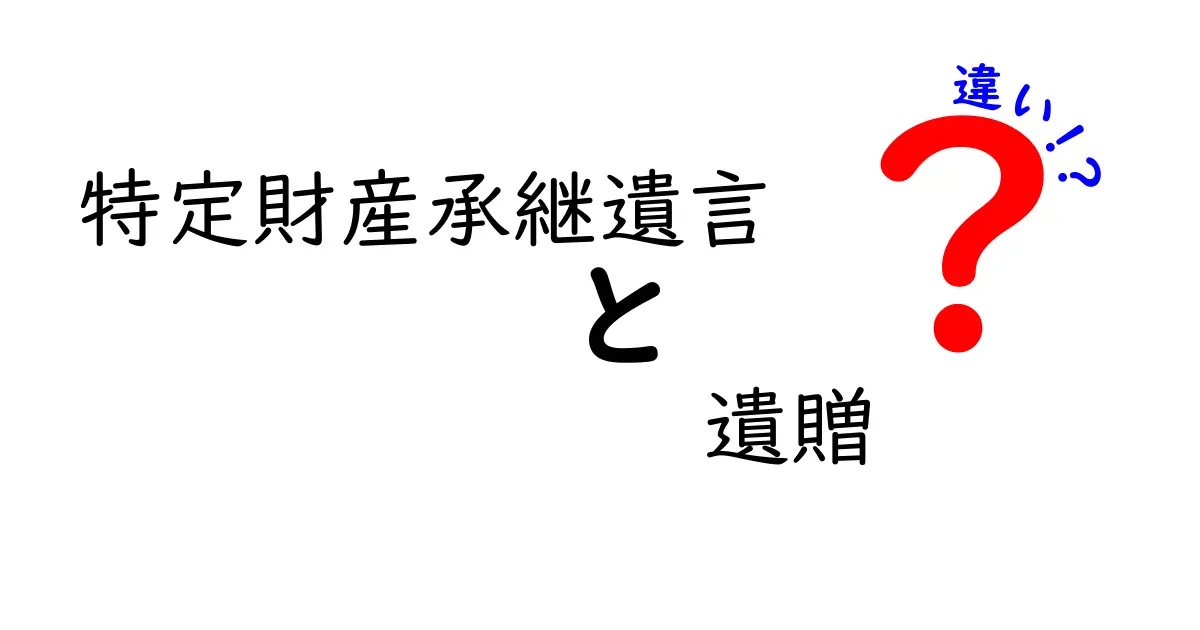

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
特定財産承継遺言とは何かと遺贈との基本的な違い
特定財産承継遺言とは、死亡後に特定の財産を特定の受遺者に引き継ぐことを目的とする遺言の一つです。ここで言う特定財産とは、例えば家や土地、特定の株式、企業の現物など、名称と具体が定められた財産を指します。
このような遺言は、財産の「現物承継」を重視する場面で使われることが多く、遺産全体の分割方法をあらかじめ決めることで後の紛争を減らす狙いがあります。
一方、遺贈は遺言の中で財産を特定の人に無償で譲り渡すことを指す広い概念です。遺贈には現物遺贈や金銭の遺贈など、さまざまな形があります。
この2つの違いをざっくりまとめると、特定財産承継遺言は「特定の財産を特定の人へ渡す」ことを目的とする遺言の方法のひとつであり、遺贈は遺言の中で財産を特定の人に譲る一般的なしくみだと理解できます。
実務上は、特定財産承継遺言と遺贈が組み合わさる場面もあり、遺言全体の設計次第で遺産分割の結果が大きく変わります。
なお、遺産分割では遺留分と呼ばれる法定の最低取得分が存在するため、いくら特定の財産を特定の人へ渡すと決めても、他の相続人の遺留分を侵害しないよう配慮が必要です。
この点を押さえておくと、将来のトラブルを事前に回避しやすくなります。
以下のポイントを覚えておくと、後で読み返したときに理解が進みやすいです。
1) 特定財産承継遺言は「特定財産」を中心に受遺者を決めるケースが多いこと。
2) 遺贈は「財産を誰に渡すか」という広い意味で使われる遺言の機能の一部であること。
3) 遺留分の存在により、全てを特定財産で独占するような遺言は実務上制限を受けることがあること。
4) 公正証書遺言や自筆遺言など、遺言の形式によって証明力や実効性が変わること。
このような前提を知っておくと、誰に何を渡すのかを考えるときに、現実的な選択をしやすくなります。
特定財産承継遺言の仕組みと具体的な使い方
特定財産承継遺言を作るときには、まずどの財産を「特定財産」として扱うのかを明確にします。
次に、それを受け取る人を定め、どのタイミングでその財産を移転させるのかを記します。
このとき重要なのは、現物の移転をすべての遺産分割と同時に行うのか、それとも遺産の一部として分割するのかという点です。
さらに、遺言執行者の指定があると、財産の移転作業を専門家が代行してくれるため、実務上の負担が軽減されます。
公正証書遺言で作成する場合には、公証人の関与により証明力が高まり、遺言の執行がスムーズになるメリットがあります。
ただし、遺言の内容が過度に偏っていると、他の相続人の遺留分を侵害する恐れがあるため、 専門家の助言を受けながら作成することが重要です。
具体的な使い方としては、家業を継ぐ次世代へ特定の株式や社有地を譲るケース、長年大切にしてきた家宝や思い出の品を特定の家族に渡したい場合、などが挙げられます。
このような目的を実現するには、財産の評価、相続税の見通し、他の相続人の権利保護を同時に考える必要があります。
遺言の形態選択としては、公正証書遺言が堅牢性の面で有利ですが費用と手間がかかります。自筆遺言はコストを抑えられますが、書き間違いがあると無効になるリスクがあります。自分の状況に最も適した形式を選ぶことが大切です。
このセクションでは、特定財産承継遺言の実務上のポイントを押さえつつ、遺言を作成する前に確認すべき点を整理しました。
複雑な財産が絡む場合には、専門家のアドバイスを受けることが大切です。
後でトラブルにならないよう、遺言の草案を家族と共有し、理解を得る努力も忘れずに行いましょう。
遺贈とは何か、いつ使われるのか、どんな法的効果があるのか
遺贈は、遺言の中で財産を特定の人に譲ることを意味します。遺贈には「特定遺贈」と「総遺贈」などの形があり、財産の種類や数量を明確にする点が特徴です。特定の財産を特定の相手に渡す場合には、どの財産が対象かを遺言書に詳しく書く必要があります。
遺贈は原則として死亡時に発生する法的効果を持ち、相続開始と同時に相手に権利が生じます。
ただし、遺言による遺贈でも遺留分は尊重されます。遺留分とは、相続人が最低限受け取る権利のことで、遺贈によって完全に奪われることはありません。
遺贈の実務上の利点は、相続人間の争いを避けやすい点です。財産を特定の人へ直接渡すことで、他の相続人との分割協議を簡略化できる場合があります。
一方のデメリットとしては、遺贈が実際には実現しないことが起こり得る点です。たとえば遺贈の対象となる財産が既に処分されていたり、遺贈を受ける人の権利が法的に認められない場合には、遺贈の実行が難しくなります。
このような背景を踏まえ、遺贈を検討するときには、対象財産の確定性、相続人間の法的関係、遺留分の調整を事前に整理することが重要です。
さらに、遺贈は遺言の形式によって効力が左右されることがあります。公正証書遺言での遺贈は証明力が高く、執行がスムーズになる傾向があります。
次に、特定財産承継遺言と遺贈の違いを具体的な場面で比較してみましょう。
家族の中で特定の資産を特定の人へ渡したい場合には特定財産承継遺言が有効です。
一方、財産の分配を大幅に整理したい場合には遺贈として複数の財産を複数の受遺者に割り当てる方法が適しています。
いずれにしても、遺言の形式、財産の性質、遺留分の存在を総合的に検討することが大切です。
特定財産承継遺言と遺贈の違いを具体例で分かりやすく比較
下の表は、特定財産承継遺言と遺贈の違いをざっくりと比較したものです。
この表を読みながら、自分のケースでどちらが適しているかを考えてみてください。
ポイントとしては、対象財産の特定の有無、遺言の形式、遺留分の関係、実務の難易度の順に気をつける点です。
このように、特定財産承継遺言と遺贈は目的や適用範囲、実務的な取り扱いに違いがあります。
どちらを選ぶかは、財産の性質、相続人間の関係、将来の分配の方針、そして法的リスクの観点から判断することが大切です。
最終的には、専門家のアドバイスを受けながら自分の家族に最適な構成を組むのが安心です。
この記事を読んでいるあなたが、将来のトラブルを減らし、遺言の目的を確実に実現できるようになることを願っています。
次の記事: mlmと代理店の違いを徹底解説 初心者でも分かる見極めガイド »





















