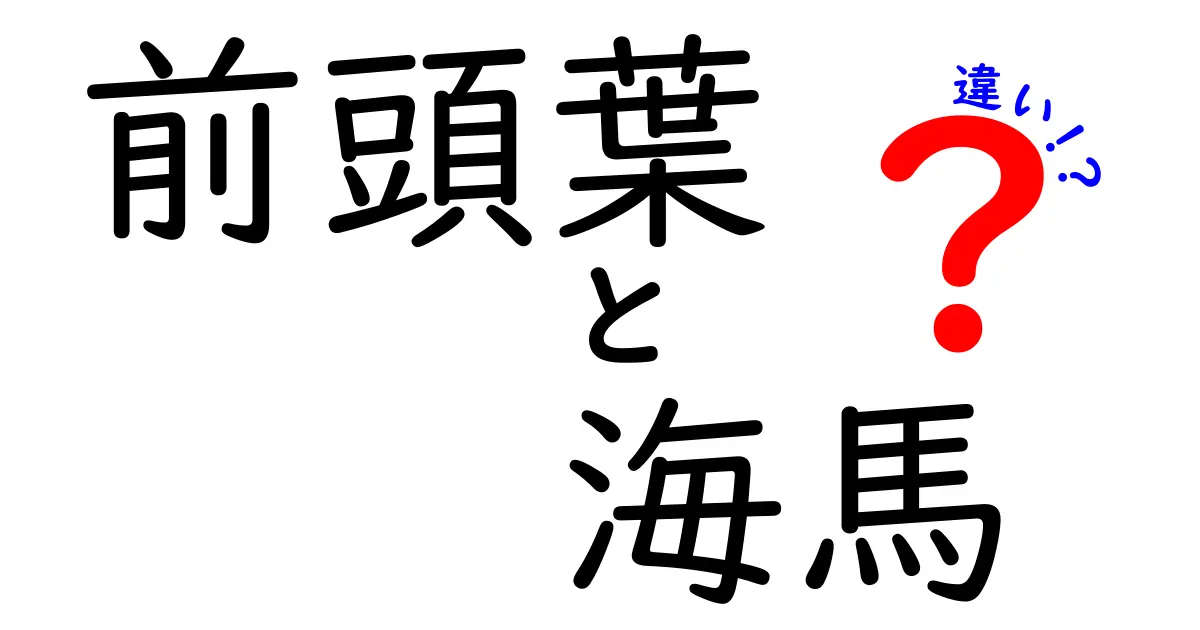

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
前頭葉と海馬の基本的な違い
この章では、脳の中の前頭葉と海馬がどこにあり、どんな役割を果たすのかを、日常の例を使ってやさしく解説します。前頭葉は額のあたりに位置しており、私たちの計画を立てる力、衝動を抑える力、複雑な判断をする力などを担当します。例えば、宿題の計画を立てるときや時間割を作るとき、正しい選択をしたいときに前頭葉が働きます。反対に海馬は耳の少し後ろ寄り、深い場所にあります。新しいことを覚えるとき、道案内を覚えるとき、体験した出来事を記憶として残す役割を担います。これらは別々の仕事のようでいて、実は密接に協力して私たちの行動を生み出しています。
この二つの部位を同時に考えると、日常の小さな選択一つひとつがどう作られているのかが見えてきます。
前頭葉と海馬は脳の中で「異なるチームのように働く」ことが多いのですが、実際には連携して動くことが多いです。例えば、新しい友だちと会ったとき、第一印象をどう扱うかを決めるためには前頭葉が状況判断をし、過去の経験(記憶)をもとに海馬が情報を引っ張ってきます。こうした連携があるからこそ、私たちは新しい環境に適応したり、過去の経験から正しい判断を選んだりできるのです。
日常生活での役割の違いを具体的に感じる場面
日常生活には「計画」「抑制」「判断」「記憶」という複数の要素が混ざっています。この混ざり方を理解すると、学習がもっと楽しく進むようになります。たとえば、授業中に先生が新しいテーマを提示したとき、前頭葉は「この新しい情報をどう使うか」を考える計画を作ります。海馬は「この情報をこれまでの知識と結びつけるにはどうするべきか」を探します。こうした連携がうまくいくと、授業内容が頭に定着しやすくなります。日常の中でよく考える癖をつけることは、前頭葉の働きを鍛える良い練習になります。一方で新しいことに挑戦したとき緊張や不安が強いと前頭葉の働きが乱れることもあります。そんなときは深呼吸をして心を落ち着かせ、経験を思い出してから行動を決めるといった工夫が有効です。
この章を読んでくれたみなさんへ、覚えておいてほしいのは「脳は一つの器官で完結するのではなく、複数の部位が協力して働いている」ということです。前頭葉は未来の行動をつくる設計図、海馬は過去の経験を土台にして新しい情報を整理する整理係です。これらが力を合わせると、私たちは新しいことを学んだり、難しい判断を求められたりしても、落ち着いて対応できるようになります。脳の仕組みを知ることは、学習の道具箱を広げることにもつながります。
結論と覚えておきたいポイント
前頭葉と海馬は、私たちの毎日の行動や学習に欠かせない二つの大事な部位です。前頭葉は計画・判断・制御・抑制の役割を担い、海馬は新しい記憶を作る窓口と道案内の機能を持ちます。両者は独立して働くこともありますが、多くの場合は情報を交換しながら協力して働きます。そして、長期的な学習や複雑な行動を身につけるためには、これらの部位をバランスよく使い分けることが大切です。日常生活の中で、計画を立てるとき、記憶を呼び起こすとき、難しい選択をするときには、前頭葉と海馬の連携を意識してみましょう。
結論を日常に活かすコツの例をもう少し追加します。宿題の計画を立てるとき、海馬が覚えた経験をどう活かすかを想像して前頭葉が設計図を描く。例えば、英単語を覚えるときには、語源や語尾変化を整理してから実際の文章に落とし込みます。そんな手順を意識すると、学習の効率が上がります。自分の頭の中で「どう使うか」を整理する癖をつけるだけで、記憶は長く定着します。
ある放課後のカフェで友だちと雑談をしていると、前頭葉と海馬の話題が自然と出てきました。友だちは「計画は前頭葉、記憶は海馬が担当」と言い、僕は「記憶をどう使うかは前頭葉が決める。ときには海馬が道順を教えてくれる」という見方を追加しました。私たちは、テスト勉強のときにどの情報をどう結びつけて整理するかを、実際の体験談を交えながら話しました。日常の雑談でも、脳の仕組みを知ると学習が見違えるほど楽しくなることを、互いに再発見しました。こんな小さな話題が、次の学習の動機づけになるのだと実感しました。
次の記事: 灰白質と白質の違いを徹底解説!脳の秘密を中学生にもわかる言葉で »





















