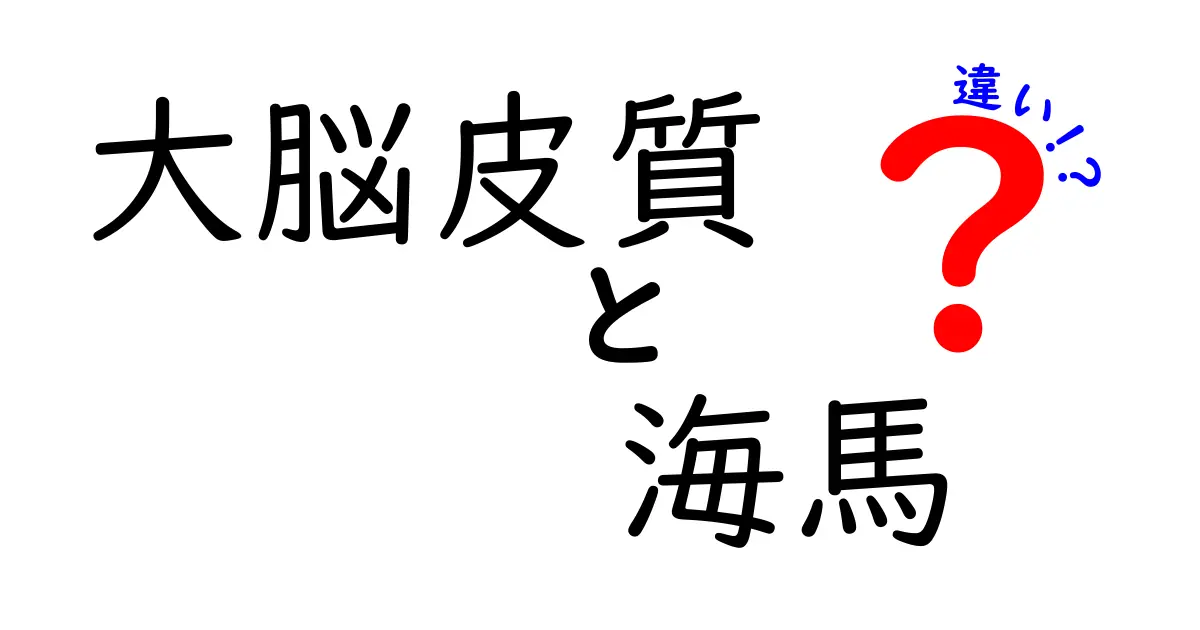

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
大脳皮質と海馬の違いを理解するための基本ガイド
まず、大脳皮質と海馬は脳の中でとても重要な役割を担う部位です。大脳皮質は思考・感覚・判断など高次の機能を司り、私たちが日常的に使う「考える力」「感じる力」を支えています。一方、海馬は新しい記憶を作り、場所の情報を結びつけて「場所の地図」を作る働きをします。これらは別々の役割を持ちながら、協力して私たちの体験を脳に蓄え、次の行動へとつなげています。大人でも理解を深めるには、まずこの2つの部位を表のように比べてみると理解が進みます。ここでは、表と例え話を使って分かりやすく解説します。
例えば、学校の授業を思い浮かべてください。授業の内容を覚えるとき、まず近くで感じる感覚や言葉の意味を整理するのが大脳皮質の仕事です。そして、授業の内容を覚えた記憶自体を“長期的に”固定するのは海馬の役割です。これらができると、道に迷わずに目的地へ行けるような感覚や、過去の出来事を思い出す際の場所のイメージが生まれます。これらの基本を押さえたうえで、次の項では部位ごとの特徴と、具体的な機能を詳しく見ていきます。
機能の違いを詳しく解く
海馬は特に新しい情報を整理して短期記憶を長期記憶へと移行させる「記憶の梱包機」のような役割を果たします。体験した事柄を順序立てて配置し、場所・人・出来事の結びつきを「地図」として作り上げます。これができると、道に迷わず目的地へ行けるような感覚や、過去の出来事を思い出すときの場所のイメージが生まれます。対照的に大脳皮質は、五感からの情報を受け取り、それを意味づけしたり判断に変えたりします。視覚の情報は後頭葉で受け取り、意味を推理するのは前頭葉の役割です。これらの連携がなければ、私たちは「何を感じているのか」「次にどうするべきか」を考えることが難しくなります。
このように、海馬は「覚える力」を、皮質は「考える力」をそれぞれ担っています。発達の過程で、皮質は徐々に複雑な知的作業を可能にしますが、海馬の機能は新しい体験を記憶として蓄えるための土台となるのです。
次のセクションでは、二つの部位が脳の中でどのように位置づけられ、どんな連携をしているのかを、表と図を使ってもう少し詳しく見ていきます。
このような違いを知ると、脳の働き方が見えてきます。覚えることと考えることは別の機能であり、両方が協力して私たちの行動を支えています。長い文章を読んで理解する場面でも、皮質が情報を整理し、海馬が記憶の形成を担うという組み合わせが多く見られます。
思考と記憶は深く結びついており、学習や日常の経験を通じてお互いに影響し続けるのです。
ねえ、海馬って名前の由来知ってるかな。実はこの部位の形が海の生き物の海馬(シーホース)に似ていることから名前がついたと言われているんだ。脳の中で海馬は長い筒状の構造をしていて、情報を受け取って記憶に結びつける役割を担う。覚えることと場所の記憶を作ることは、海馬と大脳皮質の二人三脚で動くチームみたいなもの。子どものころの記憶がふわっと蘇るとき、海馬が道案内の地図をそっと描き、皮質がその地図を意味づけして私たちの行動につなげていると考えると面白いね。
次の記事: 中心前回と運動野の違いを徹底解説!中学生にもわかるポイントと図解 »





















