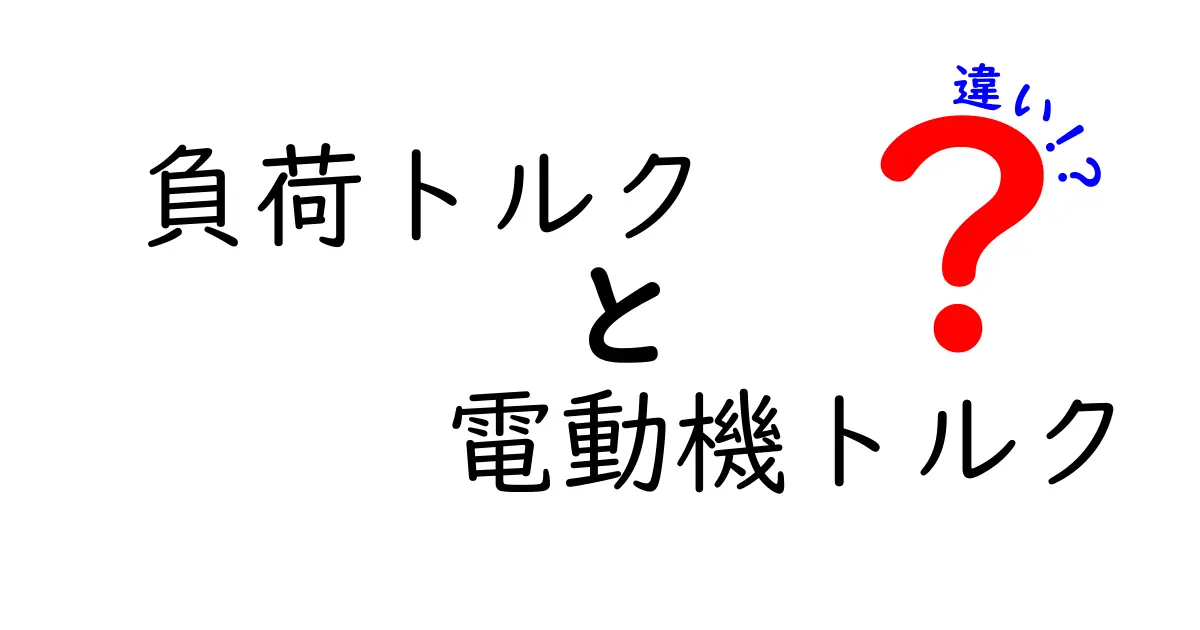

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
負荷トルクと電動機トルクの違いを徹底解説|現場で使える基礎とポイント
この解説では「負荷トルク」と「電動機トルク」の違いを、学生にも分かるよう丁寧に説明します。まずはそれぞれの意味を整理しましょう。
負荷トルクは、回転する軸に外部から働く抵抗のことを指します。工作機械でワークを回すときに外部から受ける力、摩擦、流体抵抗、ギアの嚙み合いによって発生する抵抗がこれに該当します。
一方、電動機トルクはモータ内部で発生する回転力です。コイルに電流が流れると磁場が生じ、ローターが回ろうとする力が生まれます。ここで大切なのは「モータが生む力」と「外部の力で回転が抑えられる力」を区別して理解することです。
この2つを混同してしまうと、同じモータでも回転数が変化する理由や、過負荷時の挙動が見えづらくなります。現場では、回路の設計だけでなく機械の荷重条件を正しく把握することが安全と効率につながります。
基本概念の整理
このセクションでは、負荷トルクと電動機トルクの正確な定義だけでなく、単位や測定の考え方、どのように現場で測定情報を使うかを整理します。
最初に重要なのは「トルクは力の回転方向の働き」である点です。
負荷トルクは外部からの抵抗であり、電動機トルクはモータ内部で生じる回転力です。これを混同すると、速度特性の解釈が難しくなります。
例えば速度が一定の場合、負荷トルクが大きくなるとモータが出すトルクがそれに追従する必要があり、必要出力が増えるため電流が増え、効率が低下します。
これはドライバの設定にも影響します。ここでの要点は、負荷トルクは外部条件、電動機トルクはモータの内部条件として切り離して考えることです。
現場での影響と使い分け
実務では、負荷トルクと電動機トルクの関係を適切に理解しておくことが、機械の安定運転と安全性を左右します。
例えば荷重が増えると回転数が低下し、回転速度を保つには電動機トルクを増やす必要があります。これはモータの温度上昇や過電流のリスクにもつながるため、制御装置のパラメータ調整が欠かせません。
現場のポイントとしては、負荷トルクの変化に対して電動機トルクがどの程度追従できるかを事前に評価すること、そして適切なトルク指標を選択することです。これにより、破損を防ぎ、部品寿命を延ばすことができます。強い負荷でも安定回転を維持するためには、設計時に安全率を確保すること、緊急停止条件を設定することが有効です。
比較表と実務ポイント
ここでは両者の違いを整理した表と、それを現場でどう活かすかの実務ポイントを示します。
まずは表を参照してください。
ねえ、負荷トルクと電動機トルクの話って友だちと雑談しても盛り上がるネタになるんだ。荷重が増えるとモータが出せる力だけでは回らなくなる場面が多くて、現場ではトルクのバランスを見て制御を調整する必要がある。負荷トルクが強いときには電動機トルクを上げることになるけれど、それだけでは温度が上がったり効率が悪くなったりする。だから設計者は安全率を確保しつつ、適切な指標を設定して回す方法を探る。こうした実務談義は理論だけでは見えない現場の知恵だ。





















