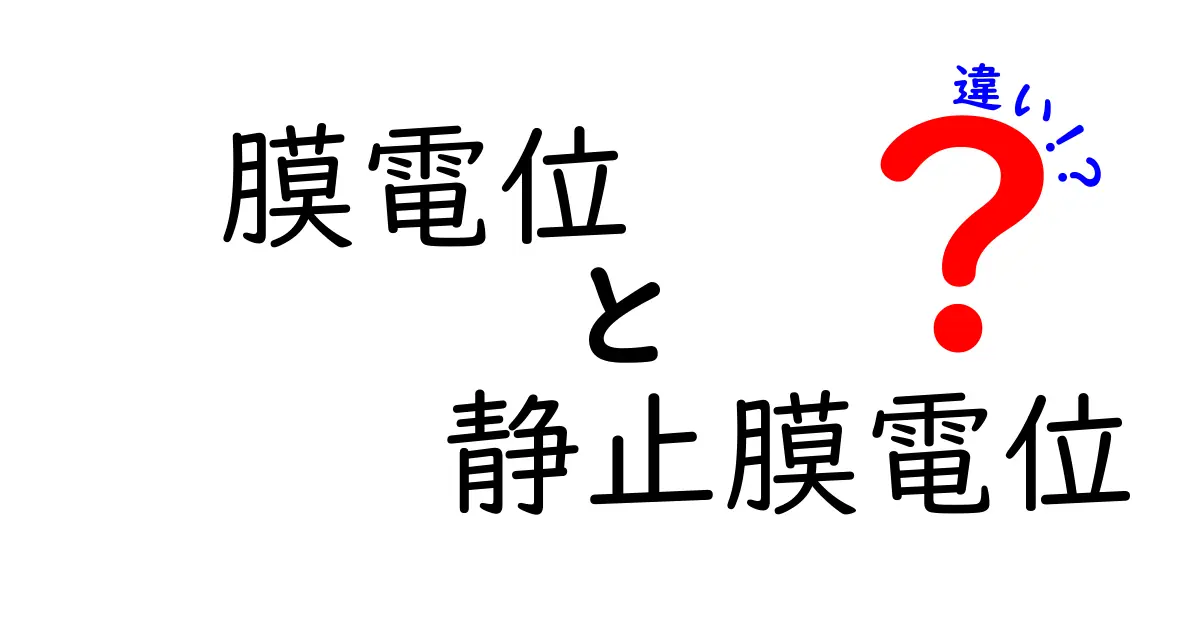

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
膜電位と静止膜電位の違いを知ろう
膜電位とは、細胞膜を境に内側と外側のイオンの濃度や透過性の違いから生まれる電気的な差のことです。イメージとしては、細胞の内側が外側に対して少しだけ「マイナスの電気」を持っている状態と考えるとわかりやすいです。大人の人でも、神経や筋肉はこの膜電位を使って情報をやり取りしています。例えば神経がメッセージを伝えるときには、この膜電位の変化が連続して伝わることで、私たちが物を感じたり、体を動かしたりします。膜電位は一定ではなく、時々変化します。周囲のイオンの動き、温度、浸透性の違い、そして細胞膜にある通り道の数と種類が関係します。
このように膜電位は「常にある状態の差」であり、個々の細胞で少しずつ違います。すべての細胞にとって必要な基礎の差であり、体全体の情報伝達の土台になるのです。
静止膜電位は、その膜電位の特定の状態を指します。すなわち、細胞が「静かにしているとき」または活動をしていないときの膜電位を指します。神経細胞では通常、静止膜電位はおおよそ-60ミリボルトから-90ミリボルト程度の範囲におさまります。どうしてそんな値になるのかというと、主に細胞膜を通るイオンの数と流れ方が決めているからです。細胞膜には多くのナトリウムチャネルは閉じ気味で、逆にカリウムチャネルがゆっくり開くため、内側が外側より少しだけ負になる状況が安定します。
さらに、内側には大きな陰イオンが留まっていることや、細胞内外の水分子の動きが関係します。静止膜電位は細胞の基本的な「電気のベースライン」と言えるでしょう。もし外部から刺激が来ても、このベースラインはすぐに崩れる可能性があり、次の反応へとつながります。
具体的な違いを整理して理解を深める
膜電位と静止膜電位の違いをまとめると、まず用語の範囲が違います。膜電位は「膜全体の電位差」という総称であり、細胞が活動しているときも含みます。静止膜電位はその中のある状態、つまり活動をしていないときの特定の基準値です。では実際の場面でどう使い分けるのかを考えてみましょう。
この2つを混同すると、実験ノートや授業のノートで混乱が生まれやすくなります。覚え方としては、膜電位=電位差の総称、静止膜電位=静かな状態の膜電位、と覚えると理解しやすいです。神経細胞の活動の準備段階や刺激が来たときの変化を理解するには、静止膜電位がベースとなり、その上に活動電位が重なるイメージが役に立ちます。
静止膜電位は、特定の安定状態の膜電位です。静かな状態の基準値として扱われ、値は細胞の種類によって異なります。神経細胞でよく出てくる-70mV前後は典型的な目安ですが、心筋細胞や他の細胞ではこれより低い、または高い値になることがあります。静止膜電位を理解することで、刺激が来たときに膜電位がどう変化していくか、つまり「どうして電気信号が発生するのか」が見えやすくなります。実際の教科書では、ナトリウムイオンとカリウムイオンの通り道の差が重要だと繰り返し説明されます。これらの道具がどのように開いたり閉じたりするかを考えると、膜電位のダイナミクスが体の中でどう動くかが感覚的につかめます。
ある日、私と友達のミカが学校の実験ノートで膜電位の話をしていた。教科書には膜電位と静止膜電位の違いが簡単に書かれているけれど、現場での理解はまだあいまいだった。私はノートに絵を描きながら、静止膜電位は“細胞が静かにしているときのベースライン”みたいなものだと説明した。膜電位はそのベースラインの上下で変化する幅全体を指すと伝えると、ミカは「じゃあ刺激が来たときにどう変わるのかが大事なんだね」と納得した。さらに、心筋細胞と神経細胞では静止膜電位の値が違うこと、イオンの通り道の数や開閉のタイミングが変化の鍵になることを一緒に整理した。私たちは実験ノートの中で、静止膜電位と膜電位の違いを自分の言葉で書く練習を続け、イオンの性質と膜の透過性が体の動きとどう結びつくのかを、身近な例とともに理解しようと話し合いを深めた。
この過程で、難しそうに見えた概念が、身の回りの体の動きとつながっていることに気づき、学ぶ楽しさを感じられるようになった。
次の記事: 大脳と大脳半球の違いを中学生にもわかる図解つきで徹底解説 »





















