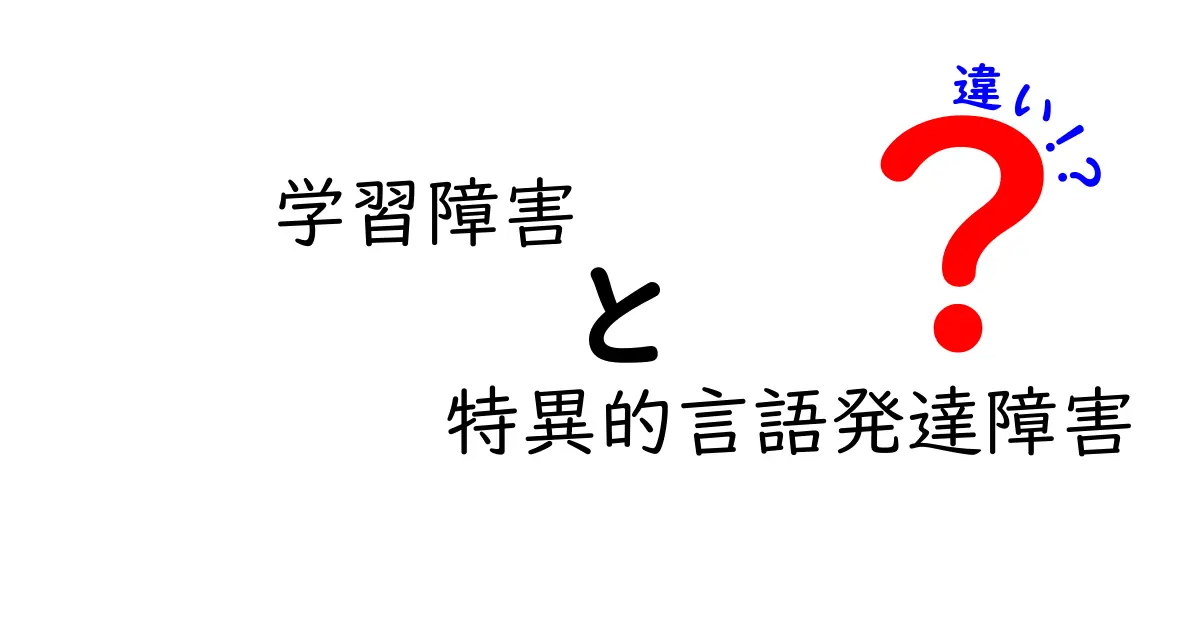

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
学習障害と特異的言語発達障害の違いを徹底解説—知っておきたい見分け方と支援のポイント
本記事は学習障害と特異的言語発達障害の違いを、中学生にも分かる視点で解説します。学習障害は教科の成績が思うように伸びない全体的な学習困難を指すことが多く、特異的言語発達障害は言語を使う場面でのみつまずくことが多い障害です。両者は似て見えることもありますが原因や現れ方が異なります。ここでは見分け方の基本と、学校や家庭でできる支援のポイントを具体的に整理します。読み書き算数の順序処理や記憶の使い方など、日常の学習場面でのヒントも紹介します。まずは定義の差を押さえましょう。定義の差を理解すると困っている子どもの力を正しく引き出す手伝いができます。読み書きに悩む子の姿を、ただ否定せず支える見方を一緒に学びましょう。
この理解を深めることで、学校の授業でのつまづきがなぜ起こるのかが見えやすくなります。
違いの基本ポイント
学習障害 LD は主に読み書き計算などの学習プロセスに関わる困難であることが多く、全体的な知的水準が高くても特定の領域だけ苦手という特徴があります。例えば読みやすさや文字の形の区別、書くときの字の乱れ、計算の順序だったりする課題が日常的に現れます。語彙や文法の基本力が必ずしも低いわけではないため、他の科目は比較的得意な場合もあります。診断には長い期間の観察と複数の検査が必要で、学習の遅れと知的能力の差を混同しないよう注意が必要です。支援には反復練習と多感覚的な指導を組み合わせ、授業の進度に合わせた個別計画を作ることが大切です。
特異的言語発達障害は通常、言語の理解や表現の壁が中心に現れ、語彙の理解不足、文の組み立ての難しさ、会話の相手の理解を難しくする要素などが目立ちます。知的機能は平均以上であることが多く、他の分野の学習は比較的正常に進む場合もあります。診断は言語聴覚士や教育心理士が関わり、標準化された言語検査と日常のコミュニケーション場面の観察を総合して行います。介入は言語療法、語彙の拡張、文法の練習、物語の理解と表現の練習などが中心です。
この違いを知ることは、子ども一人一人の支援計画を作るうえでとても大切です。
臨床実例と支援のヒント
現場では、学習障害を抱える子どもは教科の難しさだけでなく授業中の集中力の持続や宿題の負荷に影響を受けやすいことがあります。保護者や先生は、まず子どもの強みを探し、それを生かせる学習環境を整えることが大切です。読み書き難の子には視覚支援や音声読上げの活用、短い課題を小分けして達成感を積み重ねる、多感覚の学習法を取り入れると効果が高いことが多いです。言語発達の遅れが中心の子には日常会話の中で語彙を増やす機会を増やす、読み聞かせの時間を長くとる、物語の要点をつかむ練習を重ねるなどが有効です。家と学校が連携して、月ごとに小さな目標を設定することも励みになります。
この表を手がかりに、家庭と学校での具体的な支援を設計しましょう。なお、いずれの障害も個人差が大きく、早期発見と継続的な支援が大切です。
今日は特異的言語発達障害についての雑談をします。友だちAが言語のつまずきを経験していて、どうサポートしたらいいか迷っている場面を思い浮かべてください。Aは新しい単語を覚えるのが遅く、長い説明が苦手です。そこでBは、視覚的手がかりと音読を組み合わせて練習する方法を提案します。語彙の拡張には日常の会話で新しい表現を取り入れ、短い会話の練習を毎日取り入れることを勧めます。Aのことを否定せず、できたことを褒めて自信を少しずつ育てることが大切です。焦らず、失敗からも学べる体験を積むことが、言葉の力を取り戻す第一歩になります。訳がわからない時には周囲が丁寧に説明する温かさも大切です。





















