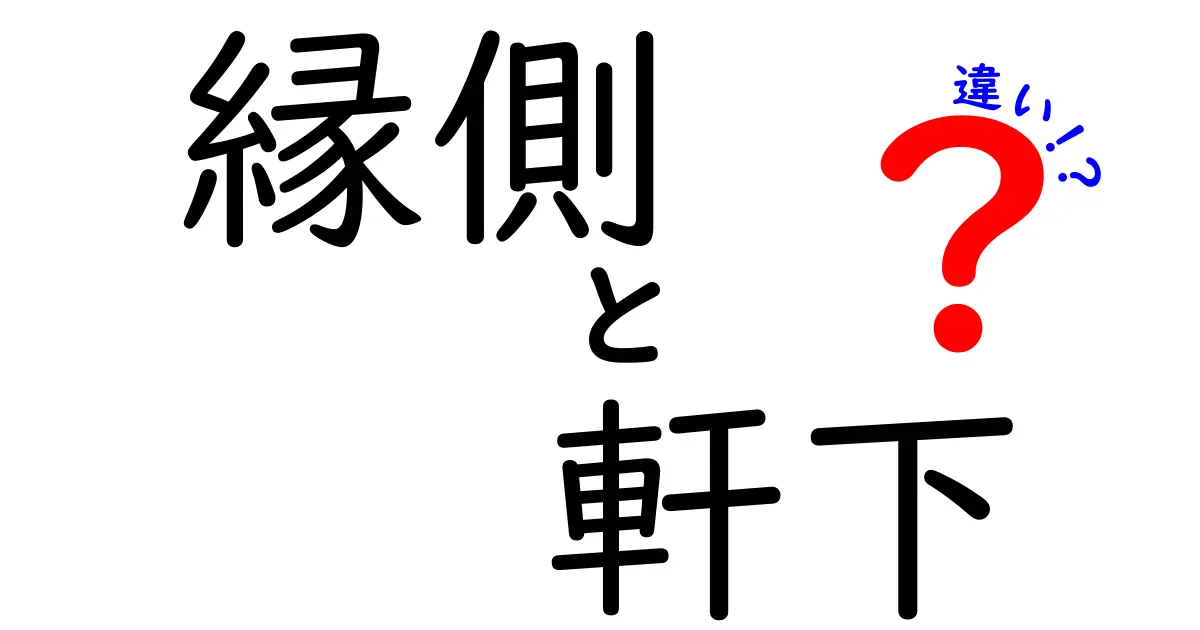

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
縁側と軒下の基本的な違いとは?
日本の伝統的な家屋でよく見かける「縁側」と「軒下」は、どちらも建物の外側にあり、日常生活や建物の構造に深く関わっています。しかし、意味や役割が異なるため、混同しやすい部分もあります。
縁側(えんがわ)とは、家の内外をつなぐ空間で、主に建物の室内側に面した外廊下のような場所を指します。縁側は、家の中の和室や居間のすぐ外に設けられ、普段は障子やふすまで仕切られています。
一方、軒下(のきした)は、建物の屋根や軒が張り出した部分の下にあたる場所を指し、雨や日差しを避けられる外側の空間です。軒下は必ずしも歩けるスペースではなく、建物全体の屋根の延長線上にある場所です。縁側とは違い、室内に直接接する部分ではありません。
縁側の特徴と使われ方
縁側は、伝統的な日本家屋の魅力的な部分で、室内と庭をつなぐ役割を果たします。木製の床で作られていることが多く、座ったり物を置いたりすることができるため、日向ぼっこやお茶を飲む場所として利用されました。
また、夏は風通しがよく涼しい場所であり、冬は障子やふすまを閉めて室内の暖かさを保つ役割も担います。家族がくつろぐ場所、来客をもてなす場としても使われ、地域の交流の場にもなっていました。
縁側は日本独特の空間であり、今では減少傾向にありますが、伝統的な住宅や古民家で見ることができます。
軒下の特徴と役割
軒下は建物の屋根が外側に伸びた部分の下で、雨や直射日光を避ける役割があります。軒は屋根の端にあるので、軒下は外壁を守ったり、建物周囲の通路としての機能も果たしています。
歩道のようなスペースとして使われることもありますが、縁側のようにくつろぐ場所ではありません。使われ方としては、洗濯物を干したり、自転車を置くなどの実用的な利用が多いです。
また、軒の長さによって軒下の広さも変わります。日本の建築様式で軒は重要な役割を持ち、建物の美観や構造の強化にも関わっています。
縁側と軒下の違いをまとめた表
| 項目 | 縁側 | 軒下 |
|---|---|---|
| 場所 | 室内の和室や居間の外側に接した廊下状の空間 | 建物の屋根・軒の下にある外部空間 |
| 主な役割 | 室内外のつながり、くつろぎの場 | 雨風や日差しを避ける、建物保護 |
| 構造 | 木製の床があることが多い | 屋根の張り出し部分の下で、床があるとは限らない |
| 使い方 | 座ったりお茶を飲むなど生活空間として利用 | 物置きや通路としての実用的利用 |
| 文化的意味 | 日本の伝統的空間で交流やくつろぎに活用 | 建物構造の一部で、防護や快適性向上を目的 |
縁側の魅力は、単なる通路ではなく、家族や友人とのコミュニケーションの場だったところにあります。昔の日本ではテレビもなかったので、縁側でおしゃべりをしたり、季節の移り変わりを感じたりして時間を過ごしました。また、縁側は庭と室内をつなぐ中間地帯であり、四季折々の景色を楽しめるのも魅力の一つです。現代の生活ではあまり見かけなくなりましたが、古民家を訪れるとほっとする空間として残っています。縁側には日本人の暮らしの知恵や心地よさがぎゅっと詰まっているんですね。
前の記事: « 茶器と茶碗の違いとは?初心者でもわかる簡単解説!





















