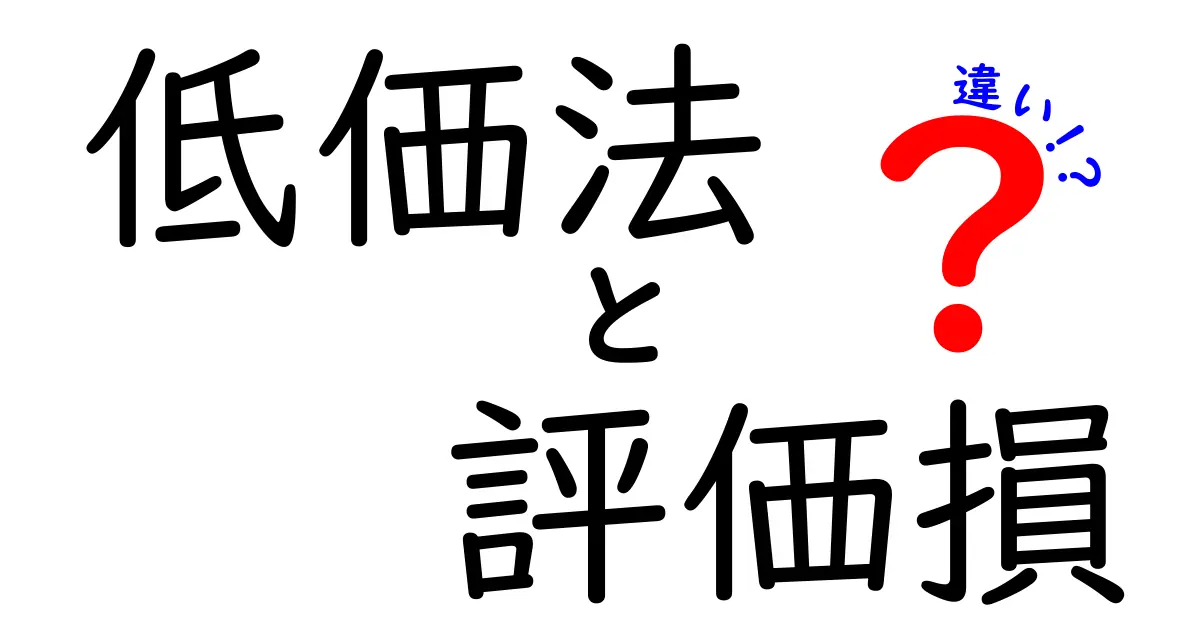

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
低価法と評価損、その違いを簡単解説
商売をしていると、商品や在庫の価値を見直す必要が出てきます。
そのときよく聞くのが「低価法」と「評価損」という言葉です。
どちらも商品の価値を減らして帳簿に記録することですが、実は意味や使い方が違います。
今回は中学生の方にもわかりやすいように、それぞれの内容と違いを解説します!
低価法とは?
まず低価法(ていかほう)とは、主に決算時に使う会計のルールです。
商売で持っている在庫(商品や材料など)の価値が市場価格より高くなっていた場合、その在庫の価値を低くして帳簿に記録し直します。
これをする目的は、在庫の実際の価値を正しく表すためです。
例えば、仕入れ値が1000円の品物があったとして、市場価格が800円に下がってしまったら、帳簿上は800円で評価し直す必要があります。これが低価法の考え方です。
低価法は在庫の価値を減らす根拠として用いられ、複数の在庫がある場合にはすべての在庫に適用します。
まとめると:
- 決算時に在庫の価値を見直す方法
- 帳簿価格(仕入原価)と時価のうち低い方に評価する
- 在庫全体の価値を正しくするためのルール
評価損とは?
次に評価損(ひょうかそん)とは、保有する資産や商品などの価値が下がってしまったことで発生する損失のことを指します。
これは単に「価値の下がった分のお金の損失」を意味していて、低価法の適用によって生まれる結果の一部です。
例えば、先ほどの例で市場価格が800円に下がった場合、仕入れ値1000円と比較して200円分の評価損が発生したといえます。
評価損は単独で適用されるのではなく、価値を下げる会計処理によってその差額が損失として計上されるイメージです。
まとめると:
- 資産や商品価値が下がったことで発生する損失
- 低価法を適用した際に生じることが多い
- 帳簿上の損失として記録される
低価法と評価損の違いを表で比較!
2つの違いをわかりやすくまとめた表はこちらです。
| ポイント | 低価法 | 評価損 |
|---|---|---|
| 意味 | 在庫価格を帳簿で見直す方法・ルール | 価値の下がったことによる損失金額 |
| 対象 | 在庫などの商品資産全体 | 価値の下がった差額 |
| 適用タイミング | 主に決算時 | 価値が下がったとき都度 |
| 主な目的 | 在庫を実態に合った価格に評価 | 価値減少分を正しく損失計上 |
| 会計処理 | 帳簿価額を低価格側に下げる | 損益計算書に損失を計上する |
まとめ
低価法は、決算時に会社の持つ在庫を本当の価値に直すための処理のことです。
一方、評価損は、その処理によって価値が下がった差額の損失を表しています。
つまり、低価法がルールや方法で、評価損はその方法を適用して出てくる結果の損失だと考えれば理解しやすいでしょう。
これを理解しておくことで、会社の財務状況や決算書の見方がわかりやすくなりますよ。ぜひ覚えておきましょう!
「低価法」と聞くと、ただ単に在庫の価値を下げる処理のように感じますよね。でも実は、これは簡単にいうと『在庫の値札を本当の価値に合わせてはりなおす』作業なんです。
値札の値段が実際の市場より高いままだと、会社の財務書類が正確でなくなってしまう。
そのため、低価法は企業の財務状況を正確に保つためにとても重要。
雑談ではありますが、将来ビジネスをする人にはこの『見た目の価格と実際の価値のズレを直す』考え方は必須の知識と言えますね!
次の記事: 有形固定資産と有形資産の違いとは?初心者でもわかるスッキリ解説! »





















