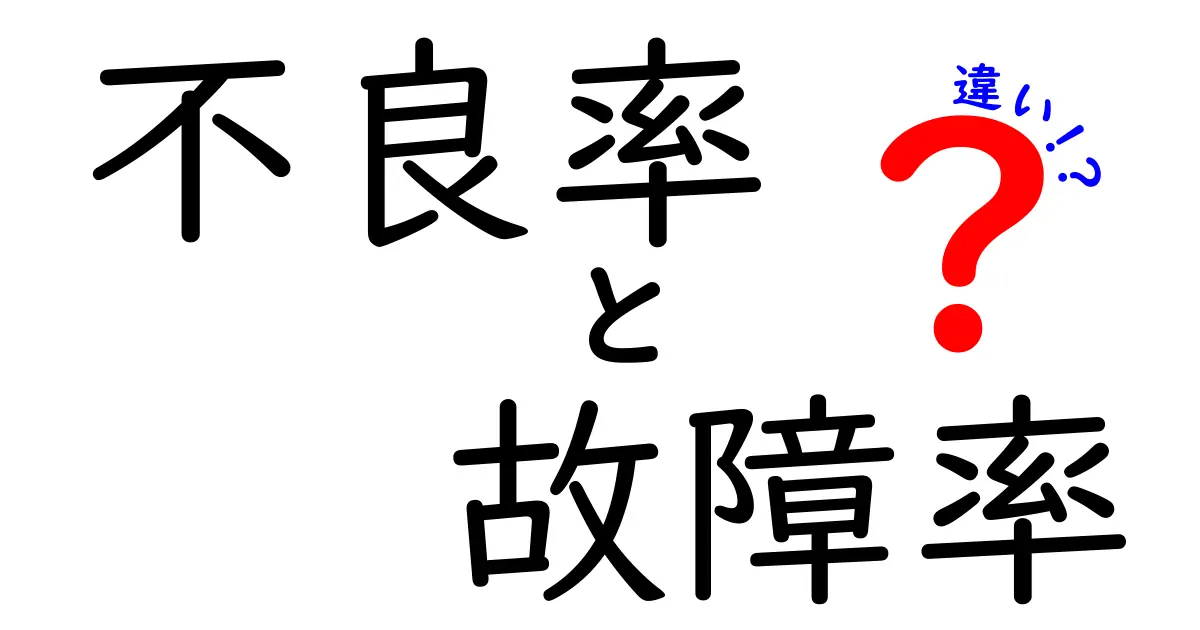

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
不良率と故障率の基本的な違いとは?
<製品の品質を評価するときにしばしば聞く言葉に「不良率」と「故障率」があります。どちらも製品の問題を示す数字ですが、
実は意味や使い方が異なります。
まず不良率とは、製造された製品のうちに基準を満たさずに合格とならなかった製品の割合を示します。
つまり、製造段階での品質チェックで問題が見つかった製品の割合です。
一方、故障率は、製品が実際に使われている期間中に故障や動作不良を起こす頻度のことを指します。
つまり、ユーザーが使用中にトラブルが発生する割合を表しています。
このように「不良率」は製造時の品質管理の指標で、「故障率」は使用時の信頼性や耐久性の指標と言えます。
不良品が出てしまうと、そもそも市場に出荷できないので会社にとっても大きな損失となります。
故障率が高いと、製品自体の信用が落ち、顧客満足度も低下します。
したがって両者は品質管理においてどちらも重要な指標なのです。
<
不良率と故障率の計算方法と使われる場面
<それぞれの数字の計算方法や使われる具体例を見ていきましょう。
【不良率の計算式】
不良率 = ( 不良品の数量 ÷ 製造品の総数量 ) × 100 (%)
例えば、1000個の製品を作って20個が基準を満たさず不良なら不良率は2%となります。
この値が低いほど製造の品質が高いと言えます。
次に【故障率の計算例】です。故障率は単純に個数だけでなく、使用時間や期間を加味して評価されることも多いです。
よく使われる指標にMTBF(平均故障間隔)やFIT値(故障率を10億時間あたりで表した値)などがあります。
例えば、100台の機械が1年間で5台故障した場合、故障率は5%となりますが、機械の使用条件や時間が異なるとその評価も変わります。
【使われる場面の違い】
不良率は主に製造工程の管理で使い、ライン改善や品質向上に役立てられます。
故障率は製品の耐久試験や市場導入後の品質監視で重視され、アフターサービスや保証期間の設計にも関係します。
つまり、不良率は事前のチェックで防ぐべき問題を示し、故障率は実際に顧客が経験するリスクを表す指標なのです。
<
不良率と故障率を比較した表とまとめ
<| 項目 | <不良率 | <故障率 | <
|---|---|---|
| 意味 | <製造工程での品質不良品の割合 | <使用中の製品の故障や不具合の割合 | <
| 計算基準 | <製品数量ベース | <使用台数+使用時間(MTBFなど) | <
| 目的 | <製造品質の改善と管理 | <製品の耐久性・信頼性評価 | <
| 使われる場面 | <製造ラインの検査 | <市場投入後の故障監視・保証設計 | <
| 評価対象 | <製品作りの不良 | <製品の使用中の障害 | <





















