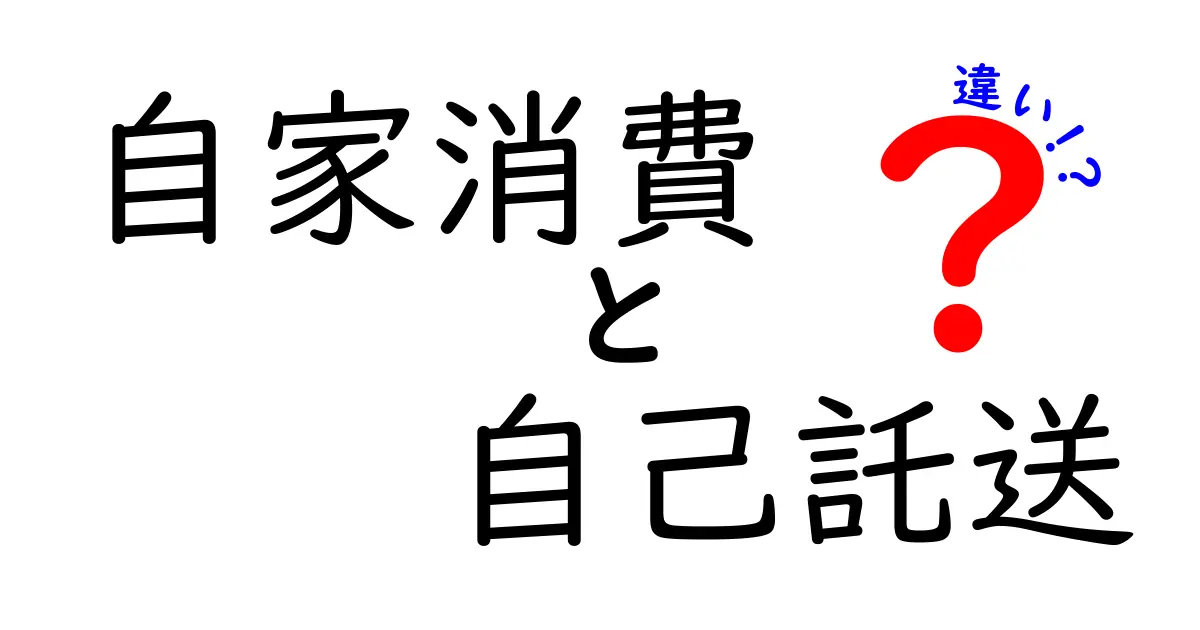

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
自家消費と自己託送の基本的な違いとは?
電気を使う際に、「自家消費」と「自己託送」という言葉を聞いたことはありますか?どちらも電気の使い方に関わる言葉ですが、実は意味も使い方も違います。
簡単に言うと、自家消費は発電した電気を自分の施設や家庭で直接使うこと、
自己託送は自分が発電した電気を別の場所に送って使うことを指します。
では、それぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。
自家消費とは?
「自家消費」とは、発電した電気を発電した場所や近くの施設で使うことです。
例えば、自宅に太陽光発電システムを設置し、その電気を家の中で使う場合が該当します。
この方法の大きな特徴は、発電した電気を電力会社の送電網を通さずに使うため、電気のロスが少なく経済的だという点です。
また、停電時でも自家消費用の設備があれば、電気を使い続けられることがあるため災害時にも安心です。
ただし、発電した電気を別の場所で使いたい場合には不向きです。自家消費は基本的にその場所限定での利用となります。
自己託送とは?
一方で「自己託送」は、発電した電気を自分の複数の施設や場所で使いたい時に利用される仕組みです。
例えば、ある工場で発電した電気を、別の工場や営業所に送りたい場合が自己託送にあたります。
この場合、送電線を利用して電気を届けるため、送電網の利用料金などがかかります。
自己託送は離れた場所で電気を使えるメリットがありますが、利用には規制や手続きが必要であり、一般家庭ではあまり利用されない方法です。
また、自己託送をする際は、使用する距離や量によって料金や設備も変わるので注意が必要です。
自家消費と自己託送の比較表
以上が、自家消費と自己託送の違いのポイントになります。
どちらも再生可能エネルギーの普及やエネルギー効率化で注目されていますが、上手に使い分けることが大切です。
今後、電気の使い方や発電の形も多様化していくため、基本用語や仕組みを正しく理解しておくことはとても重要です。
ぜひこの記事を参考に、自分に合った電気の利用方法を見つけてみてください。
自己託送についてちょっと面白い話です。実は自己託送の仕組みを使うことで、例えば都市の中心から離れた場所の工場に太陽光発電の電気を送ることができるんです。これって、見方を変えれば自分の電気を「遠くに住む自分の友だちに送る」ような感じで、電気の“郵便配達”のようなもの。しかも送るには特別なルールがあって、送電線の使用料を払ったり管理したりしなければならないため、まさに一種の『電力のリレー』なんです。こうやって電気はただのエネルギーから、複雑な社会インフラの重要な一部になっているんですね!
前の記事: « エネルギー使用量とエネルギー消費量の違いとは?わかりやすく解説!





















