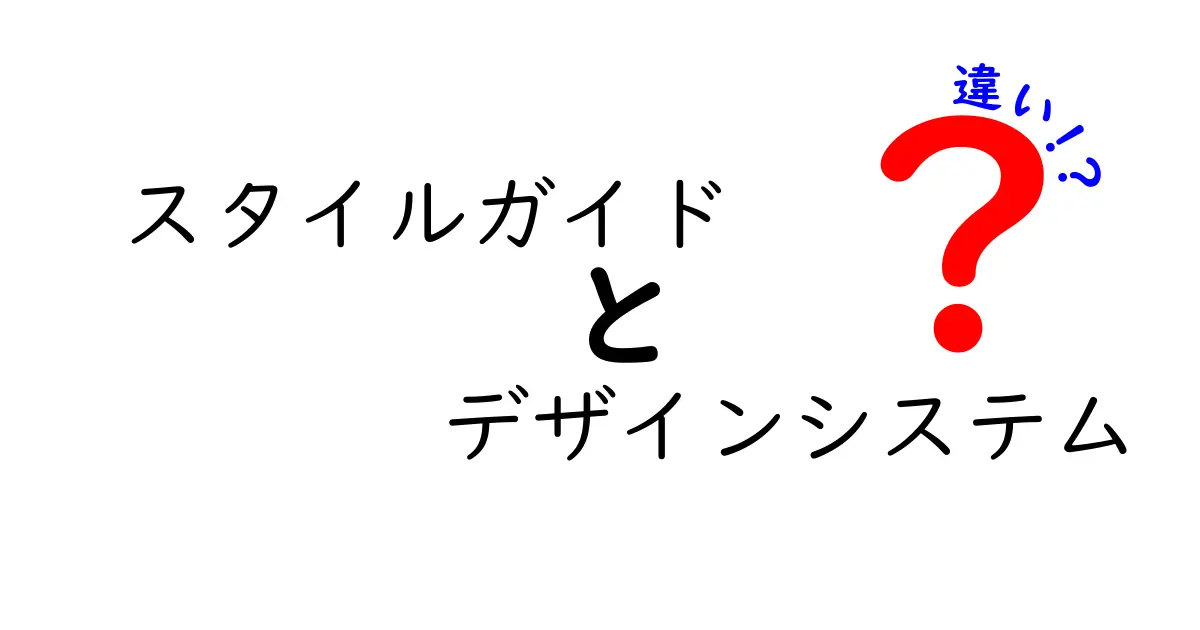

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
スタイルガイドとは何か?
スタイルガイドは、文字の大きさや色、フォント、ボタンの形、間隔など、デザインの基本ルールをまとめたものです。
これを守ることで、アプリやウェブサイトの見た目がバラバラにならず、統一感を保てます。
例えば、会社のロゴの使い方や、見出しの色を決めておくのもスタイルガイドの役割です。
中学生でもわかるように言うと、「デザインの取り扱い説明書」のようなものと考えてください。
これにより、デザイナーだけでなく、エンジニアや他のチームの人も同じルールで作業できるようになります。
スタイルガイドは主にビジュアルのルールを決めている点が特徴です。
しかし、それだけでなく、文章のトーンや写真の使い方なども含まれることがあります。
こうした統一感は、使う人にとって見やすくわかりやすいものになるため、とても重要です。
デザインシステムとは何か?
デザインシステムは、スタイルガイドのルールに加えて、実際に使えるパーツやコードをまとめたものです。
たとえば、ボタンやフォームのパーツを部品として用意し、それを何度も使えるように管理しています。
これにより、新しい画面を作るときも同じパーツを簡単に入れられて、ばらつきなく作業ができます。
デザインシステムは、スタイルガイドのルールに加え、具体的な設計やコードの仕組みも含むため、デザイナーだけでなくエンジニアも使いやすいように作られています。
つまり、デザインシステムはデザインの「教科書」から「工場のライン」へと進化したイメージです。
また、デザインシステムは継続的に更新されやすく、チームの成長に合わせて変えていける特徴があります。
こうした便利なしくみのおかげで、大規模なアプリやウェブサイトを効率よく作れます。
スタイルガイドとデザインシステムの主な違いを比較!
| 項目 | スタイルガイド | デザインシステム |
|---|---|---|
| 内容 | デザインのルールや色・フォントの指示 | ルールに加え、実際のUIパーツ・コードまで提供 |
| 目的 | 見た目の統一 | デザインの効率化と一貫性維持 |
| 利用者 | 主にデザイナーや編集者 | デザイナーとエンジニア両方が利用 |
| 更新頻度 | やや少なめ | チームの成長に合わせ頻繁に更新 |
| イメージ | デザインの取り扱い説明書 | デザインを作るための工場のライン |
デザインシステムの面白いところは、単なる見た目のルールだけじゃなく、プログラムとしての部品も含んでいることです。
だから、ボタンやフォームのパーツを使うたびに一から作らなくても済みます。
これって、中学生でいうと「レゴブロック」があらかじめたくさん用意されていて、そのパーツを組み合わせるだけでカッコいい作品を作れるような感覚ですね。
だから、大きなウェブサイトやアプリも効率的に作れるんです。
次の記事: 初心者必見!UIデザインとUXデザインの違いをやさしく解説 »





















