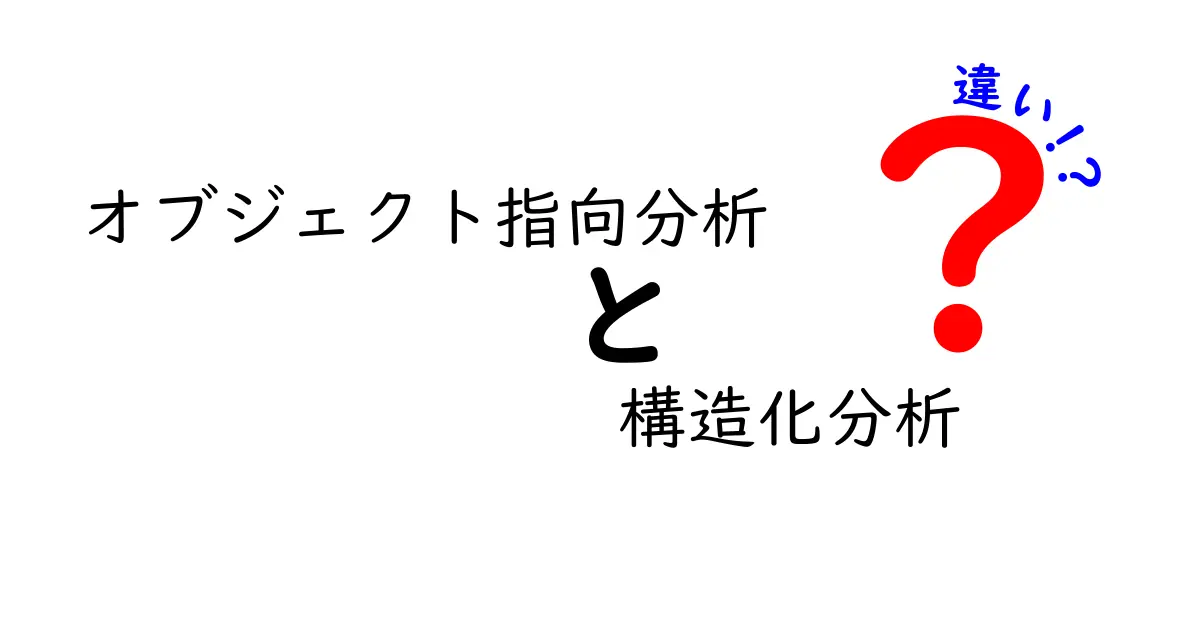

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
オブジェクト指向分析と構造化分析とは何か?
まず、オブジェクト指向分析と構造化分析について簡単に説明します。
オブジェクト指向分析は、ソフトウェア開発で使われる方法の一つで、プログラムの中の“モノ”や“こと”(これを「オブジェクト」と呼びます)に注目して作り方を考えます。例えば、車のソフトを作るとき、「車」自体をひとつのオブジェクトとして、その中に「タイヤ」や「エンジン」というオブジェクトを組み合わせて考えます。
一方、構造化分析は、問題を細かく分けて、それぞれを段階的に整理していく方法です。仕事の流れや手順を図で表し、どんな情報がどこで使われるかを分かりやすくするのが特徴です。
それぞれの方法が目指すものが違うので、使い方や考え方に違いがあります。次の章で詳しく解説しましょう。
オブジェクト指向分析と構造化分析の違いをポイントで解説
ここでは、オブジェクト指向分析と構造化分析の大きな違いを5つのポイントで説明します。
- 考え方の違い:オブジェクト指向分析は現実世界のものやことを「オブジェクト」として捉えますが、構造化分析は処理の流れや機能を細かく分けて整理します。
- 表現方法:オブジェクト指向はクラス図やオブジェクト図などを使い、構造化分析はデータフロー図(DFD)や状態遷移図などを使用します。
- 適用範囲:オブジェクト指向分析は再利用や変更を考えやすく、複雑なシステムに向いています。一方、構造化分析はシンプルな処理や業務の流れを整理するときに適しています。
- 開発の流れ:オブジェクト指向は設計やプログラミングまで見越した分析が多くありますが、構造化分析は問題の理解と整理に重点を置きます。
- 難しさと学習曲線:構造化分析は比較的学びやすいですが、オブジェクト指向分析は最初は難しく感じることが多いです。
これらの違いをまとめると、下の表のようになります。
| 比較項目 | オブジェクト指向分析 | 構造化分析 |
|---|---|---|
| 考え方 | 現実のモノやこと(オブジェクト)を中心に考える | 処理や機能の流れを分解・整理する |
| 表現方法 | クラス図、オブジェクト図など | データフロー図、状態遷移図など |
| 適用範囲 | 複雑なシステム、再利用しやすい設計 | シンプルな業務処理や処理手順の整理 |
| 開発の流れ | 設計やプログラミングまで見据える | 問題理解と機能整理を重視 |
| 学習難易度 | やや難しい | 比較的学びやすい |
オブジェクト指向分析の「オブジェクト」って何か、意外と身近です。例えば、あなたの身の回りにあるスマホや自転車も全部がオブジェクトになります。それぞれが持つ特徴(プロパティ)やできること(メソッド)を考えながらソフトを作ります。こう考えると、現実世界をそのままソフトに映しているんですね。これがあるから、オブジェクト指向は大きなシステムでも管理しやすいんです。
前の記事: « UMLとXMLの違いとは?初心者でもわかる基本ポイント徹底解説!





















