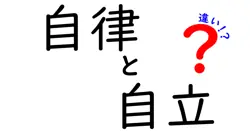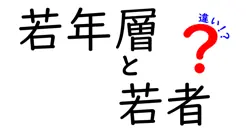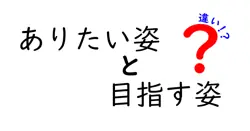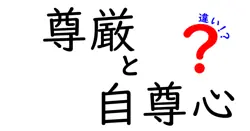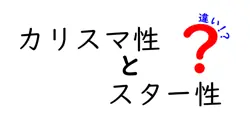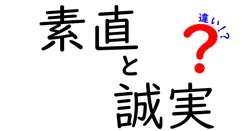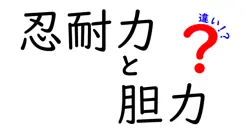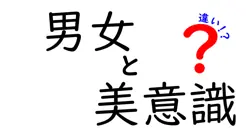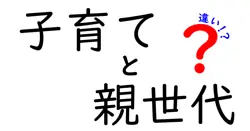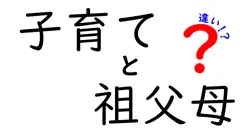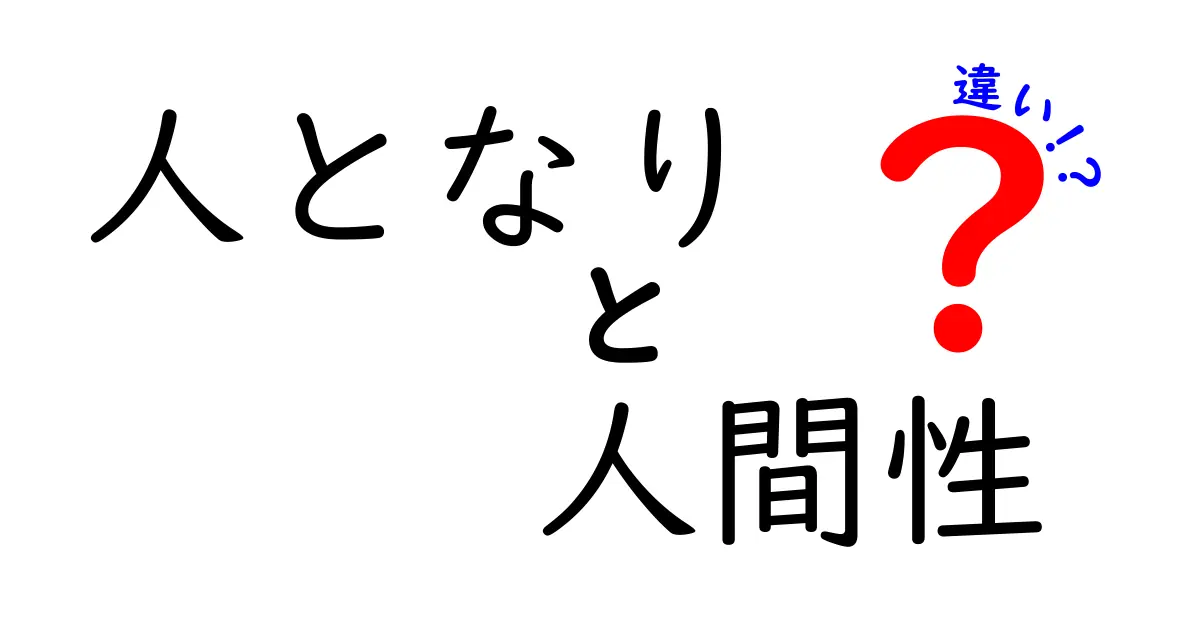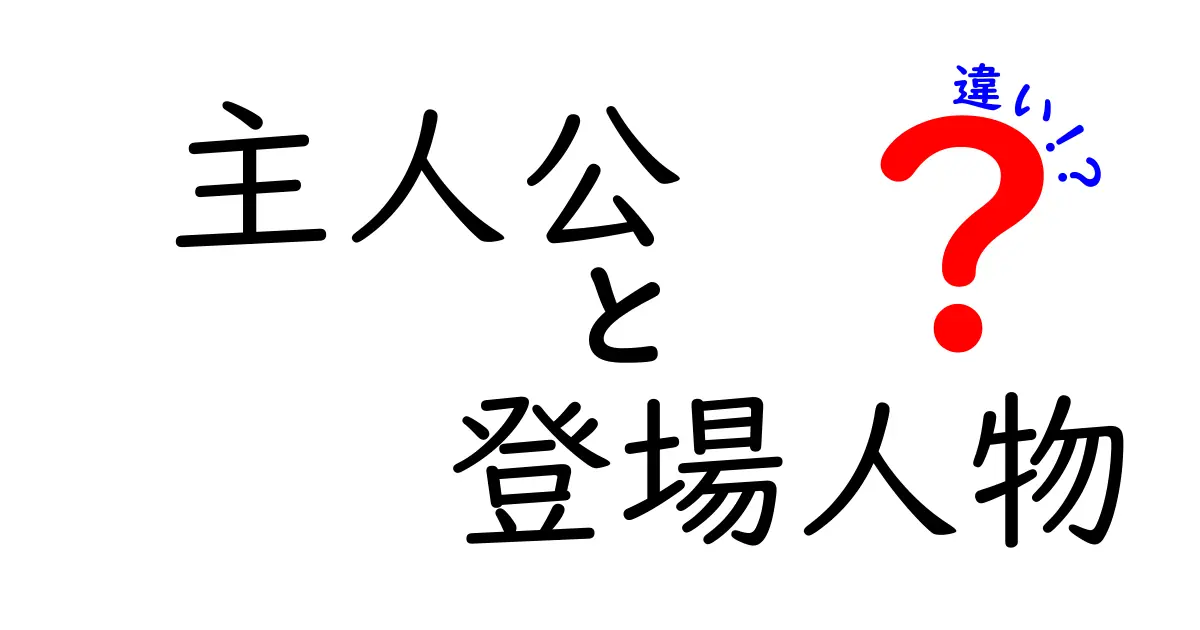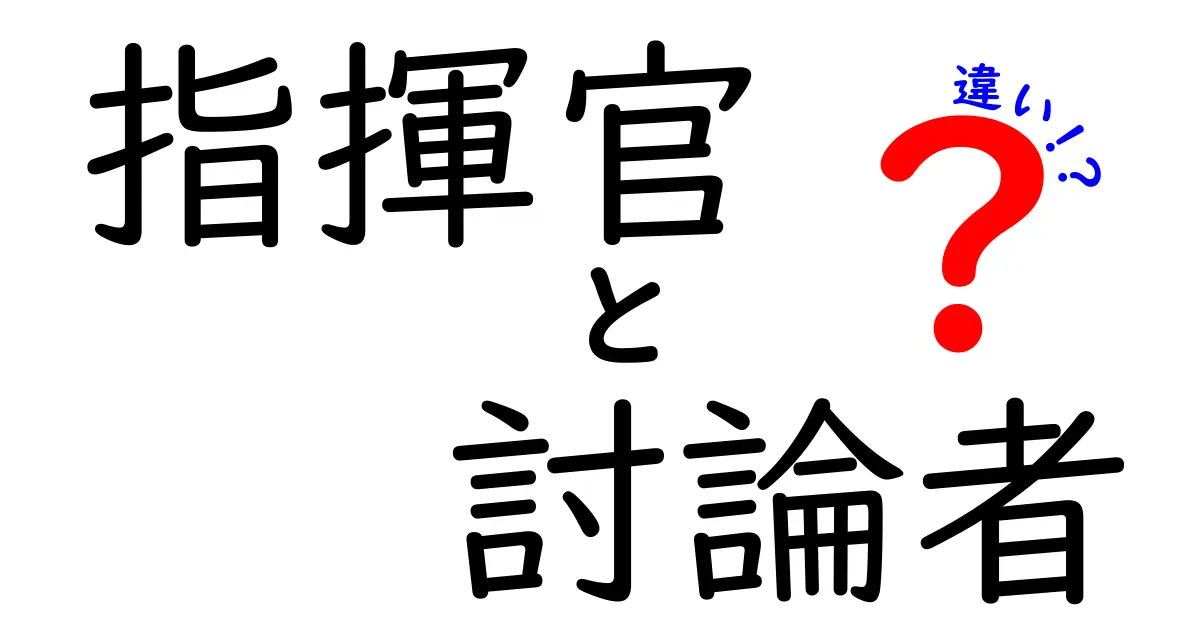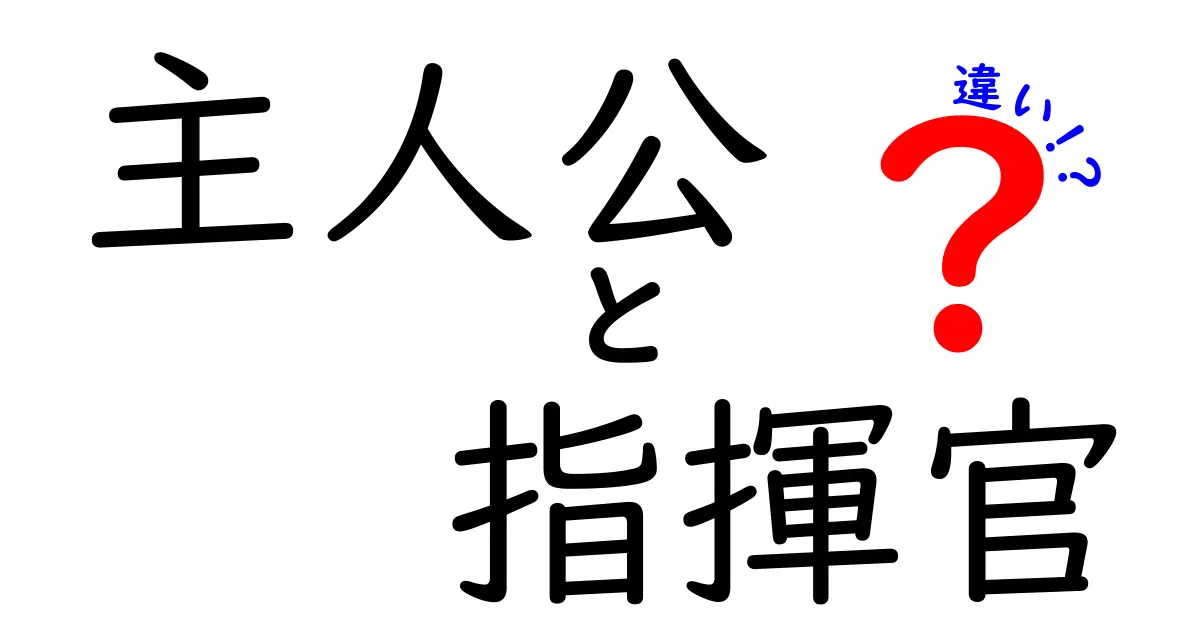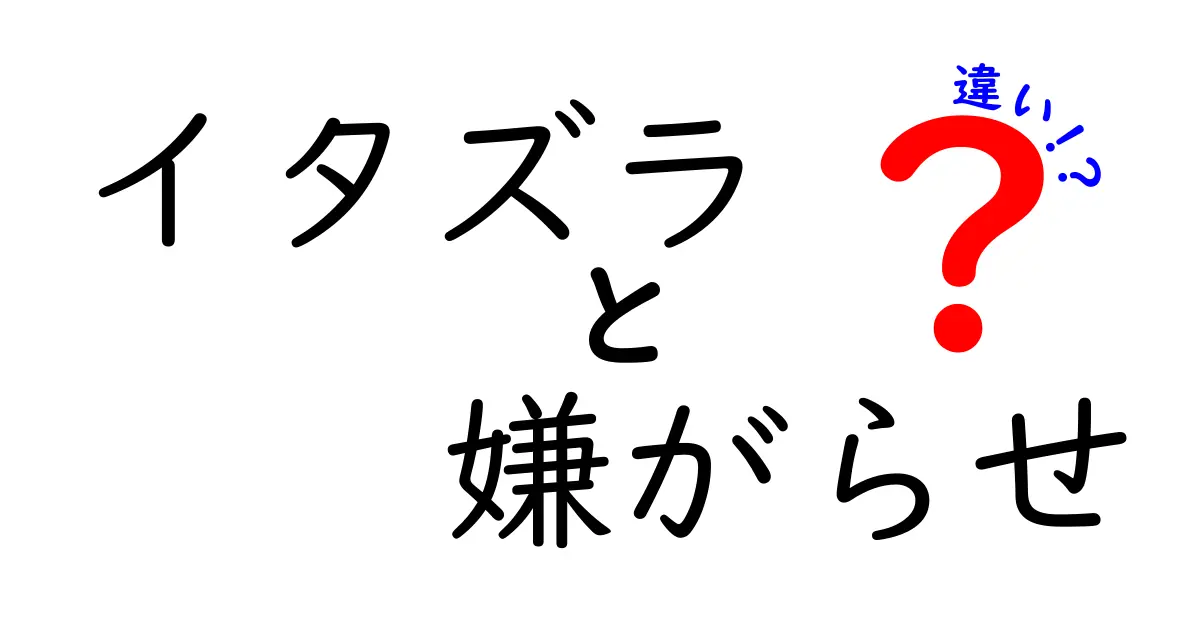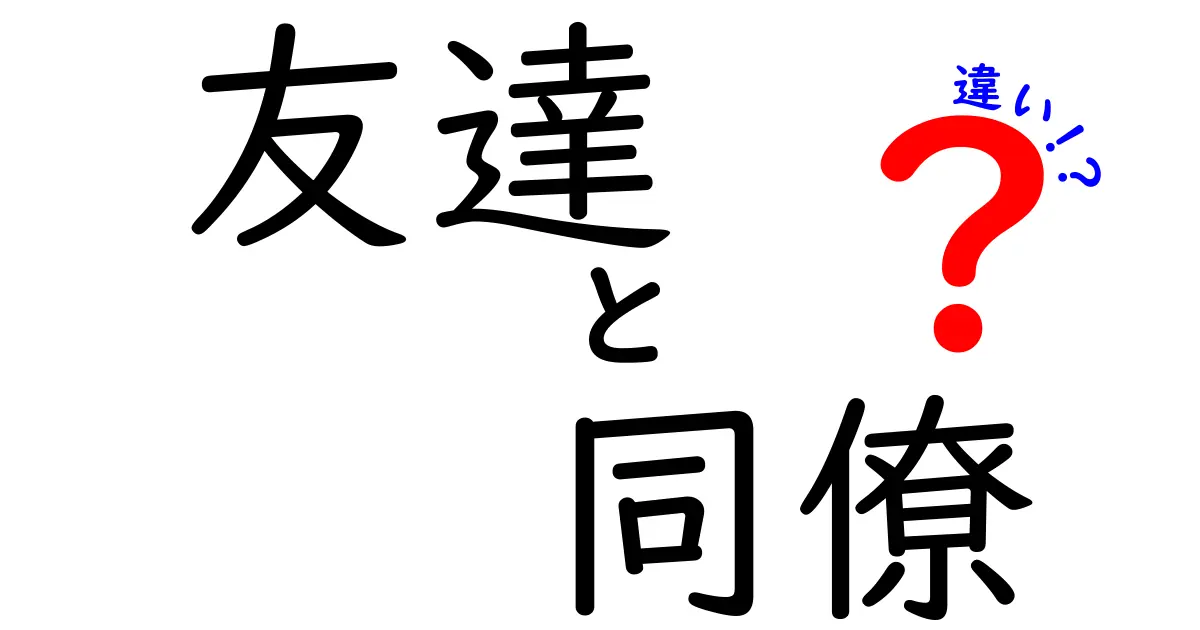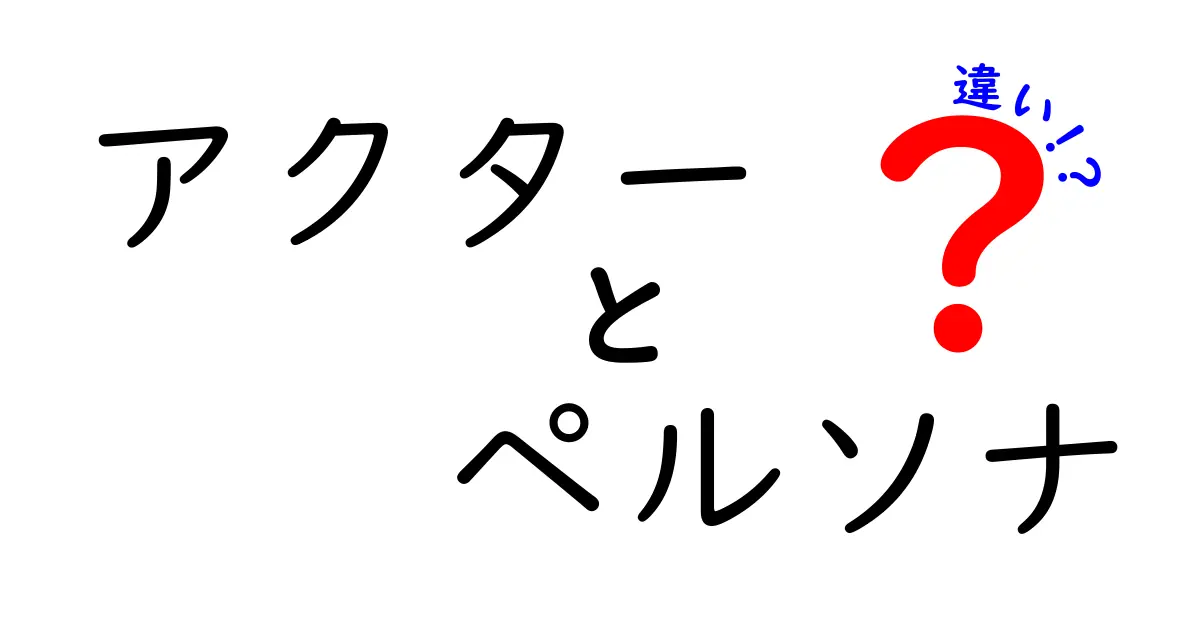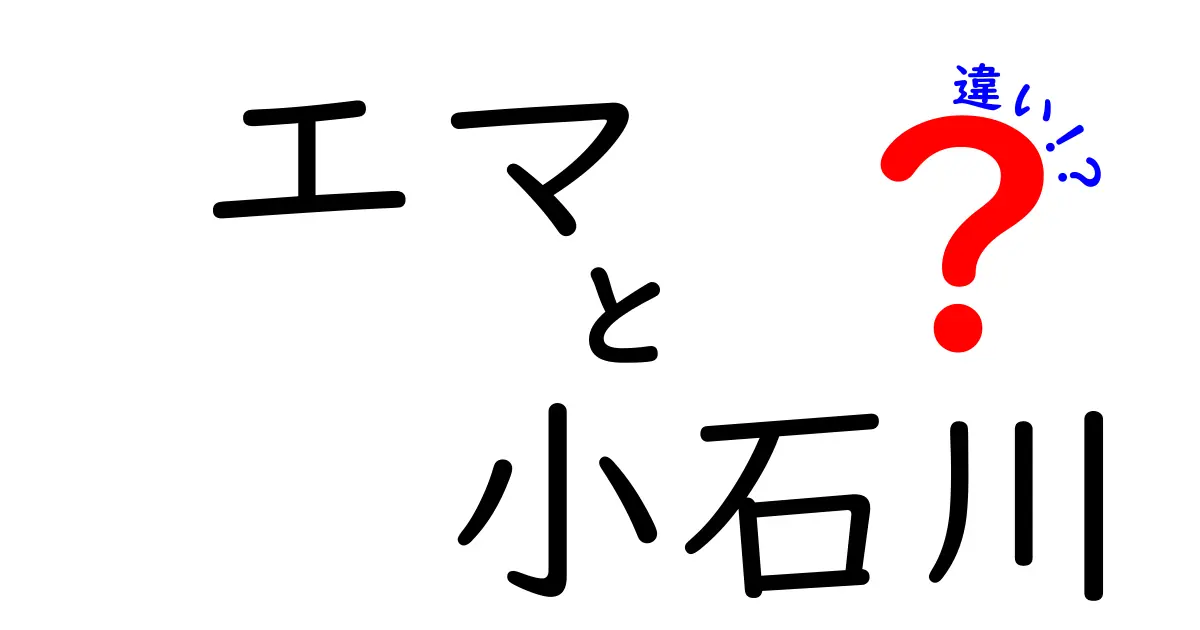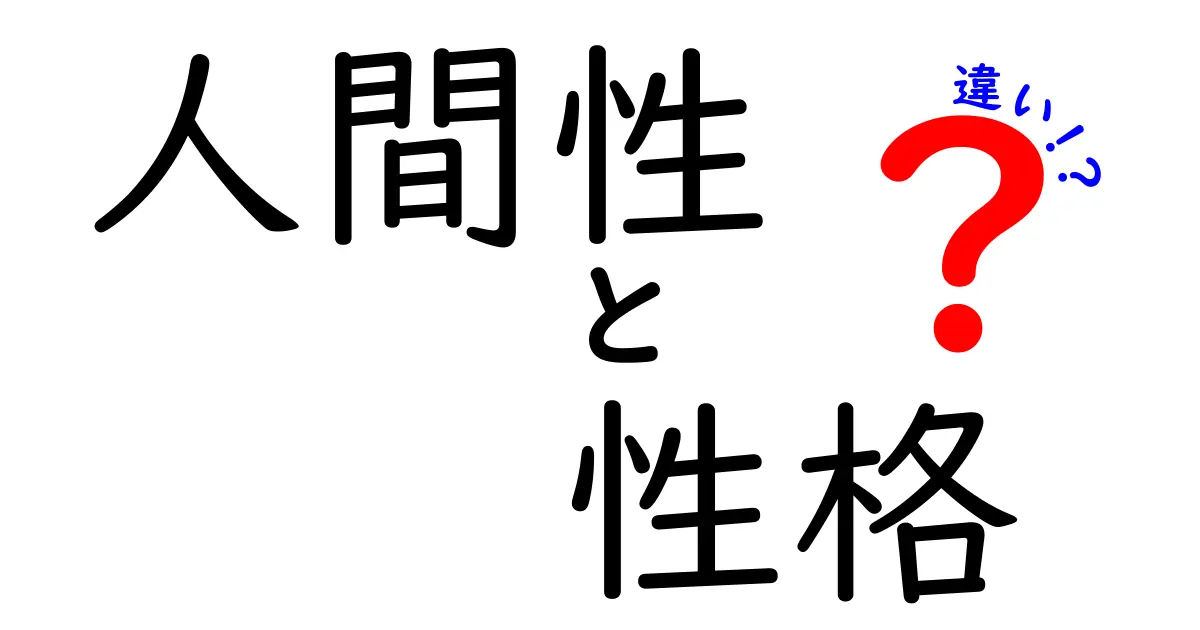

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
人間性と性格の違いを知るための基本
人間性と性格は似ている言葉ですが、指す範囲が異なるため混同されやすい概念です。人間性はその人の内面にある価値観や倫理観、他者へ向ける思いやりの基盤を指します。過去の経験や教育、文化的背景といった要因が絡み、長い時間をかけて形作られます。性格は日常の振る舞いの傾向であり、感情の出方、判断の仕方、他人との距離の取り方といった、実際の行動パターンを表す言葉です。人間性は外に見えづらい本質に近く、性格は観察しやすい表層の特徴です。この違いを理解すると、人間関係の誤解を減らせます。
もちろん、両方は切り離せず相互に影響しますが、変化の速度と性質には差があります。
形成の過程には遺伝的な要素と環境の組み合わせがあり、幼い頃の家庭、学校、友人関係、社会の期待などが影響します。人間性は倫理的な芯を育てる力であり、困難な状況でどう行動するかという“基準の高さ”を決めることがあります。性格は学習や習慣の積み重ねで変わりやすく、転職や引っ越し、災害体験といった大きな環境の変化にも影響を受けます。性格は修正可能性が高い面をもつ一方、人間性の深さは見直しにくいことがあります。
例えば、同じ人でも新しい学校に入ると最初は緊張しますが、時間が経つと周囲への配慮の仕方や助け合いの姿勢が変わります。そうした変化は性格の変化によるものが大きいですが、長い目で見ると人間性の影響が効いてくる場面が多いです。
見分け方と日常への影響
日常生活の場面でこの二つを見分けるコツは、長期的な観察と具体的な行動の結びつきを見ることです。人間性は時間をかけて現れる価値観の集まりとして、他者の困難に直面したときの反応や公正さの判断、謝罪や感謝の表現の仕方などに表れます。性格は場面ごとの反応や好み、言葉遣い、ストレス時の落ち着き方など、比較的短い期間で変動する特徴によって現れます。
よくある混乱の例として、明るく社交的な人が、実は深い思いやりを内側に秘めている場合があります。こうした人は表面的には性格の明るさで周囲を引きつけますが、困難な局面では倫理的な判断を優先することが多く、これが人間性の強さを示します。
| 項目 | 人間性の現れ方 | 性格の現れ方 |
| 反応の長さ | 時間を掛けて現れる | 場面ごとに変わりやすい |
| 主な影響 | 倫理観・共感・信頼 | 感情の起伏・癖・言葉遣い |
この理解は関係性を築くうえで役立つはずです。
ねえ、この記事の話を雑談風に深掘りするなら、私たちはしばしば“人間性が強い人ほど誠実に振る舞う”と語ることが多い。でも本当は違います。性格が穏やかでも、人間性が高い人なら危機のときに協力を引き出せるし、逆に性格は明るくても人間性が薄いと他人を傷つけることもある。そういう現場の感覚を友達と雑談するとき、私はこう結びます――人間性は地図、性格は歩く靴のようなものだと。
前の記事: « 人間性と感性の違いを徹底解説!あなたの判断が変わる3つのポイント