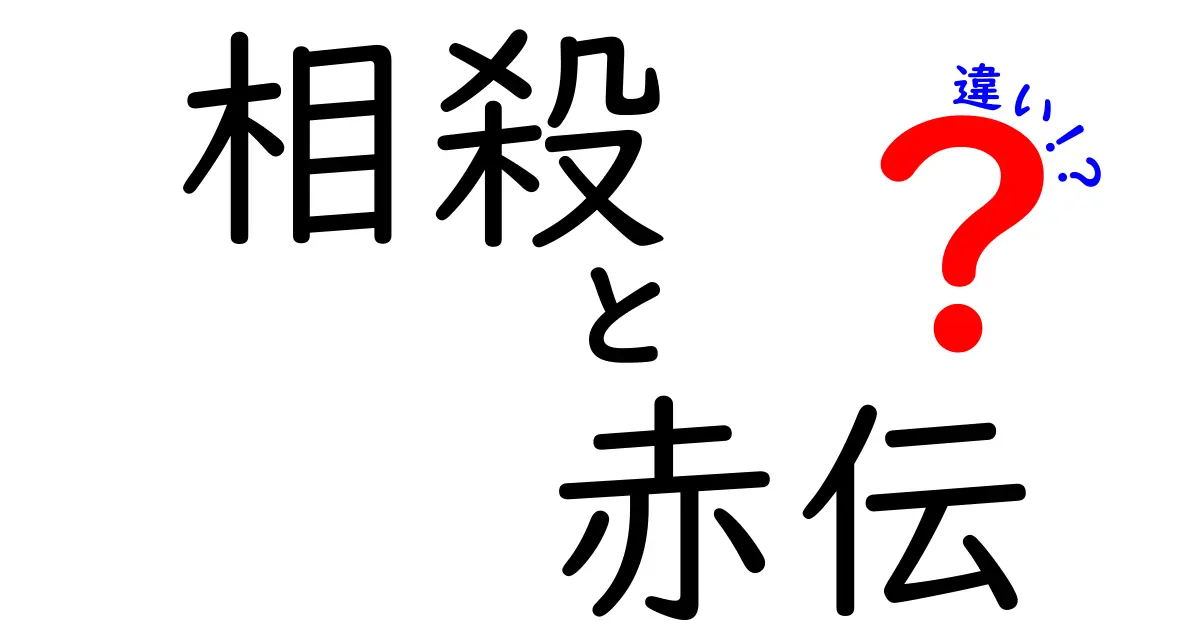

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
相殺と赤伝とは何か?基本の理解
会計や経理の現場でよく使われる言葉に「相殺」と「赤伝」があります。この二つは似ているようで、実際には用途や意味が違うんです。
まず相殺とは、二つの金額や債務・債権をお互いに引き算して、差し引きした残りの額で決済することを指します。例えば、A社がB社に10万円の借入があり、B社もA社に5万円の売掛金があれば、互いの金額を相殺して、残った5万円を支払うという仕組みです。
一方で赤伝(赤伝票)は、既に発行した請求書や伝票の内容に誤りがあった場合に、その誤りを訂正するために発行するマイナス(負の)伝票のことです。赤いインクで書かれることが多いため「赤伝」と呼ばれています。誤った金額や数量を訂正し、帳簿上の数字を正確に保つ役割があります。
相殺と赤伝の具体的な違いを徹底比較
では、この二つの違いを具体的に比べてみましょう。
| 項目 | 相殺 | 赤伝 |
|---|---|---|
| 意味 | 二つの債権債務を差し引きして決済 | 誤った伝票を訂正するマイナス伝票 |
| 目的 | 支払いや請求の金額を減らす | 売上や請求の誤りを修正する |
| 使用される場面 | 債権債務が重複する場合 | 請求や伝票の記入ミス発見時 |
| 会計処理 | 相殺仕訳を行い金額を整理する | 赤伝票によって帳簿を修正する |
| 具体例 | A社の借金と売掛金の相殺 | 数量間違いや請求額誤記の訂正 |
相殺は主に「請求」と「支払い」の両方に絡む金銭的な取引の調整に使う言葉で、赤伝は「伝票の誤り」を正しく帳簿に記録し直すためのものです。経理の立場では似ているようで異なる処理方法で、それぞれの役割を正しく理解して使い分けることが重要です。
経理業務での使い分け方と注意点
実際の経理業務では相殺と赤伝を誤って使うと、帳簿の数字に誤差が生じてしまいます。
たとえば、支払額と請求額を直接減らす必要がある場合は相殺の処理をして、正しく残高を把握します。
一方、伝票や請求書の記述ミスが分かった際には、誤った分のみを赤伝でマイナスとして入力し、正確な帳簿を作り直します。
相殺では二つの取引を一度に処理するのに対し、赤伝は一つの取引の誤りを修正するため別の伝票を使って処理するため、混同しないよう注意が必要です。
さらに、会計ルールの上でも両者は別物として扱われるため、税務申告などにも間違いがないかチェックしましょう。
経理担当者ならば、相殺は金額を合算または差し引きして決済の効率を上げる処理、赤伝は誤記を正確に直す訂正伝票と覚えておくのがポイントです。
「赤伝」という言葉の由来、実は赤インクで書かれた伝票だからというだけでなく、昔は誤りやマイナスを目立たせるために赤ペンで書く習慣がありました。
この方法は経理ミスを早く見つけられるという利点があります。つまり赤伝はミス防止の知恵の一つなのです。
現代では赤色でなくても赤伝票として扱われることがありますが、この歴史的な背景を知ると経理作業も少し楽しく感じられますよね。
次の記事: 保健指導と健康相談の違いとは?わかりやすく解説! »





















