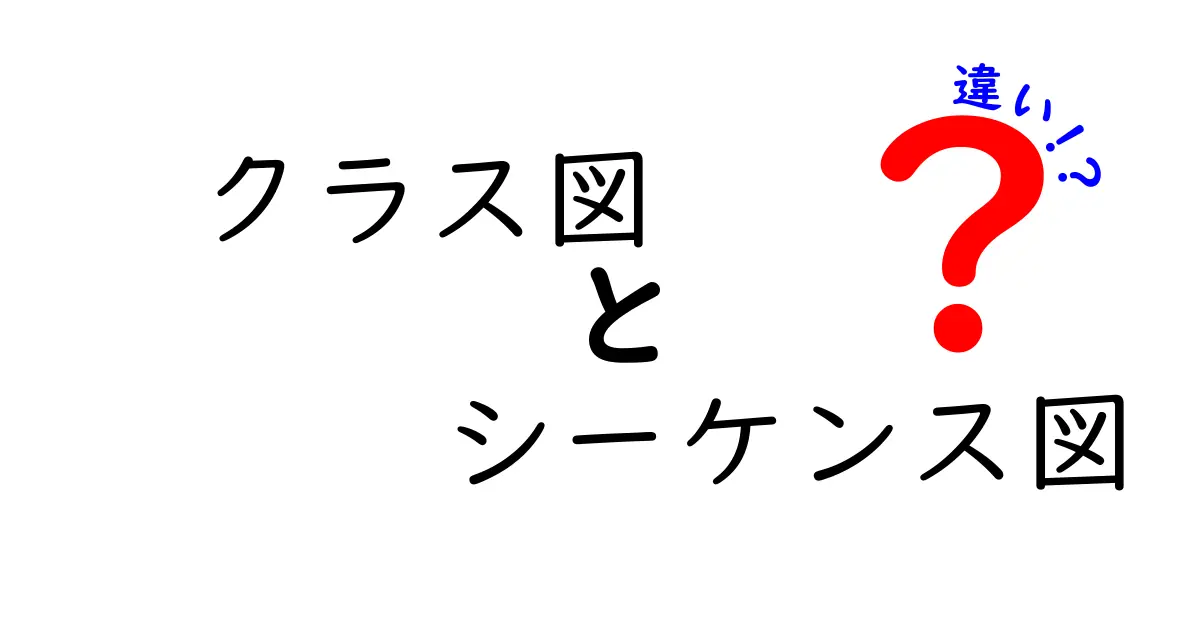

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
クラス図とは?基本を理解しよう
クラス図は、ソフトウェアやシステムの設計で使われる代表的な図の一つです。どんなものかというと、システムの中にある『クラス』という設計の単位と、それらの関係を表した図です。例えば学校のクラスでいうと、『生徒』や『先生』がクラスにあたりますが、プログラムの世界では『カメラ』や『ユーザー』などのものごとを表すのに使います。
クラス図は「どんなデータを持っているか」「どんな動作ができるか」を見るために使います。
具体的には、クラスの名前、持っている変数(属性)、できること(メソッドや操作)、そして他のクラスとの関係(継承や関連など)を図に描きます。
この図を見るだけで、システムの構造や構成をイメージしやすくなるのが特徴です。
例えば、図に「ユーザー」「商品」「注文」というクラスがあれば、これらがどうつながっているのかがわかり、システムの骨組みを理解できます。
これにより開発者同士の共通認識が生まれ、効率よくプログラムが作れるのです。
まとめると、クラス図はモノ(クラス)の構造や関係を表した設計図のようなもので、プログラムの元になる設計の基礎となります。
シーケンス図とは?動きを追いかけよう
一方、シーケンス図はクラス図とは違って、システムの中の動きや流れを表す図です。「いつ」「どのクラスが」「どんな順番で」「どのようにメッセージをやり取りしているか」を示します。例えば、あなたが友だちにメッセージを送るとき、どんな順番で送って受け取るのか、ということを絵にしたものと思ってください。
シーケンス図では、縦方向に時間が流れ、横方向にクラス(またはオブジェクト)が並びます。
矢印でメッセージのやり取りを示し、順番やタイミングを分かりやすく表現します。
これにより、システムの動作イメージや処理の流れをつかむことができます。
例えば、オンラインショップで「ユーザー」が「商品」を注文する流れをシーケンス図で表すと、まずユーザーが注文情報を入力し、その情報がシステムに伝わり、注文の確認や決済処理が順に行われる様子が図になります。
つまり、シーケンス図は時間の流れに沿った操作やメッセージのやり取りを示すことで、システムの動作を理解しやすくする図です。
クラス図とシーケンス図の違いを表でわかりやすく比較
ここで、クラス図とシーケンス図の違いを分かりやすくまとめた表を見てみましょう。
| 特徴 | クラス図 | シーケンス図 |
|---|---|---|
| 目的 | システムの構造やクラス間の関係を表す | システムの動作や処理の流れを表す |
| 表す内容 | クラス名・属性・操作、クラス間の関連 | オブジェクト間のメッセージや操作の順序 |
| 時間軸の有無 | 時間軸なし(静的構造) | 時間軸あり(動的な流れ) |
| 使用シーン | システムやソフト全体の設計 | 具体的な機能の動作や処理の流れの説明 |
| 図の見た目 | 四角で構成された、箱のような図 | 縦に時間が流れ、矢印で通信を示す |
このように、クラス図はシステムのパーツと関係を整理し、シーケンス図はそのパーツが時間の中でどう動くかを示すものと覚えておくとよいでしょう。
シーケンス図でよく使われる「メッセージのやり取り」は、ただの命令だけでなく「問い合わせ」や「返事」も表現できるんです。だから、プログラムのやりとりをまるで会話のように見えるのが面白いところ。
中学生のみなさんが友達と話す順番やタイミングを図に描くイメージで、シーケンス図を見るととてもわかりやすいですよ。
これによって、どのタイミングで何が起こるかをプログラムを書く前に確認できるので、開発ミスも減らせるんです。
次の記事: 基本設計と方式設計の違いとは?初心者でもわかるシンプル解説 »





















