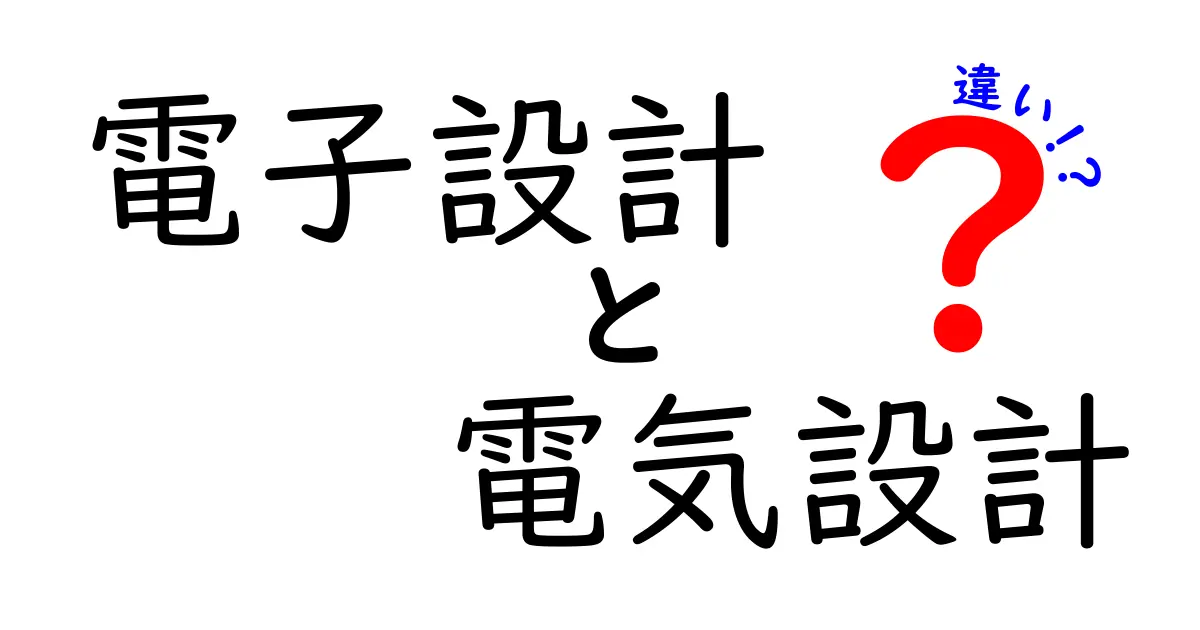

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
電子設計と電気設計とは何か?基本を押さえよう
電子設計と電気設計は、似ているようで実は役割や内容が異なる技術分野です。
まず電子設計は、電子回路や半導体を中心に扱い、小さな部品を使って信号処理や制御を行う設計を指します。コンピューターの基板やスマートフォンの回路設計などがこれにあたります。
一方、電気設計は、主に電力を扱う設計で、発電所や電気設備、配線など大きな電気システムの構築に関わります。電力を安全に届けたり使うための計画や設計を担当します。
つまり、電子設計は電子信号の操作や制御に焦点をあて、電気設計は電力の供給や配線管理などが主なテーマです。これにより、扱う規模や対象が大きく異なることを理解しましょう。
電子設計と電気設計の具体的な違いを表で比較
それぞれの違いを整理するとわかりやすいので、以下の表でまとめました。
| 項目 | 電子設計 | 電気設計 |
|---|---|---|
| 対象 | 電子回路、半導体、基板 | 発電設備、配電盤、電力システム |
| 扱う信号 | 微弱な電子信号(マイクロ〜ミリアンペア) | 大電流・高電圧の電力(アンペア数千〜数万) |
| 設計目的 | 情報処理や制御 | 電力の供給と安全管理 |
| 主な部品 | トランジスタ、IC、コンデンサ | トランス、開閉器、配線 |
| 使用分野 | スマホ、PC、自動車の電子機器 | ビル管理、発電所、電力インフラ |
これを参考にすると、電子設計は細かな電子部品を扱い情報の制御をするのに対し、電気設計は大きな電力を扱い安全に送るための計画をはじめとした設計だとわかります。
双方とも電気の知識は必要ですが、設計の軸や使う規模が根本的に違うのです。
それぞれの仕事の内容と資格・スキルについて
電子設計の仕事は、電子回路の回路図作成、プリント基板の設計、ソフトウェアとハードウェアの連携設計などが中心です。
一方で電気設計は、電力設備の設計、配電盤のレイアウト作成、電気安全法令の遵守確認など、現場での電力流れと安全確保が重要になります。
資格も違いがあり、電子設計では「電子回路設計技術者」やソフトウェア関連の資格が役立ちます。
電気設計では「電気工事士」や「第1種電気主任技術者」などの資格が要求されることが多いです。
またスキル面では、電子設計は回路設計ソフトの扱いや細かな信号解析が必要で、電気設計は配電設計の知識や電力設備の施工管理に精通していることが求められます。
どちらも専門知識の深さや設計ソフトの使い方、安全基準の理解など独自のスキルが欠かせません。
電子設計でよく使われる『トランジスタ』は、小さなスイッチのような役割を持ちます。実はトランジスタのおかげで、スマホやパソコンの中で信号を増幅したり切り替えたりできるんです。電子設計はこうした部品を組み合わせて情報をコントロールするので、まるで小さな電子の魔法使いのような仕事なんですよ。トランジスタの発明は現代のデジタル技術の基盤とも言える、非常に重要なポイントなんです。
次の記事: グランドとコモンの違いを徹底解説!中学生でもわかるポイントまとめ »





















