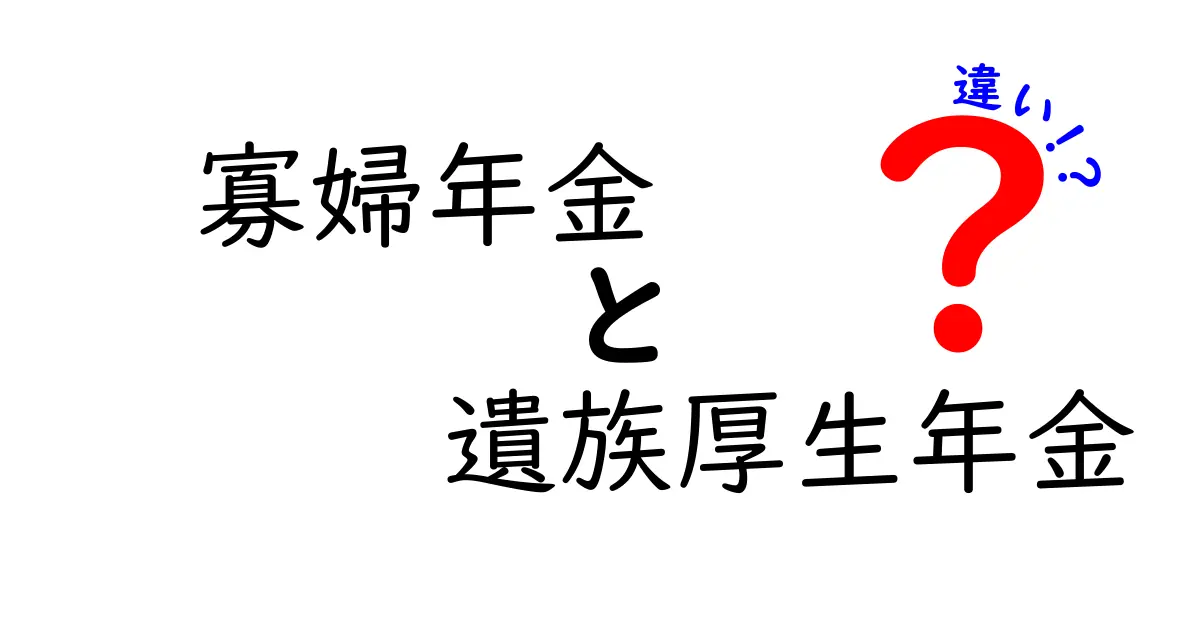

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
寡婦年金と遺族厚生年金とは?基本の違いを押さえよう
年金制度には、さまざまな種類がありますが、特に遺族に関わる年金として「寡婦年金」と「遺族厚生年金」があります。
寡婦年金は、夫が国民年金に加入していた期間中に死亡した場合に、一定条件のもとで妻が受け取ることができる年金です。
一方、遺族厚生年金は、夫(または妻)が厚生年金に加入していた期間中に死亡した場合に、その遺族が受け取る年金を指します。
つまり、どちらも遺族に支給される年金ですが、夫の年金加入状況や保険種類で受け取れる年金が異なるのが大きな違いです。
また、受給資格、受給額、受給期間も異なるため、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。
寡婦年金と遺族厚生年金の受給資格と条件の違い
まず寡婦年金は、夫が国民年金(厚生年金の基礎部分)に加入していた期間が25年以上あり、夫の死亡時に妻が40歳以上65歳未満であることが基本条件です。
さらに、妻が離婚していないことや、他の公的年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)を受給していないことも条件に含まれます。
一方で、遺族厚生年金は、亡くなった人が厚生年金に加入していた場合に支給されます。対象は配偶者のほか、子供、父母なども対象となる場合があります。
受給資格としては、亡くなった人が厚生年金への加入期間や保険料納付状況などが関係し、遺族の関係性や年齢によって受給できる金額が変わります。
特に、子どもがいる場合は遺族厚生年金が優先されることが多く、また、寡婦年金は遺族厚生年金と併給できないルールも存在します。
寡婦年金と遺族厚生年金の受給額や期間の違い
受給額については、寡婦年金は夫の国民年金の基礎年金部分の3分の2程度が支給されることが多いです。
これに対し、遺族厚生年金は、夫が生前に支払っていた厚生年金の報酬比例部分に基づいて計算されるため、金額は個人の報酬や加入期間によって大きく異なります。
また受給期間も違いがあり、寡婦年金は40歳から65歳までの期間限定で支給されるのに対し、遺族厚生年金は子供がいる場合は子供が18歳に達するまでなど一定条件で長期間支給されることがあります。
さらに、遺族厚生年金は障害者やその他特段の条件がある場合、さらに長く受給が可能な場合もあります。
寡婦年金と遺族厚生年金の違いを表で比較
| 項目 | 寡婦年金 | 遺族厚生年金 |
|---|---|---|
| 対象者 | 夫が国民年金加入中に死亡した妻(40~65歳) | 夫(または妻)が厚生年金加入中に死亡した遺族(配偶者、子など) |
| 受給資格 | 夫の国民年金加入期間25年以上 妻が他の遺族年金未受給 | 夫の厚生年金加入期間・納付状況 遺族の関係性や年齢による |
| 受給額 | 国民年金基礎部分の約3分の2 | 報酬比例部分に基づく 金額は個人差あり |
| 受給期間 | 40歳~65歳まで(期間限定) | 子が18歳になるまでなど 条件により長期支給 |
| 併給 | 遺族厚生年金との併給不可 | 他の遺族年金との組み合わせも可能な場合あり |





















