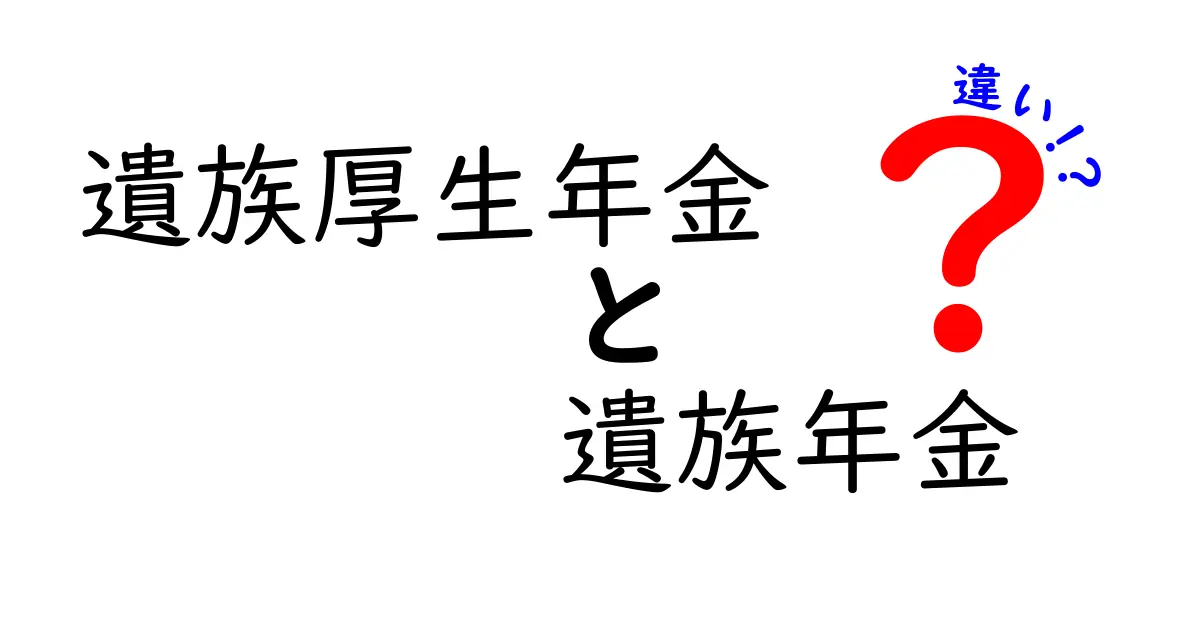

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
遺族厚生年金と遺族年金とは何か?基本の違いを押さえよう
みなさんは遺族厚生年金と遺族年金という言葉を聞いたことがありますか?似た名前なので混乱しやすいですが、これらは日本の年金制度の中でとても大切な役割をもっています。
まず遺族年金とは、亡くなった方の遺族が生活の助けとして受け取る年金の総称です。その中の一つに遺族厚生年金があります。
簡単にいうと、遺族年金は全体のしくみの名前であり、その中に「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」などの種類がある、というイメージです。
遺族基礎年金は主に国民年金に加入している人の遺族に支払われ、一方で遺族厚生年金は厚生年金に加入していた人の遺族に支払われます。これが基本的な違いとなります。
遺族厚生年金と遺族基礎年金の支給対象や金額の違い
それでは、より詳しく遺族厚生年金と遺族基礎年金の違いを見ていきましょう。
支給対象では、遺族基礎年金は主に子どもがいる遺族(主に配偶者と子ども)に支給されます。
一方、遺族厚生年金は働いていた亡くなった方の配偶者や子ども、(場合によっては両親)に支給され、対象がより広いです。
金額については、遺族厚生年金の方が一般的に多く支給される傾向があります。なぜなら支給額は亡くなった方の厚生年金加入期間の報酬額に影響されるため、働いていた人の収入に応じて計算されるのです。
遺族基礎年金は標準的な定額+子どもの人数に応じた加算が基本です。
以下の表にまとめてみました。年金の種類 加入対象 支給対象 支給額の目安 遺族基礎年金 国民年金の被保険者 子どもがいる配偶者または子ども 定額+子ども加算 遺族厚生年金 厚生年金の被保険者 配偶者、子ども、または両親(条件による) 報酬比例+遺族基礎年金が合わさる場合も
遺族厚生年金と遺族年金の受給手続きや注意点
遺族年金は多くの人の生活支援となる大切な年金ですが、受け取るためには手続きをしなければなりません。
まず死亡届を市区町村役場に提出した後、年金事務所に必要な書類を持って遺族年金の申請を行います。
遺族厚生年金の場合は、被保険者である亡くなった方が厚生年金に加入していたことが条件になります。加入期間や納付状況で受給できるかが決まるため、注意が必要です。
また遺族基礎年金の場合は子どもの年齢(18歳まで・障害がある場合は20歳まで)が条件で、配偶者の再婚をした場合は支給が停止されることも覚えておきましょう。
このように遺族厚生年金と遺族基礎年金は実は条件や手続きも少し異なります。
生活に関わる大切な制度なので、わからないことがあれば年金事務所や市区町村の窓口で相談することをおすすめします。
遺族厚生年金についてちょっと深掘りすると、実は亡くなった方が加入していた厚生年金の内容によって受給額が変わる仕組みが面白いです。厚生年金は働いている期間の給料に応じて計算されているため、例えば長期間高い給料で働いていた方の遺族には、それに見合った手厚い年金が支給されます。
また、遺族厚生年金は遺族基礎年金と合わせて受け取れる場合もあり、その場合は生活の安定につながるので、とても心強い制度です。ちょっと複雑ですが、働いていた人の生活の歴史が反映されているとも言えますね。こうした背景を知ると、年金制度の奥深さが感じられます。





















