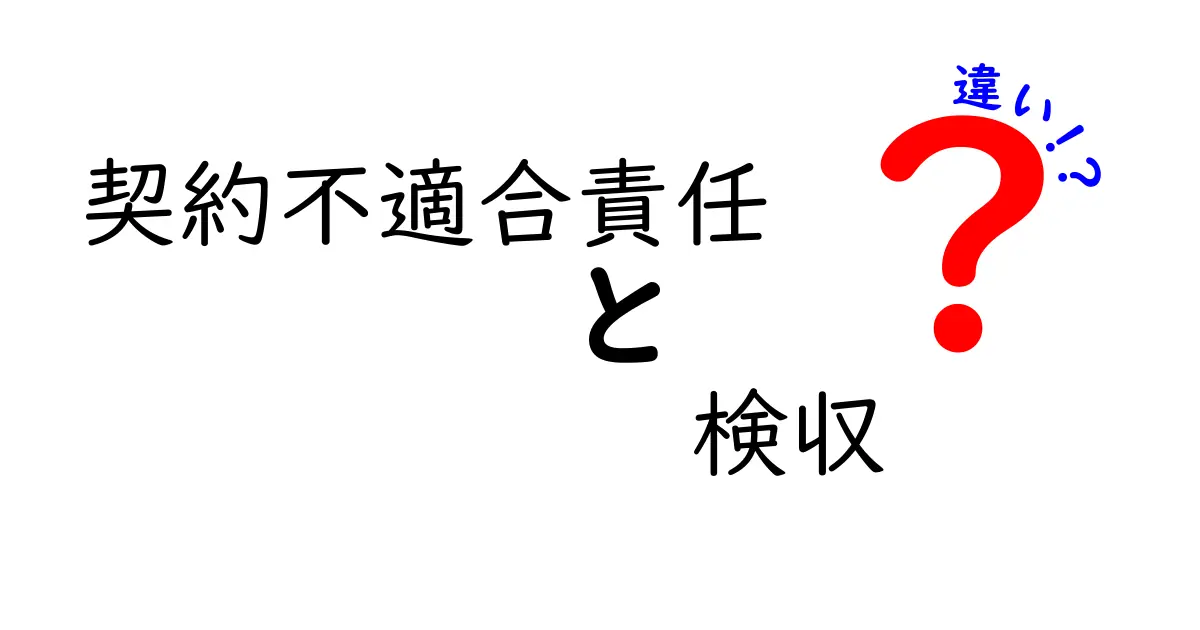

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
契約不適合責任とは何か?
契約不適合責任とは、売買や請負などの契約において、納品された商品やサービスが契約内容に合わない場合に、売り手や提供者が負う責任のことです。例えば、注文した商品が破損していたり、性能が約束と違っていた場合にこの責任が問われます。
以前は「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と呼ばれていましたが、2020年の民法改正により「契約不適合責任」という言葉に変わりました。
この責任は、買い手が商品を受け取った後に不適合が発見された場合に売り手に対して補償を求めることができる制度です。
主な権利としては、修理や交換の請求、価格の減額、契約解除などがあります。
この責任によって、消費者や取引先は安心して契約ができる仕組みとなっています。
検収とは?どんな意味があるのか?
検収(けんしゅう)とは、契約や注文に基づき納品された商品やサービスが契約内容に合っているかを受け取り側が確認することです。
検収は商品の受け取り時に数量や品質、性能が注文どおりかをチェックします。この段階で問題がなければ検収完了となり、代金の支払い手続きが始まります。
逆に問題があれば、通知して修正や再納品を求めることができます。
検収は売買契約の履行を確認する重要なプロセスであり、トラブル防止や品質管理に役立っています。
特にビジネス取引では契約書や発注書に検収の方法や期限などが細かく決められていることも多いです。
契約不適合責任と検収の違いまとめ
契約不適合責任と検収は、どちらも商品やサービスの品質や納品の適正をめぐるものですが、意味と役割ははっきり違います。
下の表で違いをわかりやすくまとめます。
このように検収は契約が正しく履行されたかどうかを現場で確認する作業、契約不適合責任は万一不備があった場合の売り手側の法的な責任です。
どちらもトラブル防止には欠かせない制度と言えるでしょう。
契約不適合責任は最近の法律用語で、昔の『瑕疵担保責任』のことを指します。ところで「瑕疵」と聞くと難しそうですが、簡単に言うと“隠れた問題”のことです。昔は見た目に分かりにくい傷や欠陥が発見されて初めて売り手が責任を負いました。しかし契約不適合責任は、契約の内容に合わない点があれば隠れていなくても責任を問えるのがポイントで、消費者にとってより安心な仕組みになっています。法律も時代と共に分かりやすく、親切になっているんですね。
前の記事: « 契約不適合責任と表明保証の違いとは?わかりやすく解説!
次の記事: 契約不適合責任と製造物責任の違いをわかりやすく解説! »





















