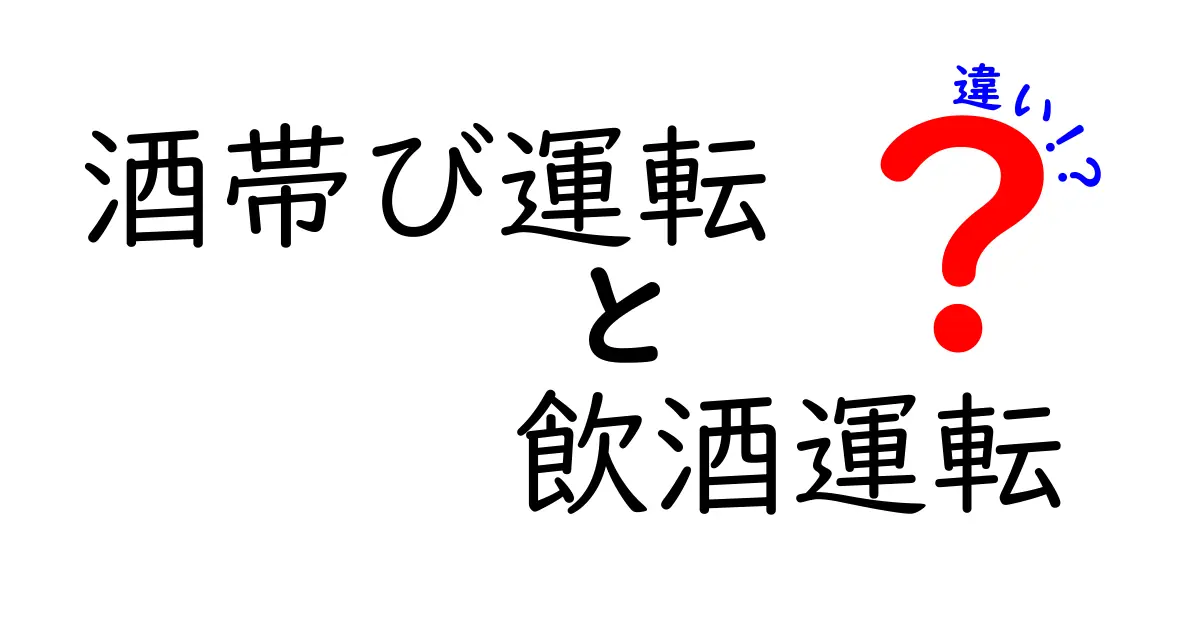

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
酒帯び運転と飲酒運転の違いを知ろう
道路交通法において、運転中のアルコール摂取に関する違反は大きく分けて酒帯び運転と飲酒運転の二つに分けられます。どちらも飲酒が関係する違反ですが、その内容や罰則は異なります。違いを理解すると、自分や周りの安全を守る上でとても役立ちます。今回はこの二つの違いを詳しく解説します。
まず、酒帯び運転とは、運転者の呼気中のアルコール濃度が一定量を超えている場合を指します。飲酒運転とは、運転者が実際に酒を飲んで車を運転した場合を指しますが、法律上は呼気中のアルコール濃度により判断されることが多いです。
法律で決められている酒気帯び基準は呼気1リットル中0.15ミリグラム以上です。これ以上の場合は酒帯び運転となり、これを下回っていても飲酒運転と認められるケースはあります。いずれにせよ、飲酒運転は厳しく罰せられますので絶対に避けるべき行為です。
酒帯び運転の詳細と罰則
酒帯び運転は呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満の場合を言います。検査で基準値を超えた場合、違反として扱われます。
酒帯び運転の罰則は軽犯罪に分類され、違反点数は13点となり免許停止や取り消しの対象となります。罰金は30万円以下で、重い場合は懲役刑が科せられます。
この違反は事故を起こさなくても検査だけで判断されるため、少量の飲酒でも危険視されています。呼気のアルコール量が基準に達しているかどうかが重要なので、ご飯の後であっても運転は避ける方が安全です。
飲酒運転の定義と罰則の強さ
一方飲酒運転は呼気中のアルコール濃度が0.25mg以上の場合に該当します。
この数値を超える飲酒運転は重大な交通違反として扱われ、最大で5年以下の懲役や100万円以下の罰金が科せられることがあります。違反点数は25点と非常に高く、免許取り消しから再取得困難となる場合もあります。
事故を起こさなくても検問や捜査により発覚すると厳罰に処されるため、絶対に飲酒して運転してはいけません。
酒帯び運転と飲酒運転の違いまとめ表
| 違反の種類 | 呼気中のアルコール濃度 | 違反点数 | 主な罰則 |
|---|---|---|---|
| 酒帯び運転 | 0.15mg以上〜0.25mg未満 | 13点 | 30万円以下の罰金、免許停止・取消し |
| 飲酒運転 | 0.25mg以上 | 25点 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金、免許取り消し厳重 |
まとめ:安全第一、お酒を飲んだら運転は絶対にやめよう
日本では飲酒運転に対する罰則が非常に重くなっています。酒帯び運転でも法律違反となり免許停止や罰金の対象となるため、たとえ一杯でも飲んだら運転しないことが最善です。
違いを理解したうえで、自分や家族、周囲の安全を守る行動を心がけましょう。飲酒運転や酒帯び運転は重大な事故や被害につながる危険行為なので、ルールを守り安全運転を心がけてください。
「酒帯び運転」の呼気中アルコール濃度0.15mg以上という基準、実は案外少ない量で引っかかることがあり注意が必要です。例えば、少しだけビールを飲んだ後でも数時間は数値が下がらない場合があります。夕食時などにちょっとお酒を飲んでから運転すると法律違反になるリスクがあるため、「微量だから大丈夫」と甘く考えずに時間を十分空けるか、そもそも運転を控えることが大切です。これによって自分はもちろん周りの人の安全も守れますよ!
前の記事: « 交番と刑事の違いとは?分かりやすく解説!警察の役割を知ろう





















