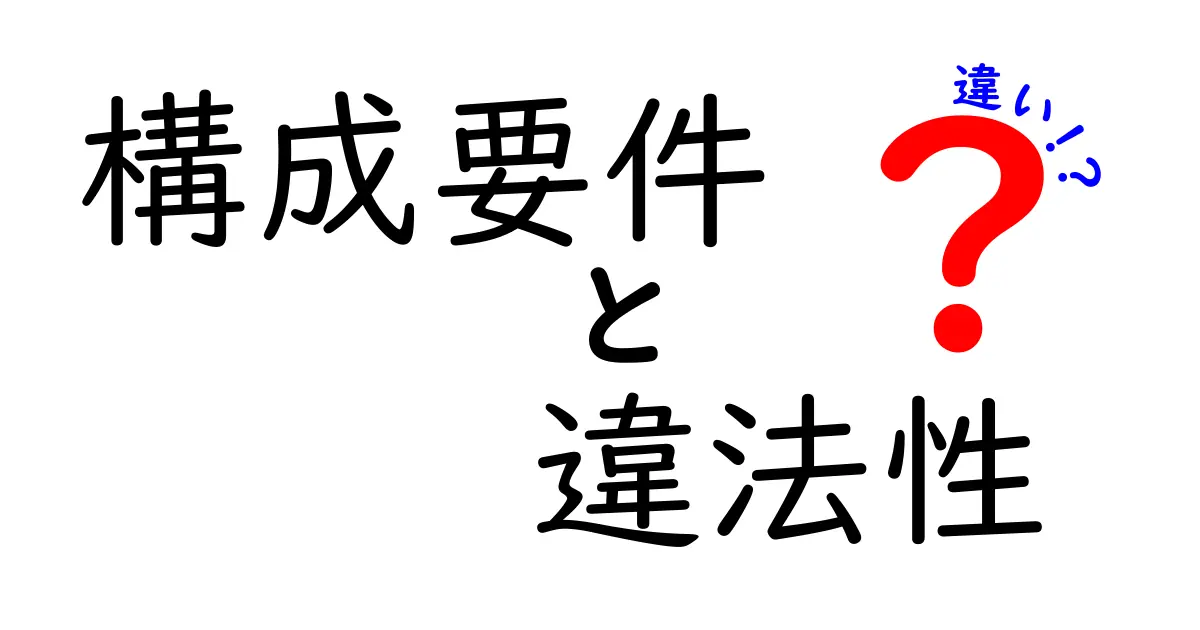

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
構成要件とは何か?基本を押さえよう
法律の話をするときに、よく「構成要件(こうせいようけん)」という言葉が出てきます。構成要件とは、ある行為が犯罪になるかどうかを判断するための条件のことです。たとえば、「泥棒」という犯罪を考えたとき、ただ物を持っていくだけではなく、その行為が「泥棒」の構成要件に当てはまる必要があります。
簡単に言うと、「それは犯罪として認められる特徴や条件がそろっているか」をチェックするものです。法律の条文には、このような構成要件が細かく書かれていて、犯罪の種類ごとに違います。
これがなければ、ただの悪いことでも犯罪ではない可能性があります。たとえば、人の家に入っても、何か特別な事情があれば違法でない場合もあるのです。
違法性とは?行為の悪さの判断基準
次に「違法性(いほうせい)」ですが、こちらは「構成要件にあたる行為が法律に違反している」という性質のことです。違法性があるとは、その行為が社会のルールや法律に反していることを意味します。
たとえば、先ほどの泥棒の例でいうと、構成要件に当てはまることで「泥棒をしました」といえますが、それが法律違反か否かは違法性によって判断されます。
つまり、全ての構成要件該当行為が違法とは限らないのです。例えば「正当防衛」や「緊急避難」の場合は、犯罪の構成要件に見える行為でも違法性がないため処罰されません。これが違法性の判断が難しく、重要である理由です。
構成要件と違法性の違いを表で比較!法律がわかりやすくなる
| 項目 | 構成要件 | 違法性 |
|---|---|---|
| 意味 | 犯罪かどうかを判断する条件や特徴 | 行為が法律に反している性質 |
| 目的 | 行為が犯罪に該当するかチェック | その行為が社会規範に反しているか判断 |
| 例 | 人の物を盗むこと等の条件 | 正当防衛や緊急避難で違法にならない場合 |
| 特徴 | 法律文章に明確に定められている | 判断には事情や背景を考慮する場合が多い |
まとめ:法律の理解に大切なポイント
今回の説明でわかる通り、構成要件と違法性は両方とも法律で重要な概念ですが、意味が大きく違います。構成要件は「ある行為が犯罪として成り立つか」の基本の枠組みであり、違法性は「その犯罪が社会的に許されないものかどうか」の判断です。
法律を学ぶときや、日常生活で法律用語に触れるときは、この違いを押さえておくと理解がスムーズになります。
これを機に、法律の言葉を少しずつ覚えていきましょう!
「違法性」という言葉、法律では難しく感じますが、実は日常生活でとても身近な考え方なんです。たとえば、友達のものを借りて返すのを忘れたとしても、それは違法ではありません。違法性がある行為というのは、社会のみんなが守るべきルールに違反していて、しかも理由がない場合のこと。ちょっとしたルール違反と法律違反は違うんだなー、と覚えておくといいですよ。
前の記事: « 刑事告訴と被害届の違いを徹底解説!知っておきたいポイントとは?





















