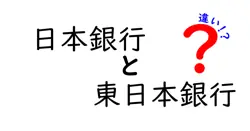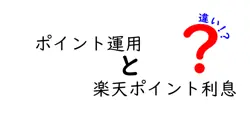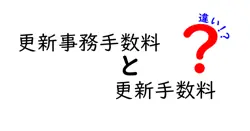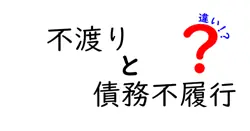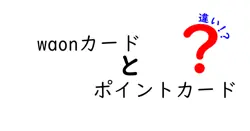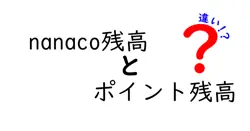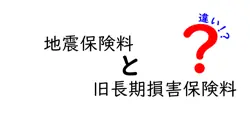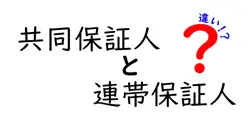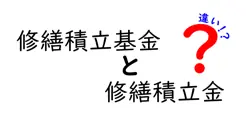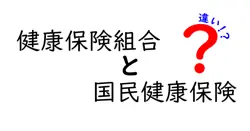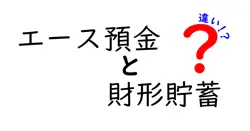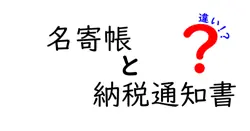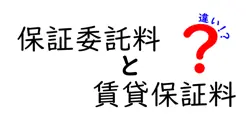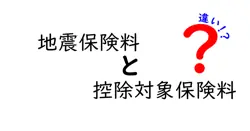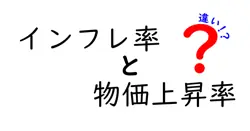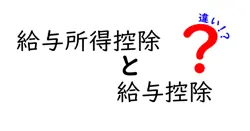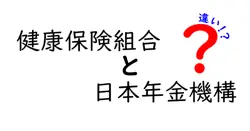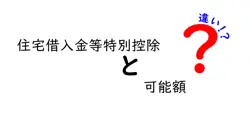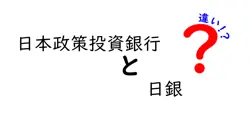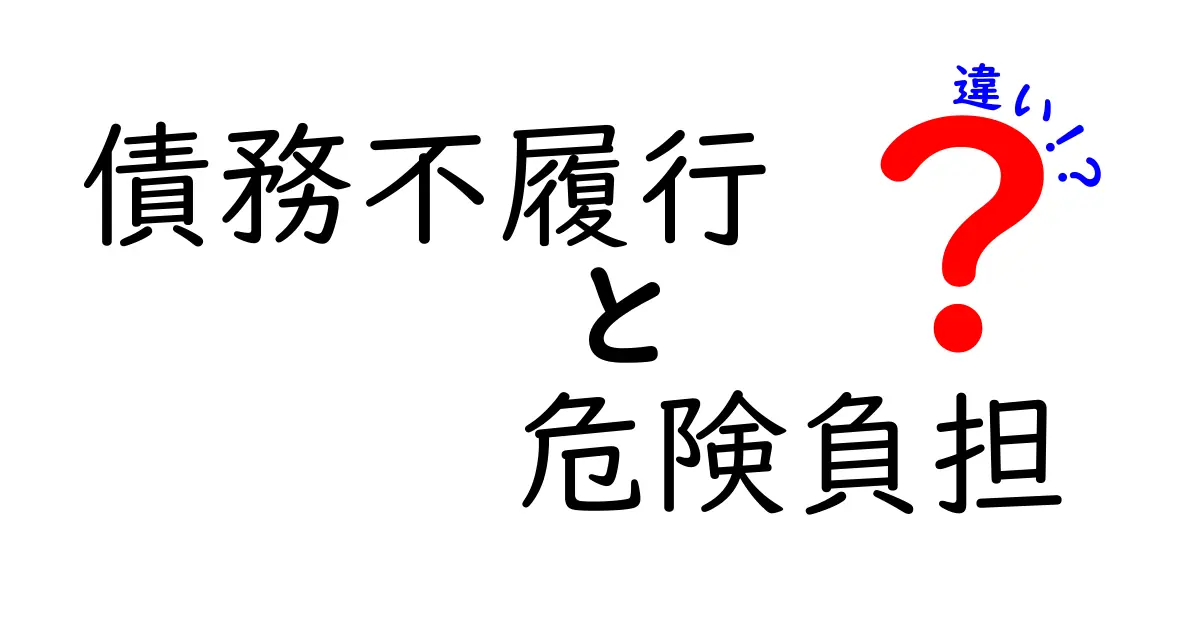
債務不履行と危険負担とは何か?
まず、「債務不履行(さいむふりこう)」と「危険負担(きけんふたん)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?これらはどちらも法律に関わる言葉で、特に契約や取引の場面で使われます。
債務不履行とは、約束したこと(例えば、お金を払う、ものを届けるなど)を守らなかった状態のことです。債務とは約束した義務のことで、不履行は「守らない」ことを意味します。つまり、債務不履行は「約束を破ったとき」のことを言います。
一方、危険負担とは、約束したものに予期せぬトラブルが起きて、どちらがその損失の責任を負うのかという問題です。例えば、売ったものが届ける途中で壊れてしまった場合、誰がその損失を負うのかが危険負担の問題になります。
この二つは似ているようで、実は違う法律の考え方なので、しっかり理解しておくことが大切です。
債務不履行の特徴と具体例
債務不履行は、契約した内容を履行しない、つまり約束を守らないことに対して責任を問うものです。
例えば、あなたがお友達に中古の自転車を売る約束をして、決められた日までに自転車を渡さなかったとします。これが債務不履行です。約束を守らなかったため、お友達から「予定通りに渡してほしい」「もし無理なら損害を補償してほしい」と請求されることがあります。
債務不履行には以下のようなケースがあります。
- 履行遅滞:約束した日時に履行しない
- 履行不能:そもそも約束を履行できない
- 不完全履行:約束したものが完全でない(壊れていたなど)
法律は債務不履行があった場合に、相手が損害賠償を請求できる権利を認めています。
危険負担の仕組みと説明
危険負担は、契約の履行前に起きた事故やトラブルで、物が壊れたり失われた時の責任の分かれ目です。ここで重要なのは、そもそも約束を守れなかったわけではなく、偶然に起きた出来事が原因だということです。
例えば、あなたが友達に本を売り、配達の途中で本が火事で燃えてしまったとしましょう。この場合、火事という予測できない事故が原因で、どちらが損害を負うかを決めるのが危険負担です。
この問題は、売買契約では所有権がいつ移るか、つまり「物の支配が誰にあるか」が大きなポイントになります。
日本の民法では、原則として「引き渡し」がなされてから危険負担が移るとされています。つまり、物を渡すまでは売主の責任、渡した後は買主の責任ということです。
このルールを知っておくことはトラブル回避に役立ちます。
債務不履行と危険負担の違いをわかりやすくまとめる
ここまでで説明した二つの言葉の違いをわかりやすくまとめると次の表のようになります。
| 項目 | 債務不履行 | 危険負担 |
|---|---|---|
| 意味 | 約束した内容を守らないこと | 偶然の事故による損害の責任負担 |
| 責任問われる理由 | 契約違反によるもの | 事故などによる予期せぬ損害 |
| 例 | 商品を渡さない・遅れる・壊れている | 届ける途中で壊れた、火事で焼失 |
| 責任の移るタイミング | 約束違反が起きた時点 | 物の引き渡し時点が基準 |
| 損害賠償請求 | 可能 | 原則不要(例外あり) |
このように、債務不履行は約束を破ったこと自体について責任を負うのに対し、危険負担は事故などの不運な出来事の責任を誰が持つかを決める考え方です。
法律のルールをよく理解することで、トラブルを未然に防ぐことができますし、もしトラブルになっても冷静に対応できるようになります。
ぜひ、契約やお金のやりとりの際にはこの違いを頭に入れておきましょう。
危険負担のルールって、実は普段あまり考えないけど日常生活で意外と関係があります。例えば、ネットで買い物するとき、商品が配送中に壊れちゃったら誰のせい?って疑問に思ったことありますよね。これはまさに危険負担の問題で、基本的に商品が届くまでは売った人の責任なんです。でも荷物を受け取った後で壊れていたらその責任は買った人にある場合も。つまり、商品が手元に来る瞬間が大切なポイントなんです。こんな風に法律は身近な場所で活きていますよ!