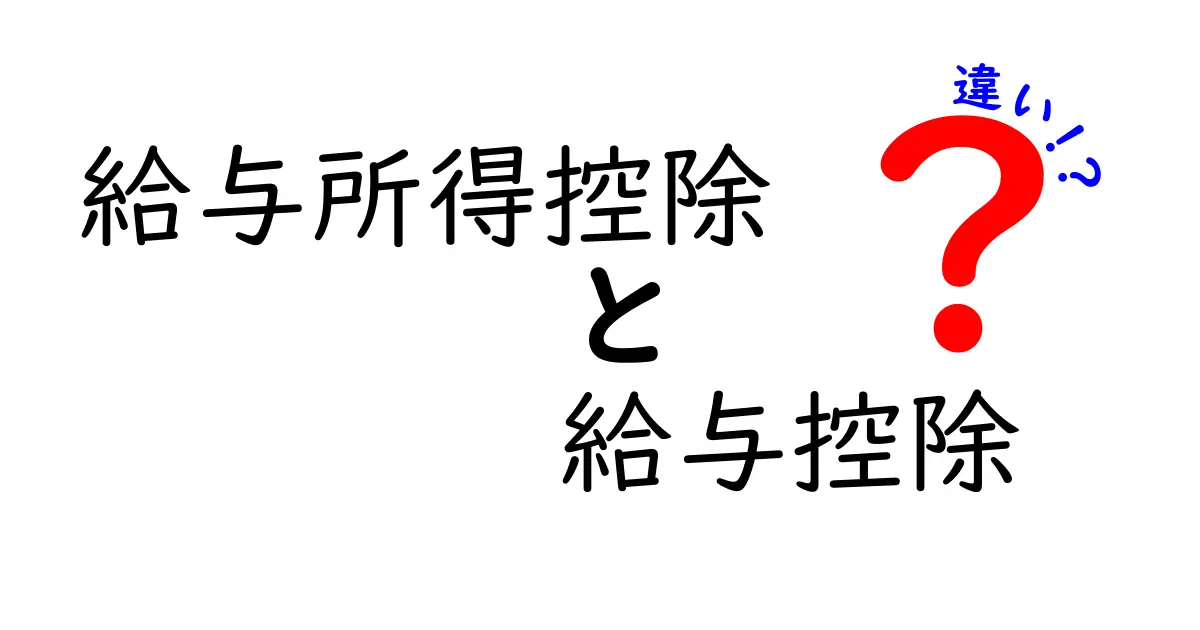

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
給与所得控除と給与控除の違いとは?基本から理解しよう
給与所得控除と給与控除、聞いたことはあっても違いがよくわからないという人も多いでしょう。
給与所得控除は、サラリーマンや会社員が税金を計算するときに使われる控除の一種で、収入から一定額を差し引くことで所得税の対象となる「所得」を減らせます。
一方、給与控除は、給与から差し引かれる様々なお金のことを指す言葉で、社会保険料や雇用保険料、所得税の源泉徴収などを含みます。つまり、給与控除は給与明細に記載される項目全体を指すことが多く、給与所得控除とは目的も意味も違います。
このように、給与所得控除は所得税を計算する際の控除で、給与控除は給与から差し引かれる費用全般を指します。両者は似た名前ですが、役割が全く異なるため混同しないことが大切です。
給与所得控除の具体的な仕組みと計算方法
給与所得控除は、国が定める基準に基づき、給与収入に応じて決まる一定の金額が差し引かれます。
主な考え方は「給与を得るためにかかる必要経費」をイメージして作られた控除額で、全員が所得から一定額を差し引くのではなく、給与収入によって控除額が違う仕組みです。
例えば、年間給与収入が180万円以下の場合は最低の控除額が決まっています。もっとも多いパターンとして、給与収入が増えるにしたがって控除額も少しずつ増え、一定以上になると段階的に控除率が下がるようになっています。
この給与所得控除があることで、実際の税金計算では課税対象となる所得が減り、税金が軽減されるというメリットがあります。
以下の表で2024年の給与所得控除額の一部を示します。給与収入(年) 給与所得控除額 ~550万円 収入×40%(最低65万円) 550万円超~1,000万円 収入×30%+18万円 1,000万円超 195万円(上限)
給与控除の具体例と注意点
給与控除は、給与から差し引かれるお金の総称で、次のようなものが含まれます。
- 社会保険料(健康保険、年金、介護保険など)
- 雇用保険料
- 所得税の源泉徴収
- 住民税の特別徴収
給与明細で「控除」として示されている項目は主にこれらです。給与控除は給与所得控除のように税額を決める計算上の控除ではなく、給与から天引きされる実際のお金の金額を示します。
そのため、給与控除は所得税の計算と直接対応しない部分が多いです。例えば、社会保険料は将来の年金や医療費のために積み立てるためのものであり、税控除とは別の性質があります。
給与控除の理解が深まると、給与明細を見て何にお金が使われているかがわかり、家計管理にも役立つでしょう。
給与所得控除って実は、いわば給与から「仕事にかかる必要経費」を国が代わりに一律計算してくれているようなものなんですよ。
サラリーマンは自分で経費を細かく計算しなくても、この控除のおかげで簡単に税金計算ができる仕組みです。
だから給与所得控除があると、サラリーマンの税負担が少し軽くなるんですね。
でも面白いのは、この給与所得控除は年によって制度が何回か変わっていて、時代の変化に合わせて調整されている点。
だから、これから社会が変わっていくと、また控除の内容も変わるかもしれませんね!
次の記事: これでスッキリ!経費と給与所得控除の違いをわかりやすく解説 »





















