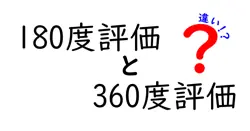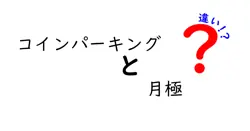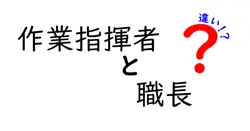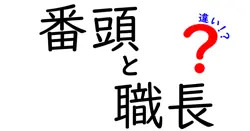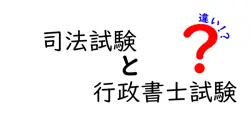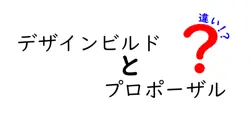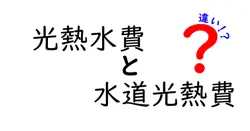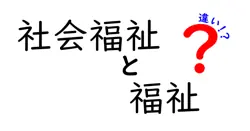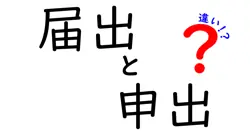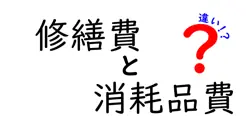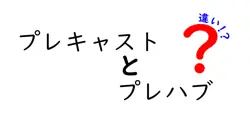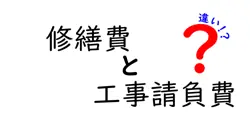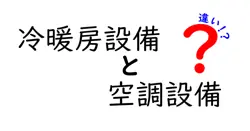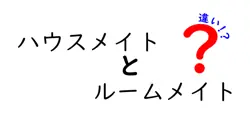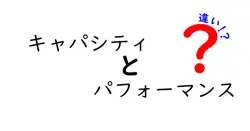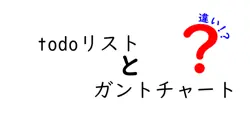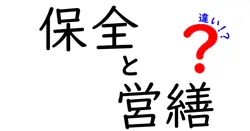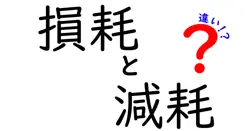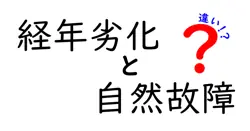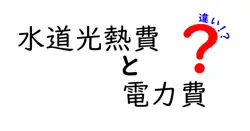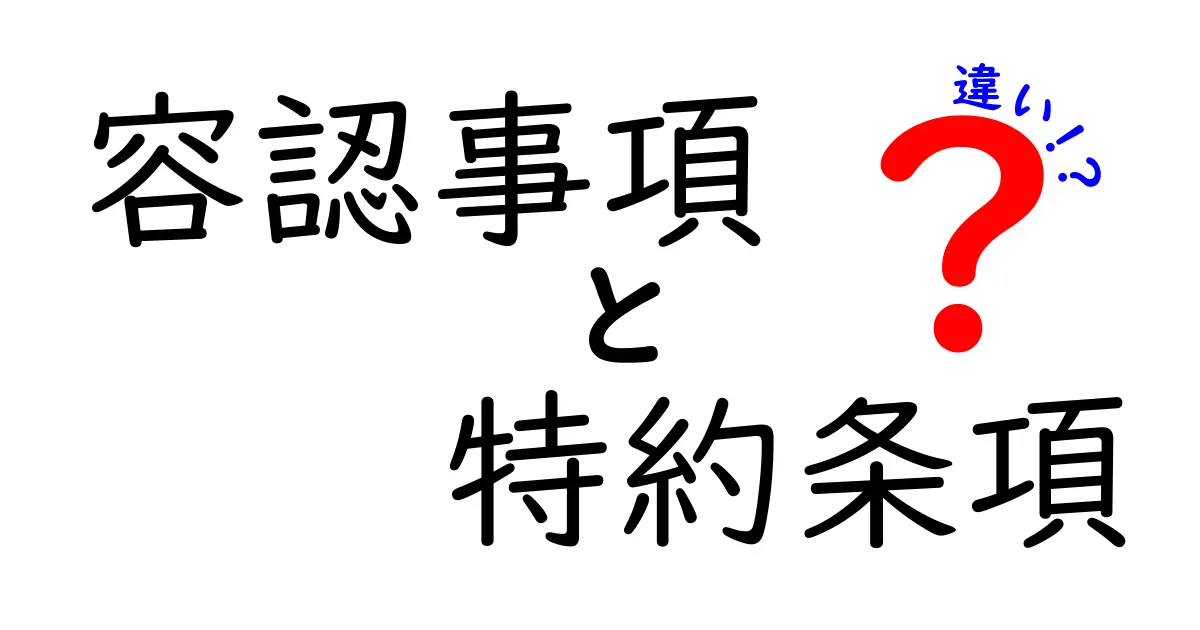
「容認事項」と「特約条項」の基本的な意味とは?
まずは「容認事項」と「特約条項」という言葉の基本的な意味をそれぞれ確認しましょう。
容認事項とは、契約や取り決めの範囲内で、相手方の行動や状態を問題とせずに認める事項のことを指します。つまり、あらかじめ一定の範囲で許される条件や行為を明確にしておくものです。
一方、特約条項は、契約書などに記載される特別な取り決めで、通例の契約内容とは異なる独自のルールを定めた条項のことを言います。通常の契約内容に追加や変更を加える役割をもちます。
この二つはどちらも契約関連の用語ですが、役割や内容に違いがあります。これを理解しないと契約上で誤解が生じやすくなります。
それではそれぞれをさらに詳しく掘り下げてみましょう。
容認事項の特徴と使われ方
容認事項は、契約の中であらかじめ「この範囲なら問題ない」と合意している内容です。
例えば、不動産の賃貸契約において「小型ペットの飼育を容認する」といった形で記されることがあります。これにより、通常禁止されるはずのペット飼育が特定の条件で許可されている状態になります。
このように、容認事項は契約のルールの中でやや緩やかな例外や許可を示します。
特徴的なポイントは以下の通りです。
- 相手方の行動を許容する範囲を示す
- 問題にならないとあらかじめ合意している
- 不定期に変更されることは少ない
容認事項があることで、利用者や契約者は安心して特定の行動ができるようになり、トラブル防止につながります。
ただし、条件が明確でなかったりあまりにも範囲が広いと後で問題になることもあるため、明確な記載が必要です。
特約条項の特徴と実際の例
特約条項は、一般的な契約内容からの変更や追加を行う特別な約束ごとです。
例えば、契約期間を延長したり、支払方法を特別に決めることなどが含まれます。
特約条項は契約書内に記載され、契約の法的効力を持ちますので、双方が同意しなければ有効になりません。
例えば、保険契約で「特定の病気に対してのみ保険金の支払い条件を変更する」といった場合があります。
このように特約条項は契約のカスタマイズが可能になり、契約内容を柔軟にする大切な役割を果たします。
主なポイントは以下です。
- 契約の一部を独自の条件で変更・追加するもの
- 契約の原則を覆す場合もある
- 必ず契約書に明示し、双方合意が必要
特約条項があることで、契約者同士で特殊な事情に応じた取り決めができ、トラブルを未然に防げることもあります。
容認事項と特約条項の違いを表で比較!
| 項目 | 容認事項 | 特約条項 |
|---|---|---|
| 定義 | 契約において許される行為や状態 | 契約内容の特別な変更や追加の約束 |
| 役割 | 一定の範囲内での許可や緩和 | 契約のルールを柔軟に変更・追加 |
| 記載場所 | 契約書の中の条項や覚書 | 契約書の特約条項部分に明示 |
| 法的効力 | 契約の一部として認められる | 契約の一部として強い効力を持つ |
| 合意の必要性 | 契約締結時の共通理解が多い | 双方の明確な合意が必須 |
このように違いを整理すると、契約のルールに対する「許容」と「変更」という性質の違いがはっきりします。
契約を結ぶ際は、この違いを理解し、自分の立場やニーズに応じて適切に使い分けることが非常に重要です。
まとめ:契約での「容認事項」と「特約条項」を正しく理解しよう
この記事では、「容認事項」と「特約条項」の意味や特徴、そして違いについて詳しく説明しました。
容認事項は契約の範囲内で相手の行動や状態を許可する内容で、特約条項は契約内容を特別に変更・追加する条項です。
両者は契約を守りながら柔軟な対応を可能にする重要な要素です。どちらも契約書に明確に記載されていることが望ましく、十分理解しておくことがトラブル防止の鍵になります。
契約社会で安全に自分の権利を守るために、これらの違いをしっかり抑えましょう。
ご参考になれば幸いです。
契約でよく見かける「特約条項」ですが、実はこの条項があるかどうかで契約の内容やトラブルの解決方法が大きく変わることがあります。
例えば、特約条項がなければ契約の基本ルールがそのまま適用されるのですが、特約条項で細かく条件を変えている場合はその部分が優先されます。
これにより、契約のカスタマイズが可能になり、自分たちの事情に合わせた柔軟な取り決めができるわけです。
ただし、特約条項はきちんと書面にして双方が同意していないと効力はありません。なので、契約の時は特約条項があるかどうか、そして内容をしっかり読むことがとても大切なんです。
前の記事: « 債務不履行と危険負担の違いとは?法律の基本をやさしく解説!