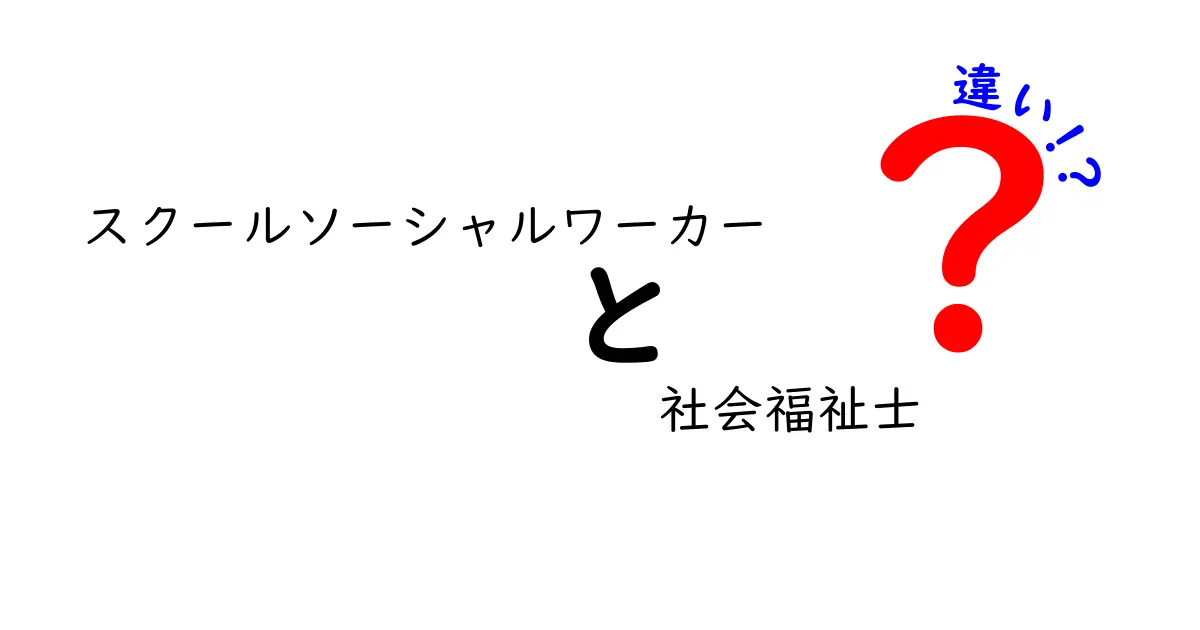

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
スクールソーシャルワーカーと社会福祉士の基本の違いとは?
学校で子どもたちを支える仕事に携わる人たちとして、スクールソーシャルワーカー(SSW)と社会福祉士があります。どちらも福祉の専門家ですが、
仕事の場所や内容、資格の取り方が違います。
まずはこの二つの基本的な違いを知っておきましょう。
スクールソーシャルワーカーは学校に勤務し、子どもやその家庭が抱える問題を解決するために支援を行います。
一方で社会福祉士は病院や福祉施設、地域の相談所などさまざまな場所で働き、高齢者や障害者、子どもなど幅広い対象者を支援します。
つまり、SSWは学校という場に特化した社会福祉士のような役割と考えることもできますが、資格や働く範囲は少し異なります。
スクールソーシャルワーカーの役割と仕事内容
スクールソーシャルワーカーは主に学校に所属して、子どもたちの心理的な問題や家庭の相談に対応します。
子どもがいじめや不登校、家庭環境の問題で苦しんでいるときに、学校と家庭、関係機関との橋渡し役をします。
また、学校生活が円滑に進むように支援計画を立てることも重要な仕事です。
学校内の先生やカウンセラーだけでは対応しきれない問題を解決するために、福祉の専門スキルを活かしています。
さらに、地域の福祉サービスと連携し、子どもを取り巻く環境づくりにも貢献しています。
社会福祉士の役割と仕事内容
社会福祉士は、医療機関や福祉施設、地域の相談窓口など、多様な場所で働きます。
主な仕事は生活上の問題を抱える人たちの相談に乗り、必要な支援やサービスを紹介・調整することです。
高齢者の介護、障害者の社会復帰、児童虐待防止、生活困窮者の自立支援など、多種多様なケースに対応します。
法律や制度に基づいた専門的な知識を持ち、相談者が安心して生活できるように助けることが使命です。
地域の福祉サービスと連携して、多面的に支援を行う点が特徴です。
資格取得の方法と必要条件の違い
スクールソーシャルワーカーになるためには、まず社会福祉士の資格取得が一般的です。
社会福祉士の資格を持っていることが求められる場合が多く、専門の研修や実務経験を積んでスクールソーシャルワーカーとして認定されます。
つまり、スクールソーシャルワーカーは社会福祉士の資格を持ちつつ、学校特有の問題に対応する専門職といえます。
社会福祉士資格を取得するには、厚生労働省の指定した大学や短大を卒業し、国家試験を受けて合格する必要があります。
この試験は福祉や医療、心理学など幅広い学問が問われるため、十分な準備が必要です。
主要な違いをわかりやすく表にまとめました
まとめると、スクールソーシャルワーカーは社会福祉士の資格を基に学校の現場に特化した仕事をしている専門職ということです。
福祉の仕事に興味があるけど、学校で子どもたちを支えたいという人にはスクールソーシャルワーカーがぴったりといえます。
また、社会福祉士は幅広い現場で専門知識を活かして人々を支援する仕事で、より多様なケースに対応したい人向きです。
どちらも人を助ける大切な仕事なので、自分のやりたい仕事や働く場所を考えて選ぶと良いでしょう。
スクールソーシャルワーカー(SSW)は、たいてい社会福祉士の資格を持っている人がなる専門職ですが、学校という特別な環境で働きます。
面白いのは、学校だけでなく地域や家庭とも深く関わり、子どもが安心して学べる環境作りを手助けしていることです。
たとえば、いじめが起きた時には学校の先生だけでなく、SSWが家庭訪問をしたり福祉サービスと連携したりして問題解決をはかることもあります。
こうした役割は単に相談に乗るだけではなく、法律や福祉制度の知識も必要で、専門性の高さがわかりますね。
子どもを守るために学校に専門家がいるというのはとても心強いことです。
次の記事: 司書補と図書館司書の違いとは?資格や仕事内容を徹底解説! »





















