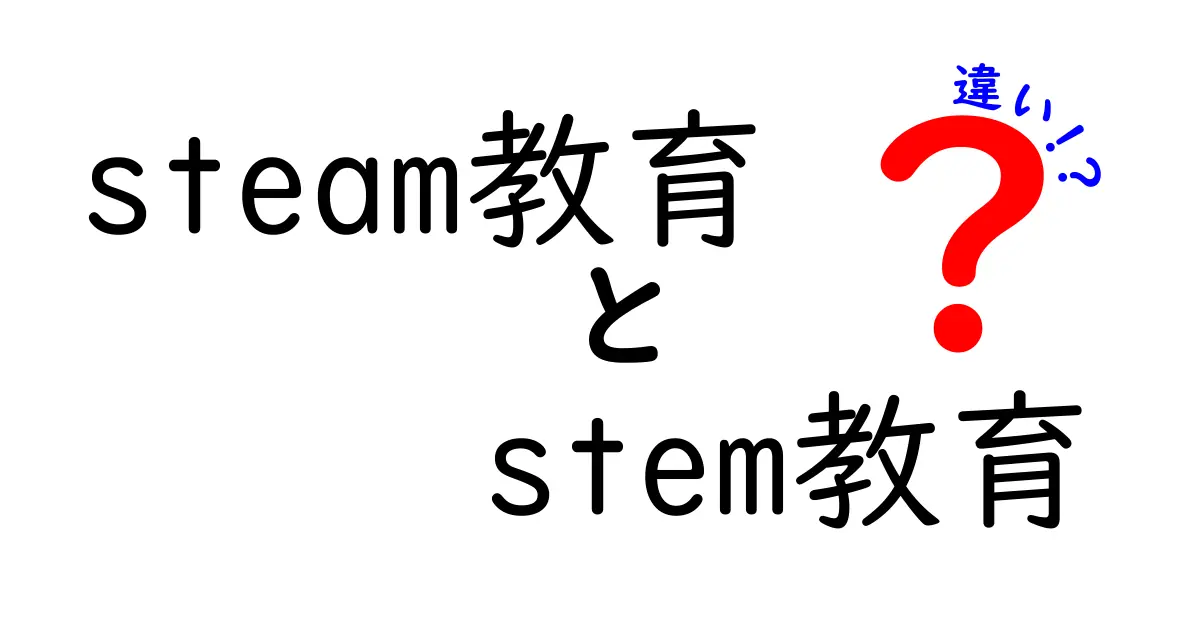

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
STEAM教育とSTEM教育とは何か?
最近、学校や教育の現場でよく聞く「STEM教育」と「STEAM教育」という言葉。どちらも子どもたちの将来に役立つ力を育てるための教育方法ですが、その違いをご存知でしょうか?
STEM教育はScience(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Mathematics(数学)の4つの分野に焦点を当てています。これらの分野の基礎知識や問題解決力を高め、理系の力を伸ばすことが目的です。
一方STEAM教育は、STEMにArts(芸術)を加えたものです。芸術には美術や音楽、デザインなどが含まれ、創造性や表現力を育てることが重視されます。
このように、STEAMはSTEMの理系教育に芸術の要素を融合させ、より柔軟で多角的な学びを目指す教育方法と言えます。
STEAM教育とSTEM教育の主な違いとは?
大きな違いは「Arts(芸術)」の有無です。
STEMは理系4分野に絞ってスキルを磨くのに対し、STEAMは芸術を融合することで、創造力やコミュニケーション力、デザイン思考など幅広い能力も育成します。
下記の表で詳しく見てみましょう。
| ポイント | STEM教育 | STEAM教育 |
|---|---|---|
| 重視する分野 | 科学、技術、工学、数学 | 科学、技術、工学、数学、芸術(美術・音楽・デザイン) |
| 目的 | 理系能力の強化、問題解決力 | 理系能力+創造性・表現力の育成 |
| 学びの特徴 | 論理的・分析的思考が中心 | 分析的思考+感性的・創造的思考 |
| 将来の活用例 | 技術職、科学研究、プログラミング等 | デザイン業界、商品開発、科学技術と芸術を融合した分野等 |
さらに、STEAM教育はチームでの協力やコミュニケーションも重視されるため、社会に出たときに必要な多様なスキルを総合的に身に付けやすいのが特徴です。
実際の教育現場での変化と未来への期待
日本でもSTEM教育はすでに多くの学校で取り入れられています。理科実験やプログラミング授業がその例です。
しかし、創造的な発想や表現力、問題解決のアプローチの多様化を重視する声が高まり、STEAM教育の重要性も増しています。
例えば、美術の時間に科学の概念を使った作品づくりをしたり、音楽やデザインの要素を取り入れることで学びが面白くなり、子どもたちの興味や意欲がより高まります。
未来の社会はAIやロボット技術などが進化し続けます。固定観念にとらわれず、テクノロジーと創造性を両立させて新しい価値を生み出す力が、より一層重要になるでしょう。STEAM教育はそのための土台づくりとして注目されています。
教育関係者や保護者の方も、子どもたちが理論だけでなく、柔軟で多面的に考えられる力を育てるために、STEAMの考え方を理解しておくと今後の学び選択に役立ちます。
STEM教育にArts(芸術)が加わったSTEAM教育ですが、実はこの『芸術』にはすごく広い意味があります。単なる美術や音楽だけでなく、デザインや演劇、さらには創造的な問題解決の方法まで含まれているんです。つまり、ただ計算や実験ができるだけではなく、『どうすればより良い方法で世界を変えられるか?』という発想力を育てることがSTEAMの狙い。これは、未来にますます必要となるスキルなので、芸術の力を侮ってはいけませんよ!
前の記事: « 指導主事と教頭の違いとは?役割や仕事内容をわかりやすく解説!
次の記事: 学会と研修会の違いとは?目的や参加者、内容をわかりやすく解説! »





















