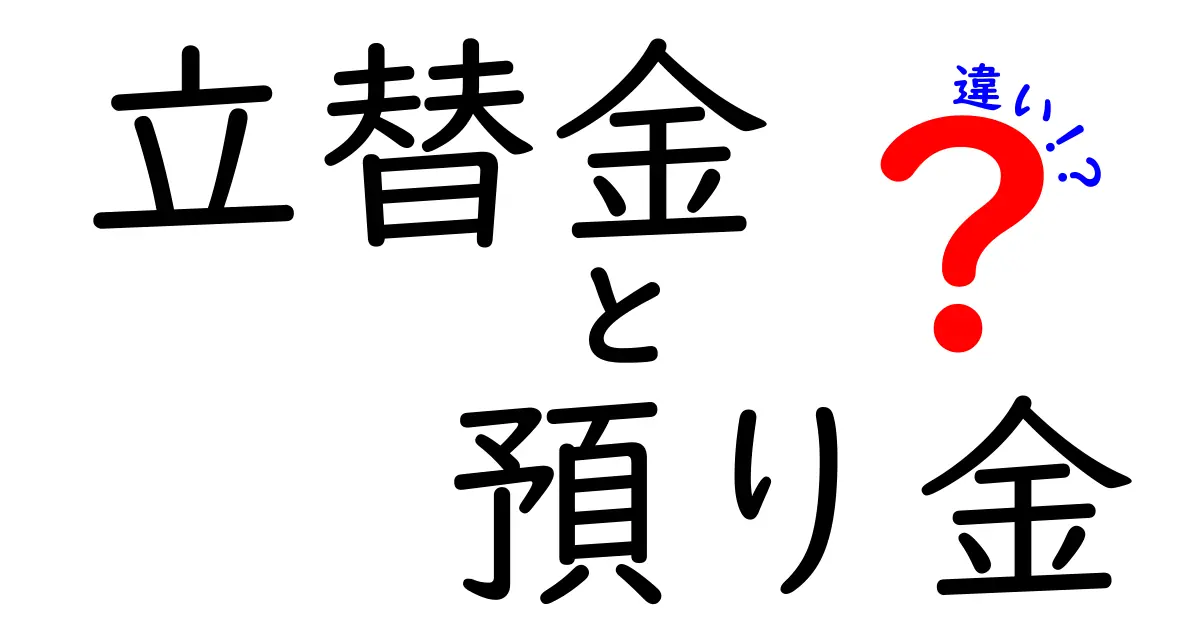

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
立替金とは?その基本と意味を解説
経理や会計の世界でよく登場する「立替金」という言葉は、会社や個人が一時的に他人や取引先の支払いを代わりに行ったお金のことを指します。たとえば、社員が会社のために交通費を先に払った場合、その社員が会社から返してもらうべきお金が立替金です。
この立替金は、あくまで会社の費用や支払いのために一時的に立て替えたお金であり、後で清算(精算)し返金されることが前提です。
経理上は「資産」として扱われ、将来的にお金が戻ってくるためプラスの勘定項目となります。このように、立替金は一時的な負担の救済として重要な役割を持っています。
預り金とは?特徴と経理上の扱い
一方「預り金」とは、他人から預かっているお金のことを指します。例えば、会社が社員の給料から天引きした保険料のように、まだ保険会社に渡していないが会社が一時的に管理しているお金が預り金です。
ここでポイントなのは、預り金は会社の「資産」ではなく「負債」として扱われることです。なぜなら、会社はこれらのお金を最終的に他の誰かに渡す義務があるため、負担を持っていると考えられます。
つまり、預り金は自分のものではなく「預かっている」だけのお金であり、後で渡さなければならないお金として会計処理は厳密に行われます。
立替金と預り金の違いをわかりやすい表で比較
ここまでの説明を踏まえて、両者の違いを表にまとめました。理解の助けにしてください。
| 項目 | 立替金 | 預り金 |
|---|---|---|
| 意味 | 他人のために一時的に支払ったお金 | 他人から預かっているお金 |
| 性質 | 資産(返金を受ける権利) | 負債(将来返さなければならない義務) |
| 例 | 社員が先に払った交通費、経費の立替 | 社員の天引き代金、保証金の預かり |
| 経理処理 | 立替金勘定などで資産計上 | 預り金勘定などで負債計上 |
立替金と預り金を正しく経理するための注意点
いくら似ているように見えても、立替金と預り金は経理上の扱いが異なります。
誤った処理は財務諸表の信頼性を損ね、税務調査でも指摘される可能性が高いため、注意が必要です。
立替金は返済されることが前提なので資産勘定に計上しますが、実際に清算が遅れている場合は未収金として管理することもあります。一方、預り金は会社のものではないため、必ず負債として記録し、預かっているタイミングを把握しましょう。
また、清算や返済の管理をしっかり行い、取引の目的と実態に応じて適切な勘定科目を利用することが大切です。
「立替金」という言葉、実は日常生活の中でもよく見かけますね。友達同士で食事代を一人が先に払った場合、その人は他の人から立替金を受け取ることになります。経理の世界でもこの考え方は同じで、会社や社員が費用を先に負担して後で清算する仕組みです。ちょっとしたお金の「貸し借り」にも似ていて、返済や精算のルールが明確になっているのが特徴です。こうした身近な例から立替金をイメージすると理解しやすいですよね。
前の記事: « 【誰でもわかる】支払調書と法定調書合計表の違いを徹底解説!





















