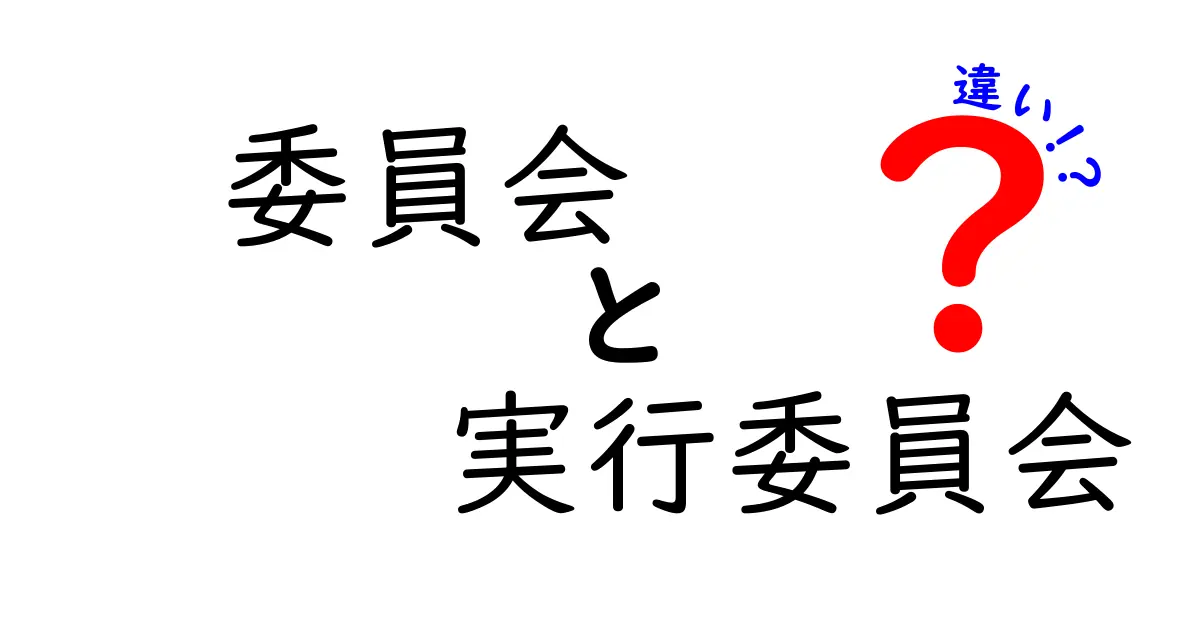

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:委員会と実行委員会の違いを知る理由
ここではまず「委員会」と「実行委員会」という言葉がどう使われるのかを整理します。学校や地域の行事ではこの二つの組織名がよく出てきます。混同しやすいポイントは、名前だけを見ると似た印象を受ける点です。実は役割や権限、決定の仕方が異なります。
この差を知っておくと、誰が何を決めるべきかがはっきり見えるようになり、計画や準備がスムーズになります。
たとえば文化祭の実行計画を立てるとき、委員会が方針を作り実行委員会が日程や担当を割り振る、そんな役割分担が生まれます。
この章ではまず語源的な意味から整理し、次に日常の場面での使い分けのコツを紹介します。最初の理解が後の実践につながるため、ゆっくり読み進めましょう。
実務での役割と権限の違いを詳しく見る
委員会とは何かをもう少し具体的に見ていきます。「委員会」は会の方針を決める組織であり、最低限の会議運営や活動方針の決定を行います。人数は組織ごとに異なり、総務や広報、企画などの職能別に設置されることが多いです。
一方で「実行委員会」は実際の運営を担う組織であり、決定された方針を現場で形にします。イベントの日程を決め、会場を手配し、当日の役割分担を現場で展開します。実行委員会は会議の回数が多く、進捗管理と柔軟な調整が求められる点が特徴です。
この二つの違いは、会議室の中だけの議論と現場の動きの間を結ぶ橋渡しの役割を分担しているかどうかにあります。委員会が「何をするか」を決めるのに対して、実行委員会は「どうやって実際に動かすか」を具体的に決め、時間と場所と人の動きを管理します。
この section では次の表で二つの組織の特徴を並べ、体感として理解できるようにします。
委員会と実行委員会を使い分ける場面のコツ
現場の経験から、使い分けのコツを実践的にまとめます。最も大事なのは目的の明確さです。イベントの成功という大きな目的に対して、どの組織がどの責任を負うのかを最初に決めておくと混乱を防げます。
具体的には、最初の段階で「委員会は方針と全体像をつくる」「実行委員会は日程と実務を割り振る」という役割分担を文書化しておくことが有効です。
また、進捗の共有は透明性を保つためにも重要です。会議の議事録と週次の報告をセットにし、誰が何をいつまでにやるかを全員が把握できる状態を作ります。
最後に、新しい課題が生まれたときの対応ルールを事前に決めておくと、急な変更にも対応しやすくなります。
実行委員会という言葉を思い浮かべると、イベントの現場作業を想像する人が多いかもしれません。実際には計画と現場の間を結ぶ“橋渡し役”としての機能が強く、リーダーシップを学ぶ場にもなります。私たちはこの組織の雰囲気を雑談混じりに語り合うことが多く、何を任せると誰が動くのか、どんな連携が必要になるのかを、仲間と話し合いながら深掘りします。実行委員会の良さは、失敗を共有して改善案を出すプロセスと、達成感を仲間と分かち合える点にあります。





















