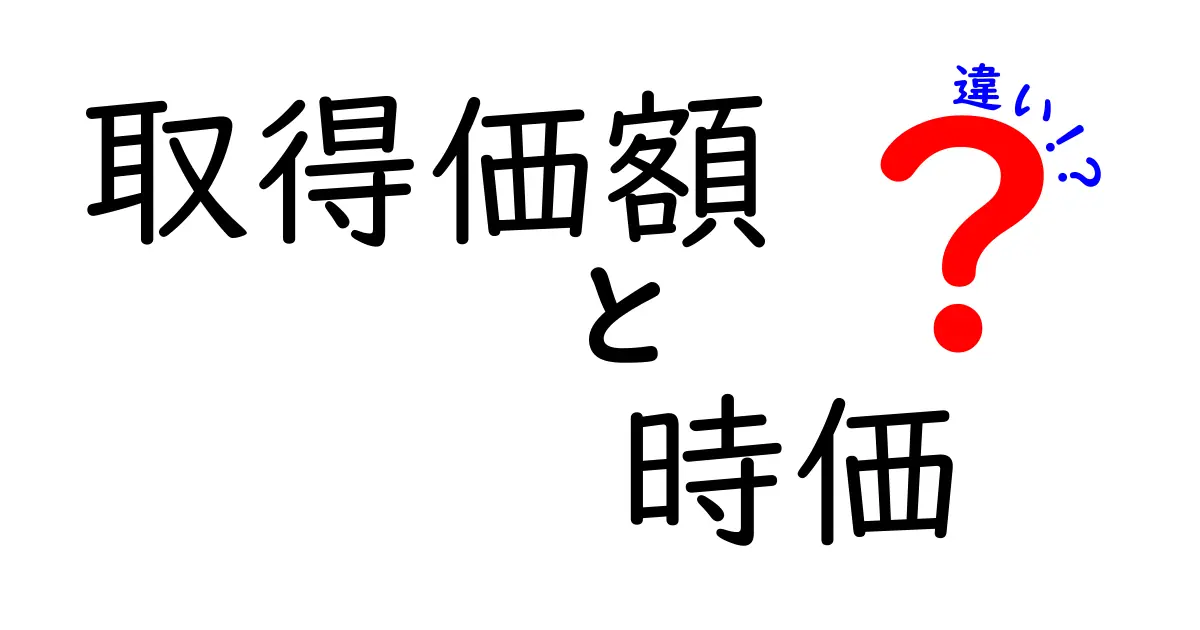

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
取得価額とは何か?
まずは取得価額について説明しましょう。取得価額とは、ある資産を購入したときに支払った金額のことです。たとえば、不動産や株式、設備などを買ったときの実際の購入代金や手数料を含めた総額が取得価額になります。
この価額は、資産を手に入れた時点での実際の費用を反映しており、その資産の原価として会計に記録されます。取得価額は変わらず、資産を持ち続ける限り減ることはありません。ただし、減価償却という仕組みで価値の一部を毎年費用として計上することはあります。
たとえば、10万円で買ったパソコンの取得価額は10万円です。このパソコンの価値が時間とともに変わっても、会計上は10万円がもとの価値となります。
このように、取得価額は購入時の実際のコストを示しています。
時価とは何か?
一方で、時価はその資産がある特定の時点で市場で取引されるときの価格のことを指します。つまり、現在の市場価値、または売却した場合に得られるであろう金額のことです。
時価は市場の需要と供給、経済の状況、資産の状態などによって常に変動します。たとえば、株式の場合は株価が毎日変わりますし、不動産も地域や経済情勢によって価格が上下します。
そのため、時価は取得価額とは異なり、変動する価格です。たとえば、最初に10万円で買ったパソコンが今は中古市場で5万円で売れる場合、その時価は5万円となります。
このように、時価は「今の価値」を示しており、売買や評価替えの時に重要な指標となっています。
取得価額と時価の違いを表で比較
なぜ違いを知ることが重要なのか?
この2つの違いを理解しておくことは、ビジネスや個人の資産管理にとって非常に重要です。なぜなら、取得価額でしか見ていないと、資産の現在の価値がわからない一方、時価だけで見ていると、購入当初の投資額が無視されてしまうからです。
特に決算書を作成したり、資産の売却や買い増しを検討する際には、取得価額と時価の双方を踏まえて判断する必要があります。
たとえば、株式の評価替えでは時価で評価しないと、実態とかけ離れた損益が生じる可能性があります。また、不動産の場合は取得価額を基に減価償却をしつつ、時価も把握しておくことで適切な売却タイミングを見極められます。
このように、取得価額と時価の違いを正しく理解することは、資産の正確な管理と経営判断に直結するのです。
取得価額ってじつは買ったときの値段だけど、実はそれだけじゃ資産の本当の価値はわからないんだよね。たとえば、10万円で買ったパソコンの取得価額は10万円だけど、時間が経つと市場価値は下がってたった5万円になることも。企業では会計上は取得価額を使うから、減価償却で毎年少しずつ価値を減らして計上してるんだ。こうした仕組みを知ると、資産の価値って時間や場面で変わるんだなと実感できるよね。
次の記事: 消費税と付加価値税の違いとは?中学生でもわかる簡単解説! »





















