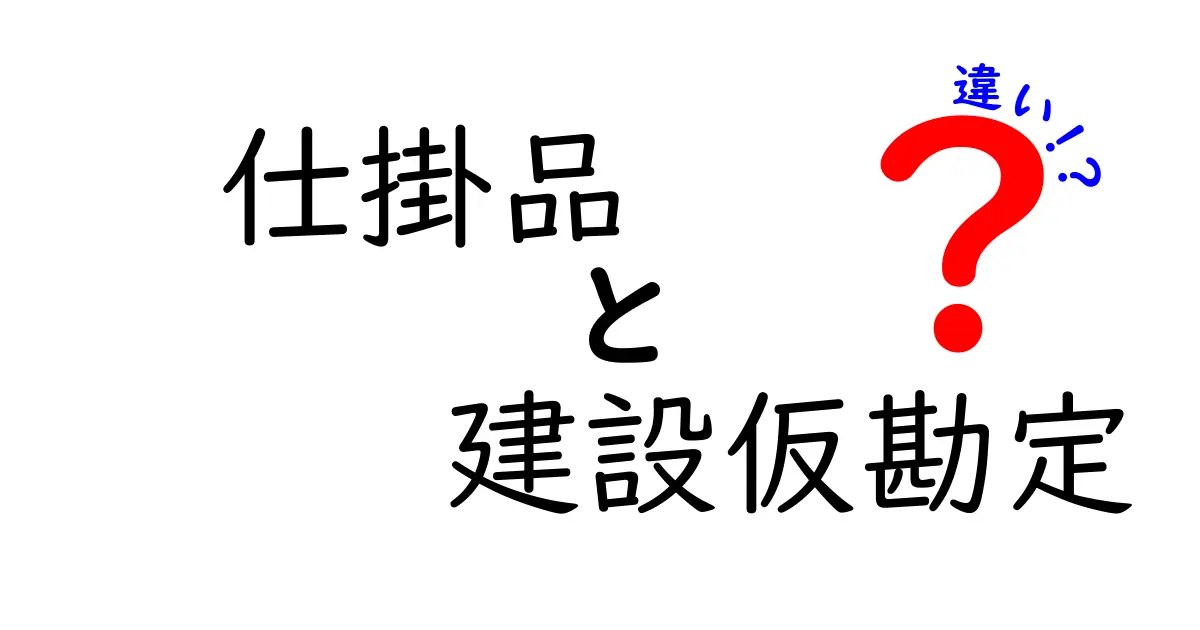

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
仕掛品と建設仮勘定とは何か?基礎から理解しよう
みなさんは「仕掛品(しかけひん)」と「建設仮勘定(けんせつかりかんじょう)」という言葉を聞いたことがありますか?
これらはどちらも会計や経理の分野で使われる用語ですが、何が違うのか難しく感じるかもしれません。仕掛品は製造が途中の製品の在庫を意味し、建設仮勘定は建物などの資産を造っているときに使う特別な勘定科目です。
それぞれ役割や意味が異なるため、今回はわかりやすく説明していきます。
まずは「仕掛品」から見ていきましょう。仕掛品とは、まだ完成していないけれど製造の途中にある製品のこと。たとえば、パン屋さんでまだ焼いていないパン生地が仕掛品にあたります。
そして「建設仮勘定」は、会社が新しい工場やビルを建てるとき、その建設費用を一時的にためておくための勘定です。完成して資産として使い始めるまでの費用の仮置き場のようなものです。
このように、2つは似ているようで役割も使用される場面も異なります。
仕掛品と建設仮勘定の違いをわかりやすく比較
次に、仕掛品と建設仮勘定の違いをポイントごとに比較しながらまとめてみます。
下の表を見てください。
| ポイント | 仕掛品 | 建設仮勘定 |
|---|---|---|
| 意味 | 製造途中の製品の在庫 | 建物や設備の建設費を一時的に記録する勘定科目 |
| 主な使われ方 | 製造業の会計処理 | 建築工事などの資産計上の場合 |
| 資産の種類 | 流動資産 | 固定資産(完成後に資産へ振替) |
| 勘定科目の種類 | 棚卸資産の一部 | 資産の仕訳の仮勘定 |
| 決算での取り扱い | 在庫として計上される | 完成後、固定資産へ振り替えられる |
この表のように、仕掛品は製造の途中段階の製品在庫としての役割を持ち、建設仮勘定は建設中の資産費用を仮に記録しておく“仮置き場”のようなものです。
仕掛品は数か月で完成する製品のための計上で、流動資産。建設仮勘定は建設が長期間かかる大型資産のための仮勘定で、完成後は固定資産になります。
用途や資産区分から全く別のものだと理解すると良いでしょう。
実際の仕訳例でイメージしよう
どんな時に仕掛品や建設仮勘定を使うか、仕訳の例を紹介します。
仕掛品の例:
パン屋さんで小麦粉や砂糖など原材料を使い始め、まだ完成していないパン生地にかかった費用を仕掛品として計上します。
仕訳は簡単に言うとこうなります。
- (借方)仕掛品 100,000円
- (貸方)原材料費 100,000円
製品が完成したら、仕掛品を完成品に振り替えます。
建設仮勘定の例:
会社が新しい工場を建てるために工事費用として支払いをした場合、
- (借方)建設仮勘定 5,000,000円
- (貸方)現金または未払金 5,000,000円
工事が完成したあとに建設仮勘定は固定資産の建物に振り替えます。
- (借方)建物 5,000,000円
- (貸方)建設仮勘定 5,000,000円
このように仕訳の流れも違うことが特徴です。
まとめ:仕掛品と建設仮勘定の違いを押さえて正しい会計処理を
今回は
仕掛品は製造中の製品としての計上で流動資産、建設仮勘定は建物などの資産を造る途中の費用を一時的にためておくための勘定で完成後に固定資産に振り替えるということを説明しました。
この違いを押さえておくことは経理や会計処理を正確に行う上で非常に重要です。
仕掛品と建設仮勘定は似ているようで全く別の目的・使い方をする言葉なので混同しないようにしましょう。
これからもわかりやすく経理や会計のポイントを紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください!
建設仮勘定の話をすると、実は完成までに何カ月も、場合によっては何年もかかる大きな建物や工場の建設費用を全部まとめて一旦“仮置き”する場所なんですよね。
中学生の時に学校の新しい校舎の工事が終わらなくて、完成してもまだ費用の整理が続いていたのを思い出すかもしれません。
経理ではそうした長い時間かかる資産作りの費用をわかりやすく管理するために建設仮勘定を使います。
つまり「大きな物を作る途中の財布」が建設仮勘定なんです!





















