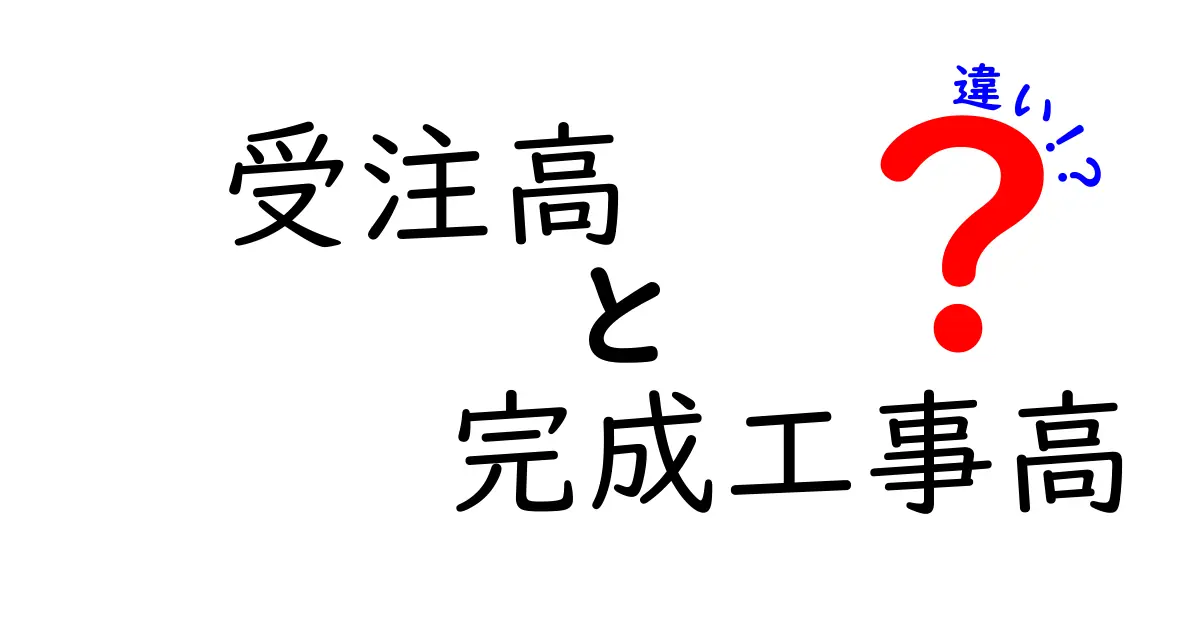

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
受注高と完成工事高の基本情報
建設業や製造業の財務・経営分析でよく使われる言葉に 受注高 と 完成工事高 があります。まずはこの二つの意味をはっきり押さえましょう。受注高 は、期間内に企業が契約を結んだ全ての金額の総額を指します。工事の着工前でも契約が成立していれば受注高に計上されることがあり、案件の規模や見積の確定度によって上下します。これに対して完成工事高 は、実際の工事が完了し、顧客へ引き渡され、請求が完了して売上が確定した金額の総額です。つまり、現場の進捗に直結して“実際に手元に入る収益”を表す指標になります。
この二つの指標は、会計処理のタイミングや現場の進捗状況によって連動しつつも、性質が異なるため、同時に見ることで企業の実力と将来性を正しく読み解く手掛かりになります。
例えば大規模建設案件を複数抱える企業では、長期間の工事が続くため受注高は高くても完成工事高は途中で遅延や変更が入ると伸び悩むことがあります。逆に短期間の小規模案件が多い企業では、受注高の伸びと完成工事高の伸びがほぼ同期するケースが多く、財務諸表上の見え方が安定します。ここで重要なのは、単純に数字の大きさだけを見るのではなく、どの案件がどの段階にあるのか、契約変更や追加工事がどう反映されているのかを理解することです。
さらに、業界用語として バックログ という概念も覚えておくと便利です。バックログは受注残のことを指し、今後の売上につながるまだ在庫化していない受注の総額です。受注高とバックログの関係を追うと、近い将来の事業規模感を予測しやすくなります。
このように、受注高 と 完成工事高 は“過去の契約の量”と“完成した工事の量”を別々に示す指標です。読み方のコツは、両者の定義の違いを押さえつつ、タイムライングラフやプロジェクト別の内訳表を併用して、いつ・どの案件が売上として確定するのかを想像することです。数字の背後にある現場の動きや契約の性質を理解すれば、計画の修正や資金繰りの対策を早く立てられるようになります。
このセクションを読んで、受注高と完成工事高の基本が頭の中に入りましたか?次は、実務での使い分けや注意点を具体的に見ていきましょう。
この二つの数字が示すタイミングと意味
受注高 は契約が確定した瞬間に“潜在的売上”として現れ、案件が現場で動き出す前段階の力強さを示します。企業はこの数字を新規事業の規模感や営業力の指標として用いることが多く、年度計画や資金調達の判断材料にもなります。ただし、受注高の大きさだけでは将来の現金化までの道のりが見えません。案件がどの程度の難易度か、支払い条件はどうなっているか、着工までの承認プロセスに時間がかかるかどうかを加味する必要があります。
完成工事高 は工事が実際に完了して売上として確定するタイミングの金額です。ここには、追加工事の発生、仕様変更、解約といった要因が影響します。完成工事高が伸びている期間は、現場が順調に進んでいることを示しますが、進捗が遅れると一時的に伸びが止まることもあります。会計上は、進行基準と呼ばれるルールに従って売上を認識します。すなわち、工事の進捗度合いに応じて段階的に売上を計上するケースが多く、最終的な完成時点とはタイミングがずれることも珍しくありません。こうした認識のずれを理解しておかないと、年度末の決算で「本来の実力と数字が一致しない」という混乱を招くことになります。
また、現場の実務では、バックログの把握 が重要です。受注残が多い企業は、今後の売上の柱となる案件が複数あると判断できます。しかし、バックログの質にも差があります。契約の難易度が高い、大型で長期の工事か、変更が頻繁に起こるか、回収条件が厳しいか、などの要因を見極めることが、健全な資金計画に直結します。したがって、受注高・完成工事高・バックログの三つを同時に監視することで、現状の実力と未来の見通しをバランスよく把握できるのです。
最後に、数字は「そのままでは語らない」という基本を忘れないことです。業種・企業ごとに契約の取り扱いや認識基準が異なることがあります。自社の会計方針と業界標準を照らし合わせ、必要に応じて財務担当者と現場担当者で情報を共有する習慣をつけましょう。これが、数字を武器にするための第一歩になります。
実務での使い分けと注意点
企業が健全な財務運営を続けるためには、受注高と完成工事高を単独でみるのではなく、総合的に解釈することが大切です。まず、計上タイミングの違いを理解しましょう。受注高は契約成立時点で認識されるのに対し、完成工事高は工事の進捗や完成時点で認識されます。これにより、年度途中での受注高の急増が翌年度の完成工事高の急増には結びつかない場合があります。次に、案件別の内訳を把握します。大口案件が一つでも完了すれば完成工事高の評価は大きく動きますが、複数の小口案件が均等に進む状況では、全体の完成工事高の安定感は増す可能性があります。こうした内訳を管理するには、プロジェクト別の進捗管理表と売上計上表を連携させると効果的です。
また、外部環境の変化にも注意が必要です。金融機関の審査や資金繰りの観点からは、受注高の伸びがそのまま現金化の速度を保証するわけではありません。したがって、現金化の遅れに備えたキャッシュフロー計画を併せて作成することが求められます。最後に、表現の揺れにも注意しましょう。会計基準や業界の慣行は変更されることがあり、最新情報を追うことが重要です。以上の点を踏まえれば、受注高と完成工事高を活用して、より現実的で実用的な経営判断ができるようになります。
表で比べてみる
以下の表は、二つの指標の違いを簡潔に比較するためのものです。実務の場面で自分の会社の数字と照らして使ってみてください。なお、本表はサンプル値です。実際には契約形態や工事規模によって数値は大きく変わります。表の見方として、受注高が増えると将来の売上の期待値が高まる一方、完成工事高は現時点の売上規模を示します。これらを合わせて見れば、資金繰りの安定性や成長の方向性をより正確に把握できるはずです。
友達との雑談の中で、受注高は“これから増える可能性のある仕事の総額”、完成工事高は“今まさに売上として確定している額”と例えると分かりやすいと感じた場面がありました。仮に大型の契約が突然入って受注高が跳ね上がっても、現場の進捗が遅れて完成工事高に影響が出ると、資金の動きにもズレが生じます。だからこそ、営業と現場が別々に動く数字を同じ目線で見ることが大事だと実感しました。数字の裏側には契約の性質・工事の進捗・変更の有無など、多くの要因が絡み合っています。私たちが驚かずに理解できるよう、説明を繰り返し、現場と財務の情報を日常的に結びつける癖をつけたいと思います。
前の記事: « 営業利益と販売利益の違いを徹底解説!中学生にも分かる図解ガイド





















