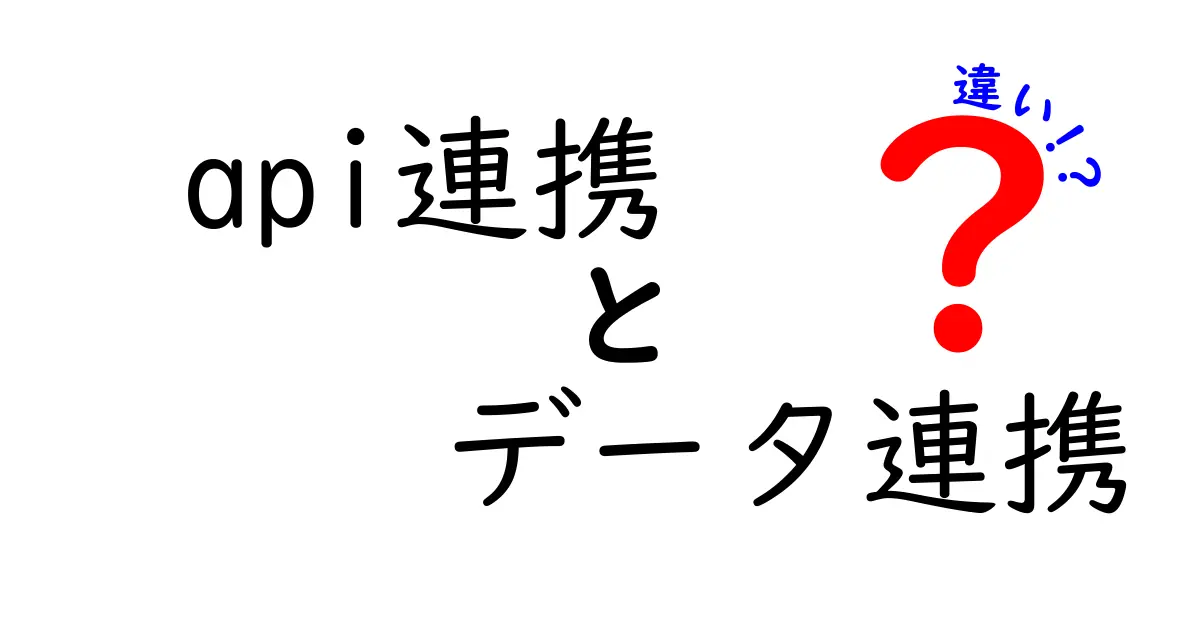

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに API連携とデータ連携の違いをざっくり把握する
現代のIT現場で頻繁に耳にする API連携 と データ連携 は、似ているようで目的や動きが異なります。API連携 は 2つのシステムが直接対話するための契約であり、ある機能やデータを取りにいく際に呼び出す手段です。データ連携 は 複数のデータを統合して別の場所に集める作業全体を指し、処理の方法や時系列が異なる場合があります。したがって API連携 はリアルタイム性を活かす場面に向く一方、データ連携 は大量のデータを定期的に移動・統合する場面で強みを発揮します。ここで重要なのは 2つの連携が同時に使われることがある点です 例えばあるアプリが外部の天気情報を API で取得しつつ、その天気データを自社のデータベースに日次でバックアップする ケースでは API連携とデータ連携が並走します このように 何を目的としているか どのくらいの頻度で更新するか どの程度の正確さが必要か などの条件で使い分けが決まります
次に 表面的なおさらいとして 3つの観点を比較します 対象データ の種類 データの流れ の方向 更新頻度 です
実務の中での要点は エラーハンドリング と セキュリティ の設計が基本となる点です 失敗時の再試行や認証の更新処理をあらかじめ決めておくと 安定性が大きく向上します
このセクションは API連携の考え方の雰囲気をつかむ入り口です 次の章で実例と実務的なコツに話を展開します
API連携の仕組みと実例
API連携の基本的な仕組みは クライアントが API を呼び 出し レスポンスとしてデータを受け取るという流れです ブラウザの利用だけでなく サーバー間の連携にも使われます 通常は REST や GraphQL などの設計ルールに従い http/https を使って通信します
ここで大事なのは 公開 API の契約 すなわちエンドポイントの場所 返ってくるデータの形式 そして認証の方式 です これらを守らなければ動作しません
実例として e コマースの決済連携を考えます 決済サービスの API を呼び出して支払いを作成し 返ってくるレスポンスのステータスを自社の注文管理システムに反映します このときリアルタイム性が求められる場面もあれば 非同期で処理されるケースもあります API連携はこのような「機能を外部の力で拡張する」仕組みです
表形式で基本的な違いを整理します
| 観点 | API連携 | データ連携 |
|---|---|---|
| 対象データ | 機能データやリアルタイムデータ | 履歴データ 大量データ |
| データの流れ | オンライン リアルタイム | バッチ 近接リアルタイム |
| 契約の性質 | API契約 REST など | データフォーマット ETL/ELT |
実践のコツとしては エラーハンドリング と セキュリティ の設計が最初に重要です 失敗時の再試行や認証の更新処理をあらかじめ決めておくと 安定性が大きく向上します
ここまでで API連携の基本的な仕組みと実例の雰囲気がつかめたはずです 次のセクションでは データ連携の特性と使いどころを深掘りします
データ連携の特徴と使いどころ
データ連携は複数の情報源からデータを集め 一つの場所へ統合する活動を指します 代表的な仕組みには ETL や ELT があります ETL は抽出 計算 処理した後にロードする従来型の流れで、データを整える時間がかかります 一方 ELT はデータを先に格納し 後で必要な処理を実行する方法で柔軟性が高くなりました
使いどころとしては 大量の履歴データを分析したい場合 データウェアハウスやデータレイクへの統合が挙げられます 現場では日次や頻度の低い更新で正確性と整合性を重視するケースが多いです しかしリアルタイム性を全く捨てるわけではなく 近接リアルタイムのデータ連携を組み合わせることも一般的です
注意点 は 1) データの品質 2) 同一性の維持 3) データの流れの監視 です この3つを満たすことがデータ連携の成功の鍵になります 例えば顧客データの統合では同姓同名の誤認識を避けるための一意の識別子の設計が欠かせません またデータの更新履歴を追えるように ログを適切に保管することも重要です
友達とカフェで雑談する感じで 今日は API連携 という言葉を深掘りします 互いのスマホアプリが どうやって情報を交換しているのか という素朴な疑問から始めます API連携は 外部のサービスに頼って機能を拡張する仕組みです でも同時に その契約を守ることが大事で 返ってくるデータの意味や形式が決められている点がミソです 難しく聞こえるかもしれませんが 実際には どんな場面で どれくらいの頻度で どの程度の正確さが必要かを考えるだけで使い分けの道筋が見えてきます 具体的には 決済情報を瞬時に取得する API と 大容量の顧客履歴を蓄積するデータ連携 を組み合わせる場面が身近です こうした話を友だちと共有するだけで 理解が深まり 自分の現場にも落とし込みやすくなるでしょう





















