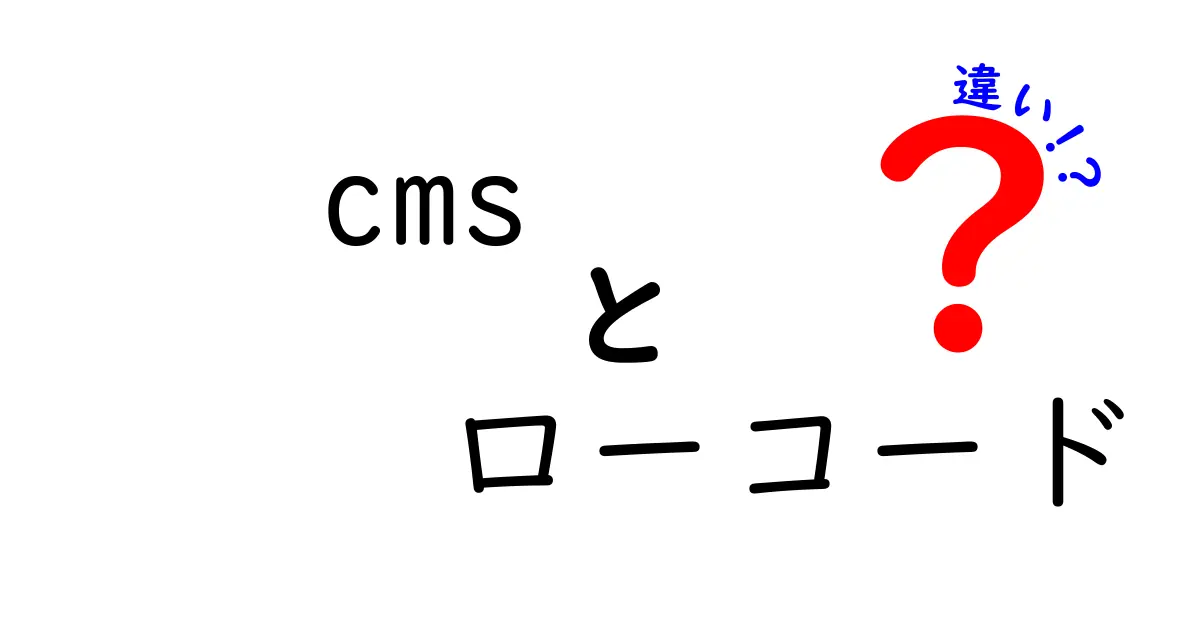

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:CMSとローコードの違いを正しく知ろう
まずは前提をそろえよう。CMSは「コンテンツを管理するための仕組み」です。ウェブサイトの記事や画像、ページの構成などを、専門の人が分かりやすく整理・公開できるようにする道具。反対にローコードは「最小限のコードでアプリを作る方法」です。見た目は難しく見えるかもしれないけれど、実は部品を組み合わせる感覚で新しい機能を作れる道具です。
CMSは“情報の整理と公開の流れ”を整えるのが得意で、ローコードは“動く機能をすばやく作り出す”のが得意です。ここをはっきり分けておくと、何を作るか、誰が使うか、どんな運用をしたいかが見えてきます。
たとえば、学校のサイトなら記事の管理やカテゴリ分け、公開ワークフローが中心になるのでCMSが適しています。一方で、部活動の出欠管理アプリやイベント申込フォームなどの新規機能をサクッと作りたいときにはローコードが活躍します。
もちろん、両者を同時に使うケースも多いです。CMSとローコードを組み合わせると、情報の安定運用と機能追加の両立がしやすくなります。このような組み合わせを「ハイブリッド運用」と呼ぶこともあります。
このセクションでは、違いをただ覚えるだけでなく、どういう場面でどちらを選ぶべきかという観点も紹介します。
まずは用語の背景と基本の考え方を押さえ、次のセクションで実務での使い分けを具体的に見ていきます。
実務での見極め方:どちらを選ぶべきか?
現場の実務では、目的が何かによって選択が変わります。「記事を中心に管理する」「公開までのルールを厳格に守る」なら CMS が最も安定します。逆に「短時間で新機能を追加したい」「コードを書かずにアプリを作りたい」場合にはローコードが力を発揮します。以下のポイントを参考にすると、迷いを減らせます。
1) 目的と対象ユーザー:誰が何を使うのかを決める。
2) 拡張性と連携:将来的にどう機能を増やすのか。
3) 学習コストと運用:導入後の人材育成と日常の運用負荷。
4) コストとベンダーロックイン:長期的な費用と制約を確認。
5) セキュリティと規制対応:データの取り扱いルールを満たすか。
このような観点を頭に置くと、CMSは「安定運用の土台」として、ローコードは「新機能の入口」として、それぞれの役割がはっきり見えてきます。
さらに実務では「ともに使うべき場面」が多いです。例えば、サイトのコンテンツはCMSで管理しつつ、特定のイベント申込フォームだけローコードで作る、そんな組み合わせが現場ではよく見られます。
この章のまとめとしては、目的と作業範囲を分けて考え、後から必要な機能を柔軟に追加できるかを事前に検討することです。長い目で見れば、CMSとローコードの両方の長所を活かせる体制が、最も堅ろで持続的なIT基盤を作ります。
ローコードを語るとき、私たちはつい“楽そうに見えるけど本当はどうなのか”という疑問にぶつかります。ローコードは確かに短時間で動く部品を組み立てられる便利道具だけれど、同時に“設計の正確さ”が問われる場面が多いということです。ローコードのプラットフォームは、ドラッグ&ドロップの部品を並べるだけで動くアプリの雛形を提供します。だから初心者でも作業感を味わえるのは大きな利点。ただし、後から機能を追加したいときに、部品の限界に引っかかることがあるのです。だからこそ、計画段階で「データの流れ」「イベントの順序」「権限の設計」をしっかり決めておく必要があります。私はその点を友達に説明するとき、こんな比喩を使います。ローコードはレゴブロックのようなもの。基本ブロックだけでは大きな建築は作れず、設計図と追加ブロック、そして時には小さなコードのパーツが必要になる。CMSと組み合わせると、コンテンツを安定して運用しつつ、機能の追加を素早く実現できるようになるのです。つまり、「使い勝手の良さ」と「堅牢さ」の両立を目指すことが大事。最後に、学ぶ姿勢は欠かせません。新しいローコードの機能が出てきたら、すぐに試してみて、データの取り扱い、セキュリティ、運用のルールを自分なりに整えていく。そんな小さな積み重ねが、長く使える力になるのです。今日の話題は、友人との雑談風にできるだけ平易に話すことを心がけました。





















