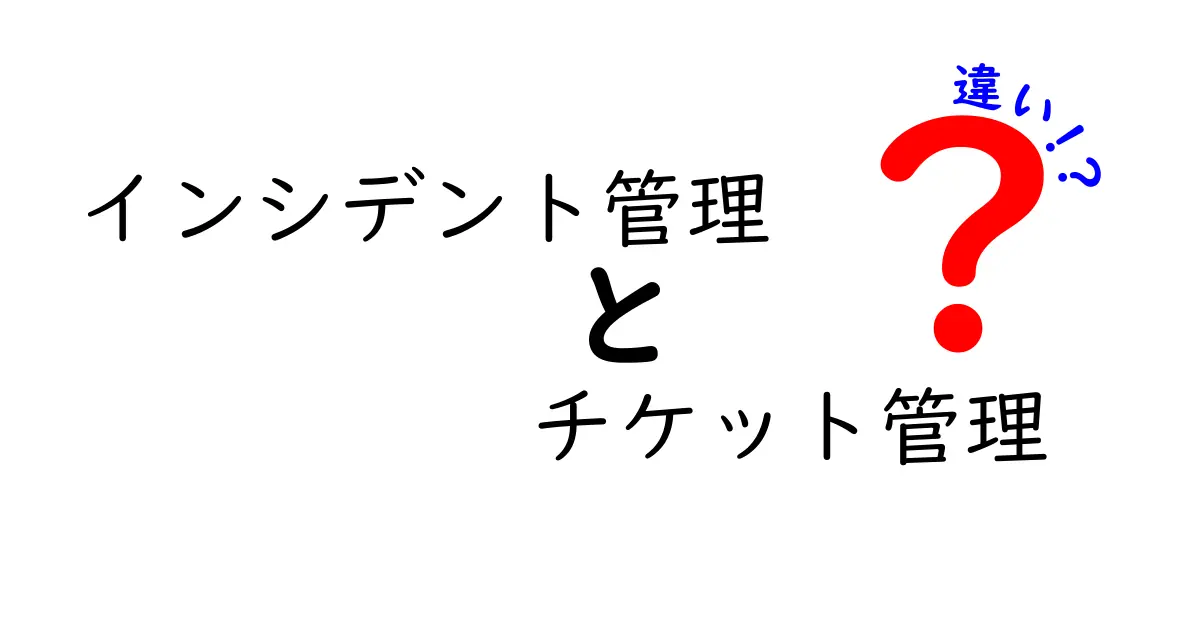

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
インシデント管理とチケット管理の基本を押さえる
インシデント管理とチケット管理はITサービス運用の現場で頻繁に名前が出ますが、混同されやすい点があります。インシデント管理はサービスの停止や品質低下といった利用者への影響を最速で回復させるための枠組みです。対してチケット管理は個別の依頼や作業を追跡・可視化するための記録手法であり、情報の整理と作業の透明性を高めることを目的とします。両者は互いに補完し合いますが、目的の焦点が異なるため、現場では定義と手順を分けておくことが重要です。ここでは順を追って、それぞれの本質と使い分けのコツを詳しく解説します。
実務の現場では、インシデントを受けたら影響範囲を速やかに評価し、適切な担当者へエスカレーションすることが基本です。同時に、個別の依頼をチケットとして管理することで対応状況を誰でも共有でき、後の振り返りや改善の材料にもなります。これらを分けて運用することで、混乱を避けつつ効率を高める体制を作ることができます。
インシデント管理とは何か?役割と目的
インシデント管理はサービスの中断や品質低下といった影響を受けている状況を速やかに安定させ、利用者の影響を最小化することを主目的とします。ここでの三つの柱は、影響範囲の把握、迅速な復旧、恒久対策の検討と再発防止です。現場では監視アラートを受け取ると、誰が何をすべきかを即座に判断し、適切な人員へエスカレーションします。記録には発生時刻・影響を受けたサービス・対応経緯・決定事項などを漏れなく残し、後の分析に活用します。これにより復旧時間を短縮し、同様の問題が再発するリスクを抑えることができます。
チケット管理とは何か?役割と目的
チケット管理は個々の作業依頼や改善要望、質問といった<作業単位>を追跡・整理する仕組みです。目的は作業の可視化と履歴の蓄積、担当者の割り当てと期日管理、進捗の共有です。現場ではチケットごとに優先度・期限・担当者・ステータスを設定し、解決までの流れを一つの単位として可視化します。これによりチーム全体が「誰が何をいつまでにやるのか」を正確に把握でき、無駄な手戻りを減らします。適切なチケット運用は顧客対応の透明性を高め、振り返り時の改善点抽出を容易にします。
両者の違いを整理するポイント
両者の違いを理解する第一歩は焦点の違いを意識することです。インシデント管理は「影響を与える問題そのものの回復」を最優先に扱い、サービスの稼働を最短時間で取り戻すことを目的とします。一方でチケット管理は「個別作業の記録と進捗管理」を重視し、作業の可視化と履歴の蓄積を通じて品質改善や再現性の向上を図ります。ポイントとしては、インシデントとチケットを同じ口座に入れて混同するのではなく、インシデントは大きなイベント、チケットは個別作業の単位と捉えることです。さらに、データの粒度の差にも注意します。インシデントは広い影響範囲と判断が必要ですが、チケットは細かな作業手順や担当者の割り当て、完了時刻などの細部情報を管理します。
実務での使い分けと流れ
現場での基本的な流れは次のとおりです。まず、監視・問合せ・報告などのきっかけでインシデントを認識します。これを受けて影響範囲と優先度を決定し、適切なエスカレーションを行います。その後、暫定復旧策を実施し、サービスを回復させつつ、影響範囲をさらに絞り込み、暫定対策から恒久対策へ移行します。同時に、個別依頼や作業をチケットとして登録します。チケットは担当者割り当て、作業手順、進捗、完了報告、再発防止策などを含め、完了時にクローズします。インシデントの終息と同時に、関連するチケットの完了・関連性の整理を行い、同様の問題を防ぐための知見として蓄積します。現場での実務のコツは、情報の整合性を保つことと、エスカレーションの基準を事前に決めておくことです。
表で比較:用語・目的・手段・指標
| 項目 | インシデント管理 | チケット管理 |
|---|---|---|
| 定義 | サービス停止や影響を最小化する枠組み | 個別作業を追跡・整理する枠組み |
| 主な目的 | 速やかな復旧と再発防止 | 作業の可視化と履歴の蓄積 |
| 対象となる情報 | 影響範囲・復旧状況・エスカレーション | |
| 指標例 | 復旧時間 RTO、影響度、再発率 | |
| 作業の流れの特徴 | 迅速な判断と対応の連携 | |
| 情報の粒度 | 大局的・影響範囲中心 | |
| 管理の対象 | サービス全体の安定性 | |
| チケットとの関係 | インシデントは上位のイベント、チケットは作業単位 |
まとめと実務のコツ
要点を振り返ると、インシデント管理とチケット管理は今ある課題を整理するための異なる視点の道具です。両者を適切に使い分けることが、サービスの信頼性を高め、顧客満足度を向上させます。実務のコツは、はじめに定義を明確にすること、影響範囲と作業履歴を分けて記録すること、そして定期的な振り返りで再発防止策を更新することです。これらを習慣化すれば、混乱を避け、効率的な運用が実現します。
友達と雑談している感覚で話しますね。ねえ、インシデント管理とチケット管理って同じようで違うんだよ。インシデントは“今この瞬間に困ってる人”を救うための大きな ха憂の回復作業の話。チケット管理はその大きな出来事を小さな作業に分解して、誰が何をいつまでにやるのかを追跡する作業日誌みたいなもの。だから、インシデントは“何が起きたかと影響の範囲”を追う、チケットは“具体的な作業と進捗”を追う、そんな感じかな。両方を組み合わせると、急なトラブルにもすぐ対応できて、後から振り返ってどう直したかをきちんと記録できるんだ。仮に同じ問題が起きても、過去のデータがあれば早く原因を掴んで再発を減らせるんだよ。





















